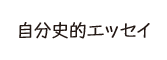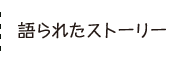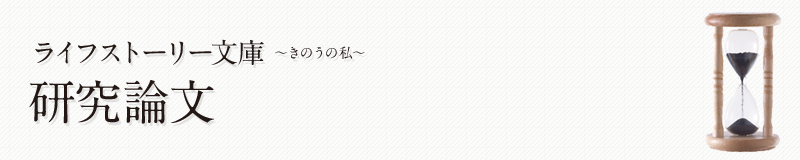
運営:椙山女学園大学国際コミュニケーション学部「ライフストーリー文庫~きのうの私~」編集室

| 2013.04.30 |
ライフストーリーセンター構築によるストーリーの社会学的研究 第6章 授業活動とライフストーリー制作 |
(横家 純一) |

はじめに
「ライフヒストリー研究」という授業の中で、学生たちにインタビュー調査とその記録の提出をお願いしている。その結果、毎年、何点かの作品ができ上がる。その中から、人びとのライフストーリーとして価値あるものを選びだし、作品として公開している。また、卒論のデータとして、「語られたストーリー」や「自分史的エッセイ」を利用したもののうち、やはり、ライフストーリーとしてふさわしいものを選び、公開したものもある。いうまでもなく、いずれも同意書をもらっている。
何をもって、「価値あるもの」とか「ふさわしいもの」とみなしているのかという議論は、別の機会にゆずり、ここでは、これまでの授業活動における、書物として手にとって読みこむという過程が、ディスプレイ上の文字をながめる作業に置き換わったことの意味について考えてみたい。
前者は、近くにあるものをいつくしむ、いわば求心的な態度であるのにたいして、後者は、遠くにあるものを見つづける、いわば遠心的な態度といえよう。求心的な態度では、大切なものがいま・ここにあること、つまり定着していることを前提としているため、その場での議論が深まりやすい。それにたいして、ウェブ公開に不可避である遠心的な態度においては、どうやら本質的なものはいつか・どこかにある、あるいはまた、ゆれ動くものこそが本質である、というような想定を伴っているためか、議論が深まりにくい。さらにいえば、もうすでに、議論がしつくされているかのような印象さえうける。
1.制作の動機づけ
通常15回の授業の中で、それぞれの受講生が、一人の語り手にたいして、60分以上のインタビューをし、その結果を、1本の作品とする。ライフヒストリーというものに、はじめて出会う学生に対して、その概要を説明することは、容易ではない。いくつかの工夫が必要となる。
まず手はじめとして、学生たちのふだんの日常生活と命(ライフ)との接点をさぐる。言いかえると、人間の「働きかけ合い」⑴の中で生まれる命(ライフ)の輝きを指摘する。たとえば、つぎの事例1や事例2のような、命(ライフ)の輝きが絶頂にたっする転機や節目の紹介は、効果的である。
この事例1は、身体的にも精神的にも、ギリギリの「どん底」に追い詰められた語り手が、神に向かって、「責任取れ!」「文句あるか!」とせまると、神から、「文句なし!」という応えが返ってくる場面である。言い換えると、「文句なし!」という神の言葉を、語り手が訊きとるという、奇蹟の場面でもある。これにたいして、科学的な見地から、「そんなはずはない」と断定することほど、ライフストーリー研究の立場から遠いものはない。人の主観の偉大さを読み取るのが、ライフストーリーの醍醐味であるからだ。ただし、受講生たちは、この段階ではまだ、狐につままれたような、半信半疑の状態にとり残されたままである。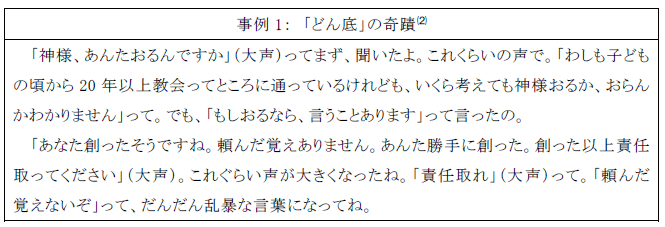 つぎの事例2は、彼女につられて、大学に入った語り手が、彼女にふられたため目標を失い、一応、サッカー部に所属しながらも、孤独な毎日をやり過ごしている場面である。
つぎの事例2は、彼女につられて、大学に入った語り手が、彼女にふられたため目標を失い、一応、サッカー部に所属しながらも、孤独な毎日をやり過ごしている場面である。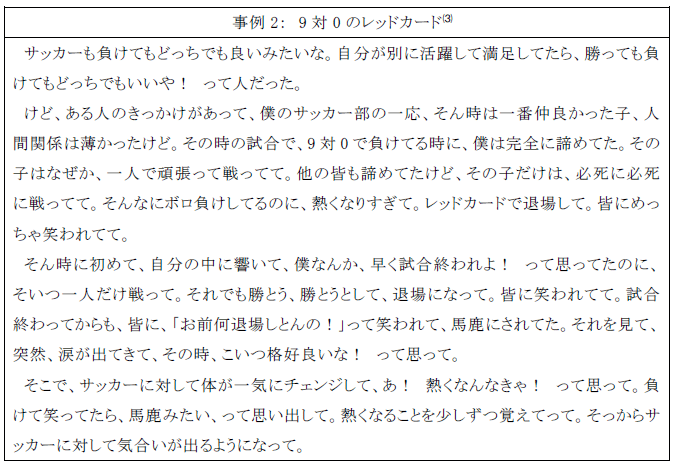 9対0の負けでのレッドカード退場という、「その子」の無謀な行動が、語り手の突然の涙をさそう瞬間は、神こそ出てこないが、事例1の奇蹟体験と等価であろう。周囲に笑われようが、いや、そうであるからこそ、自分の「熱くなんなきゃ!」という思いの優位性が確認でき、それにつづく行動選択の正当性までを保証したのである。
9対0の負けでのレッドカード退場という、「その子」の無謀な行動が、語り手の突然の涙をさそう瞬間は、神こそ出てこないが、事例1の奇蹟体験と等価であろう。周囲に笑われようが、いや、そうであるからこそ、自分の「熱くなんなきゃ!」という思いの優位性が確認でき、それにつづく行動選択の正当性までを保証したのである。
このような事例にふれると、不思議なことに、どんな受身的な受講生であっても、そこに登場する他者の人生に興味をもつようになる。そして、このことがさらに加速すると、実際の聞き取りの場面で、他人の人生が自分の人生の指針になるかもしれないという気づきにもつながる。それはいわば、まっとうな社会認識の形成プロセスともいえる。
2.語り手さがし
以上のような、先行研究の「味わい」⑷をすすめるにつれ、しだいに、自分独自の語り手さがしがはじまる。これまでの多くの作品が示すように、この語り手さがしほど学生たちを苦しめるものはない。たとえば、つぎのような事例がある。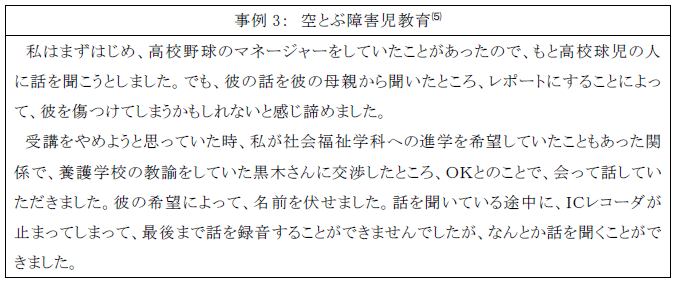 この事例3は、「彼を傷つけてしまうかもしれない」という母の忠告を、たんなる「おせっかい」とみなすことのできなかった学生の見識の限界を示しているだけでなく、われわれの人生が、そういった人と人との働きかけ合いにより形成されていることの、具体的な実践報告とみなすべきであろう。それにしても、学生に、せっかくの授業の「受講をやめようと思っていた」といわせるほどの、重荷はいったいなんなのか。
この事例3は、「彼を傷つけてしまうかもしれない」という母の忠告を、たんなる「おせっかい」とみなすことのできなかった学生の見識の限界を示しているだけでなく、われわれの人生が、そういった人と人との働きかけ合いにより形成されていることの、具体的な実践報告とみなすべきであろう。それにしても、学生に、せっかくの授業の「受講をやめようと思っていた」といわせるほどの、重荷はいったいなんなのか。
「語り手さがし」の重荷とは、住みなれたふだんの生活空間とはやや違ったところへ、自分の意思で出向き、自分が何者であるのかを説明しつつ、他者と交渉しなければならないプロセスからくる。多くの場合、それは、おそらく初めての経験であり、実行力や意欲が乏しい場合は、周囲の圧力により、すぐさま挫折という結果になってしまう。しかしそうであるからこそ、このプロセスで学べることも多い。自分のために、誰かに動いてもらうよう依頼し、相手の厚意にたいして感謝すること、そうすると逆に、自分の中に、人に支えられたという安心感がうまれ、かつ、自分の働きかけが相手に喜んでもらえるかもしれない、という貴重な体験となるからだ。
語り手さがしと前後して、ICレコーダの操作実習をする。実際に、自分の声を録音・再生することは、たんにその技術習得が目的ではない。インタビューされる人の気持ちや戸惑いを思いやり、それにきちんと対処するという、重要な学習を伴っているのである。この経験ののち、実際にインタビューを開始する。インタビューは、通常、1回で終了するが、相手や自分の都合で、2回以上の面会になることもある。
ここでの注意点は、いうまでもなく、録音に頼りきってしまうことの危険性を指摘することである。聞かせていただいているという態度を示しつづけるというマナー上の問題のほかに、その場でメモをとることで、音声表現の曖昧さを確認し、補完することもできるからだ。
3.文章化の作業
こうしてようやく、文章化の作業がはじまる。第2章でも述べたが、そもそも、聞き取りは音声言語である以上、漢字があるわけでもないし、点やマルもない。改行もなければ、カギかっこもない。これらすべては、編集者の裁量で決まる。加工することもあり、創作することだってある。かといって、それがすべて、恣意的であるとはいえない。この点にかんして、桜井厚は、さいきんの著書で、つぎのように言っている。
インタビューが個々の語りの解釈を語り手と交渉していくコミュニケーション過程であることを認めた
上で、トランスクリプトをもとに、さらなる解釈をともなう最終的なストーリーを描く権限は、調査者側に
あることだけは確認しておきたい⑹。
この「最終的なストーリーを描く権限」という、やや力強い表現が、「インタビューの倫理」と題された章での指摘であることを考えると、編集の恣意性といったレベルをつきぬけて、この研究の可能性を称揚しているように思われてならない。
そもそも、音声を文字に変換・加工する技術と実践の中に、人の文化活動の醍醐味をみつけることができる、と力説したい。いくら、ライフストーリーをめぐる音声や映像のアーカイブ化の流れがすすんでも、このような文字文化のもつ創造性を排除することはないだろう。
文章が完成したからといって、終了ではない。ベタ打ちを、読み物に変換する編集がまっているからだ。ここでもっとも重要なのは、タイトル決めである。語り手の生き方の、いわば、「テーマ」⑺をつかみとり、それを印象づける10字ほどの文を考案しなければならないからだ。テーマ選びのベストな方法は、まず全文にわたって小見出しをつけ、それらを貫くメッセージをみつけることである。
しかし、いうまでもなく、人の人生テーマは、一つでない。タイトルが一つである以上、そこには矛盾が生ずる。編集者の仕事は、締め切りのギリギリまで、この二つ以上のものから、一つを選び出すという、強調・焦点化の作業である。だからといって、限界があるという消極的見解をもっているわけではない。しょせん、といっては聞こえが悪いが、人間の活動である以上、バイアスはつきものと考えるべきであろう。絶対的な真実をつかむことは不可能と考えた方が、安全である。むしろ、このようなバイアスの中で〈ゆらぐ〉ものこそ、真実であり、われわれが探しもとめているものかもしれない。
4.作品の考察
さいごに、作品の分析・考察について考えてみたい。これはおもに、研究者や卒論執筆者によってなされるものだが、おおきくわけて、二つある。ある特定の作品を1点とりあげ、その語り手の人生全般について詳細に検討していくもの。もう一つは、いくつかの作品をならべて、それらの特徴について比較するものである。
前者の場合、語り手が生きた時代背景はもとより、その親族関係、交友関係、職業生活で遭遇した転機や重要な他者をめぐる考察がおもな作業となる。後者は、たとえば、「検閲」という視点から、しゃべりすぎてしまったことを語り手自身が反省し、編集の段階で言い換えたり、カットしたりする行為の背後に見え隠れする信念を発見することである。ここには、読みやすくするためにストーリーを加工する、編集者の姿勢についての議論もふくまれよう ⑻。
ただし、「ライフヒストリー研究」といえども、通常の授業では、ここまでの展開はない。にもかかわらず、たとえばつぎのような、提出レポートの中の「おわりに」という文章から察すると、受講生は、「ライフヒストリー研究」という授業をとおして、「一人一人違う人生を歩んでいる」という世界観とともに、「毎日ちゃんと生きなくちゃ」という前向きな人生観を獲得しているらしいことが、やや手前味噌ではあるが、窺えよう。
この授業を受けて思うこと。世界にはたくさんの人がいて、一人一人考えが違い、一人一人違う
人生を歩んでいる。現在だけでなく、過去にも、そして未来も……。そうやって考えると、
私は、変な気持ちになる。毎日ちゃんと生きなくちゃ、とも思う。なぜか、人に優しくしなくちゃ、とも思う。
そうやって考えさせる授業は、初めてだ。こんな重い授業だったっけ(笑)⑼。
注
(1)1989年のある授業の中で、当時中京大学の教授であった中野卓は、「働きかけ合い」について、つぎのように述べている。
その人との生活の絡み合いの中で、その人が自分の生活とどういうふうに関係したか、その人から
どういう影響を受けたか、その人にどういう影響を与えたか、というふうな、お互いの相互作用、
働きかけ合いというものが、その人の歴史を作ってきた、そういう話が自然と出てくる。
個人と個人との間の出会い、そして影響の与え合い、そういう共同生活、あるいは協力生活。
(田口純一編『こころの運動会』、北樹出版、1994:239)
ライフヒストリー研究については、通常、「相互作用」といったやや淡白で、物理的な定義で終わらせていることが多いが、これだけ簡潔で、しかも要をえた説明は、ほかにないだろう。それは、「働きかけ合い」や「影響の与え合い」といった、人間の営みへの、あたたかい、かつ、するどいまなざしを表現しているともいえる。
(2)塚田守「「決定的瞬間」についての語りの考察」『言語と表現 第7号』、椙山女学園大学国際コミュニケーション学部紀要、2010:24。
(3)武川まり・杉浦那津美「触るじゃん! やっぱり。」、横家純一編『バナナパフェ―椙大生活史研究 第3号』、2008:38。
(4)有末賢は、生活史研究が主題的に興味をもたれた場合、「「こんな人間もいる」というようなユニークで、珍しい体験や生き方や「語り」を収集し、それを味わい、楽しむという「読み方」」が行われるとしている。『生活史宣言』、慶應義塾大学出版会、2012:4。
(5)鈴木とも子「空とぶ障害児教育」、横家純一編『ミラクル・ハンター―椙大生活史研究 第1号』、2002:69。
(6)桜井厚『ライフストーリー論』、弘文堂、2012:168。
(7)「テーマ」について、中野卓はつぎのように言っている。
ライフ・ヒストリーは私達が調査を通じて、ライフ・ストーリーとして聞くわけです。相手は自分の
生活の、生涯の、あるいは半生の物語として、お話をしてくれるのです。初めがあって終わりがある。
それから、強調している点がある。何かの点を強調している。生活史にはテーマがある。私の生涯の
中でこういうことが大切だったと思う。こういうことだけはあなたに話しておきたいんだ。このことは
どうしてもわかって欲しいんだ。あるいは、そのとき私はこういうふうに考えたんですよ……というふうな、
その人が重要だと思っていることを、強調しながら話してくれることです。
それは、主観的な話です。その人が現在そう思っているという話。ですから、人にたいする誤解も
あるかもわからないし、人にたいする愛情をこめて、美化して話すかもわからない。
それでも構いません。その人が自分の人生をどう考えているかを、知りたいのですから。
田口純一前掲書(1994:240-241)
この時点(1994年)で、「ライフ・ストーリー」と発言していることもさることながら、われわれの人生にはテーマがある、と宣言することで、人の命の活動を高らかに謳いあげているようでもある。
(8)たとえば、口述と記述のあいだにひそむ緊張関係を考察したケースとして、田口純一「自己検閲の論理と心情」(『解放社会学研究、第6号』、1992:113-124)がある。そこでは、いったん口述された個人の生活史が、編集者によって記述されるプロセスにおいて、語り手自身により“検閲”をうけるケース――小さなものでは、単純な思い違いや表現上のミス、大きなものでは、民族差別表現とか体制批判の言説――の検討がなされている。
(9)森美穂「ボケボケするな!」、横家純一編『至福のとき―椙大生活史研究 第2号』、2007:127-128。
森美穂が、「重い授業だったっけ(笑)」という名言を残してくれたのが、2006年。それから5年後、つぎのような受講生に出会えたことを、ここに付記しておきたい。
この人は、自分の卒論のデータとして、8万字をこえる「自分史的エッセイ」(その約4分の3が、こんかいの「就活戦士ハルカ」(第一期)、「ハルカ第2章―オーラ奪回作戦―」(第二期)として結実している)をしたため、そのノリで、卒業後、自発的に語り手をさがし、インタビュー取材(第三期の「見えてきた自分の役割」と「見えてきた自分の挑戦」として結実している)を試みたのである。やや例外的ではあるが、人の人生をきくことと、自分の人生をふりかえることが、一つの人生の表裏一体の関係であることを、われわれに教えてくれる、貴重なケースといえよう。