目 次
第1章 本研究の概要と現状 塚田 守 1
第2章 ライフストーリーのウェブ公開 横家 純一 11
第3章 ライフストーリー研究の概観――インタビューを中心に 川又 俊則 19
第4章 ライフストーリー研究の概観――自分史作品を中心に 塚田 守 35
第5章 聞き取りをベースにしたストーリー――さまざまな人びとのライフストーリー研究を中心に 川又 俊則 43
第6章 授業活動とライフストーリー制作 横家 純一 59
第7章 物語としての「自分史的エッセイ」の教育実践とストーリーの社会学的分析の可能性 塚田 守 67
第8章 結論:ライフストーリーの発信と教育的効果 塚田 守 99
〔執筆者〕
塚田 守: 椙山女学園大学国際コミュニケーション学部 教授
川又 俊則: 鈴鹿短期大学 教授
横家 純一: 椙山女学園大学国際コミュニケーション学部 教授
1.研究目的
「ライフストーリーセンター構築によるストーリーの社会学的研究」は、個人が自らの言葉で綴った「自己のライフストーリー」とインタビューによって聞き取られた「他者のライフストーリー」を収集しデジタル化した上で、分類、インデックス化することで、ライフストーリーのアーカイヴを構築し、一般に公開するためのライフストーリーセンターを創設することを目的とした。そのセンターに多様なライフストーリーをアーカイヴ化し、研究者には研究するためのデータを提供し、一般の人びとには「自己のライフストーリー」を書く機会と「他者のライフストーリー」を読む機会を提供し、自らの人生について再考する場を提供しようと考え、このプロジェクトが2010年4月から始められた。
2.ストーリーのアーカイヴ化の現状
研究開始の2010年において、海外では、データのアーカイヴ化への動きはさまざまな分野ですすめられていたが、Denshoに代表されるような日系アメリカ人の歴史に限定したアーカイヴ化、海外のオーラルヒストリー・プロジェクトを実施しているセンターでは、「個人のライフストーリー」をデジタル化し、映像あるいは文章でアーカイヴ化し、歴史的記憶として記録する試みが行われている。たとえば、アメリカのBaylor University, Institute for Oral Historyがそれにあたる。また、南メイン州立大学のLife Story Centerでは歴史的な記憶を記録として残すために、訓練を受けた学生がインタビューをしたストーリーをアーカイヴ化し、一般の人びとに公開している。
しかし、日本においては、人びとのストーリーをアーカイヴ化する試みは、一般的には、特定のテーマに基づいたものに限定されたものである。たとえば、神戸大学の異文化交流センターは外国人労働者のストーリーをアーカイヴ化しているが、それは、一般の人びとに公開されることを目的とせず、実態調査のためのアーカイヴ化である。また、「戦争体験放映保存の会」のように歴史的記録として、戦争体験の継承を目的として、映像による証言を保存しようとしているところもある。2013年の時点で、広くアーカイヴ化を行っているDPIXx Japanは、ガン患者の語りを映像でアーカイヴ化している。
個人のレベルでのアーカイヴ化の例として、北星学園大学の吉田氏による『オーラルヒストリーの映像アーカイヴの構築及びウェブ上での公開に関わる諸条件の研究』(2007年)がある。海外でのアーカイヴ化を実践している例を紹介、参考にしながら、それらを、大学のホームページに、北海道におけるアイヌの人びとの歴史と現状について映像を用いたインタビューをアップしている。このような試みはまだ日本ではあまり行われていない。
機関のレベルでは、たとえば国立公文書館アジア歴史資料センターが行っているような、歴史的ドキュメントのアーカイヴ化は、予算的措置とアーカイヴ化の専門家がかかわることで、広く利用できるようになっているようである。また、香川県立文書館でも、公文書に関するアーカイヴ化は進んでいるようである。しかし、社会学研究で求められているような質的データのアーカイヴ化は、あまり進んでいないようである。「質的データ・アーカイヴ化」の現状に関する全国実態調査は行われたが、その中間発表でも、質的データを共有するアーカイヴ化の問題点は多く指摘されている。どのような問題点があるかは、この調査の分析結果に期待したい。
3.アメリカにおけるアーカイヴ化の試み:南メイン州立大学のライフストーリーセンターの場合
(1)設立の趣旨
ライフストーリーセンターは、その設立趣旨を次のように述べている。
人はだれでも自らが生きてきた「人生」について重要なストーリーをもっているという信念に基づいて設立。センターはこの20年間、人びとのライフストーリーを称賛し、全ての世代の間でライフストーリーを共有することで「コミュニティの絆」を強化することをその使命としてきた。すべての世代、多様な背景をもつ人びとのライフストーリーを記録し、保存することによって、この使命を果たしてきた。そして、また、このセンターは、お互いのライフストーリーから学ぶことに興味をもつすべての人びとの出会いの場を提供する役割も果たしている。
(2) センターの最初の10年の歩み
The Center for the Study of Lives(生活研究センター)という名前で、ロバート・アトキンソン氏が南メイン州立大学「教育と人間発達学部」の一つ部署として、大学の運営委員会の下、個人の研究室に1988年に設立。1998年頃までには、約200のライフストーリーを保存している。
それぞれのライフストーリーは、アトキンソン氏が担当する大学院の授業「ライフストリーリー、個人的神話の創造、精神的発達(HRD 693 Life Stories, Personal Mythmaking, and Spiritual Development)の課題の一つとして、学生がインタビューを行い、それをライフストーリーとしてまとめ、課題レポートとして提出されたものを、アトキンソン氏自身あるいは助手の大学院生が編集、校正して、ホームページにアップするという方式をとっている。この大学院の授業では、カウセラーをめざす大学院生が多く、日本の学生よりは、はるかに年齢層が高く、多様なストーリーがアーカイヴ化されている。最近は、プライバシーの保護の意識が高くなり、課題として提出された者のうち、およそ3分の1程度しか、掲載同意書に同意していない状態であるが、センターは20年以上の歴史をもっており、アーカイヴ化されたストーリーの蓄積は270以上になっている(アトキンソン:2013年3月4日)。アーカイヴ化されたストーリーには、①インタビューされた人物の名前、②性別、③出生地、アメリカの州あるいは国名、④インタビュー時点での居住地、⑤民族、⑥インタビュアの名前が書かれている。
10周年記念として、全国のライフストーリーのアーカイヴ化を評価する代表的な人による講演会が行われた。
On October 1, 1998, Derald Wing Sue, an Asian-American counseling psychologist
at California State University, Hayward, spoke on
“How Truthful Narratives Heal and Connect.”
This was followed on Friday, October 2 by an interactive discussion group with
Dr. Sue and community members on the topic, “Healing and Connecting through
Narratives in Asian-American Community.”
On October, 15, 1998, William Ferris, Chairman of the National Endowment for the
Humanities, spoke on “Culture and the Voice of Wisdom.” Read his keynote speech
for the Center's 10th Anniversary.
On October 29, 1998, Sara Lawrence-Lightfoot, an African-American professor of
education at Harvard University, spoke on “Remembering a Life the Way it Really Was.”
(3)センターの2008年から現在までの展開
2008年、20周年を記念して、ナラティヴやライフストーリー研究が社会的に認知された段階で、センターの名前を「生活研究センター」(the Center for the Study of Lives)から「ライフストーリーセンター」(the Life Story Center)に変え、個人のライフストーリーを保存し、共有することの重要性をさらに強調する方向に転換していった。そして、20周の記念として、ベストセラー作家、研究者、カウンセラーであるトーマス・モアが、“Narrative, Dream, and the Life of the Soul”(「ナラティヴ、夢、魂の生活」)という講演を行い、それをデジタル保存した。
具体的にウェブページの展開と修正が行われた。
まず第1に、投稿が自由にできるインターアクテイヴなウェブページに修正することにより、一般の人びとからの投稿が可能になり、そのアーカイヴ化されたライフストーリーのキーワードによる検索も簡単になり、センター自体がウェブ時代の変化に伴って発展した。そして、センター長であるアトキンソン自身はブログを書き始め、今考えている本や論文に関するエッセイを継続的に掲載している。また、文献として、ライフストーリーを書く方法などに関する文献などもセンターに掲載し、ホームページを閲覧した人が、どのようにライフストーリーを書くかの参考にできるようにしている(The Gift of Stories, 1995、 Heart and Craft of Lifestory Writing 2007など)。
次に、全国的ネットワークの展開として、2008年、センターの設置場所を「教育と人間発達学部」の個人の研究室から、南メイン州立大学のポートランドキャンパスに設置された新しいウィッシュキャンパーセンターにあるThe OLLI(the Osher Lifelong Learning Institutes) National Resource Centerに移転され、アトキンソン個人が運営する段階から専門スタッフが運営業務を行うようになった。The OLLI National Resource Centerは、バーナード・オシャー財団が高等教育と芸術を財政支援する一環として設立されたもので、2011年現在、全国に117の支部がある。それぞれの支部が設立する時に、財団が財政補助し、その後は、それぞれのOLLIが独立採算制で運営している。その中で、ライフストーリーに関する活動は重要な部分を占めており、雑誌として出版されている OLLI Review は、2010年で5巻が出版されている。アトキンソンは、そのライフストーリー部門の編集責任者の一人でもある。
以上まとめると、
① このライフストーリーセンターは、ライフストーリーを聞き、書き、共有することの重要性に対する
信念に基づいて、展開されている。
② 20年前に設立されたセンターは、一つの大学の研究室から始まっただけであったが、
今は全国的展開を果たしている。生涯教育(Lifelong Learning)の一部として評価されている。
③ 普通の人のナラティヴやライフストーリーに関する興味が広がり、ライフストーリーセンターが
目指しているものを、デジタル化し保存したもの、全国レベルでの記録のアーカイヴ化、
さらに、動画という方法でのデジタル化が進んでいる。
4.ライフストーリーのアーカイヴ化の試み:「ライフストーリー文庫~きのうの私~」
(1)このホームページ創設のきっかけ
本プロジェクトは、ロバート・アトキンソンのライフストーリーセンターの試みをベースに設立されている。本プロジェクトの助成金2010年度基盤研究⒞(一般)として「ライフストーリーセンター構築によるストーリーの社会学的研究」が採用されたことで、日本版のライフストーリーセンターの設立が考案された。
研究代表者の塚田は、ロバート・アトキンソン著『私たちの中にある物語』(The Gift of Stories)を翻訳する過程で、ライフストーリーセンターの考えに共感し、アトキンソンのライフストーリーセンターを訪ね、センターのシステム構造、運営方法、特徴に関してフィールド調査を行い、ウェブ上にストーリーをアーカイヴ化する技術とノウハウを学んできた。
そして、いままでライフヒストリー研究を行っている横家純一、川又俊則の共同研究者とともに、ライフストーリー・インタビューで聞き取られたストーリーと授業で課題として書かせている「自分史的エッセイ」を、塚田の個人研究室に属するホームページにアーカイヴ化し、ストーリーを公開し、一般の人びとにストーリーを読む機会と同時に、書く機会を与える場を構築することとした。ホームページを「ライフストーリーセンター」と呼ぶと、大学全体のさまざまなセンター組織と混同されると思われたので、「ライフストーリー文庫~きのうの私~」として、2011年3月に創設された。
(2)ライフストーリー文庫~きのうの私~」の創設とその後の展開
「ライフストーリー文庫~きのうの私~」のトップのページに以下のように書き、その創設の趣旨と意味について触れている。
人は「ストーリーを語る動物」であると私たちは考えます。人はストーリー形式で考え、話をしています。
そして、ストーリーを語ることを通して人は人生に意味を与えているのではないかと考えます。
その意味でストーリーは私たちに何かを伝え、促し、教え、導いているのではないでしょうか。
ストーリーを語るということは私たちが生まれながらにもつ欲求であり、権利であるとも言えます。
私たち自身のストーリーを語ることで、私たちの声が他の人びとによって聞かれ、認められます。
私たちは、他の人びとが聞きたいと思う「私たちの声」を見つけたいと思っているのではないでしょうか。
私たち自身のストーリーを語ることによってのみ、私たちの真実が語られることができるし、
私たちの人生の「意味」が理解されるのではないでしょうか。
人は、他の人に声に出して語ることもあるだろうし、「内なる自分」対して「書く」という行為で語ることも
あるだろう。人は、ストーリーを語り、自らをより理解し、また、他人に理解され共感される喜びを得る
ことができる。自らのストーリーを語ることは自分自身への「贈り物」であると同時に、他の人びとへの
「贈り物」になると私たちは信じています。あなたのストーリーを語りましょう。
このような趣旨を示した上で、「ライフストーリー」の意味について触れ、読者への呼びかけをしている。
「ライフストーリー」は、人生の物語です。自分の人生を書くこと、あるいは他人の人生を読むことは、
私たちの人生を豊かなものにします。自分の人生の「生きている意味」を理解し、「人生を変える」
きっかけになるからです。私たちは、学生から一般の方々までの皆さんの様々な人生を綴った自分史
やエッセイ、インタビュー記事をホームページ上に公開し、多くの人たちと共有したいと考えています。
と同時に、社会学の研究者として、「当事者の声」を重視した研究に役立てたいと期待しています。
そして、具体的に3つの目的をもって設立された。
A: 一般の人びとの「人生の物語」の公開:創設時とその後
「ライフストーリー文庫:きのうの私」の第1の目的としていることは、さまざまな人びとの「人生の物語」を収集しデジタル化し、一般に公開することであった。そのためウェブ上にホームページを作成し、そこに本プロジェクトの共同研究者たちが行ったインタビューから構築された「他者のライフストーリー(「語られたストーリー」と呼んでいる)」と授業などを通して収集された「自己のライフストーリー」(「自分史的エッセイ」と呼んでいる)を掲載、公開し、「人生の物語」が一般の人びとに読めるようにし、それぞれの「人生の物語」から何かを感じ、学ぶ機会を提供したいと考えた。
プロジェクト開始当初の枠組みとしては、公開する物語のタイプとして、①「自分史的エッセイ」、②「語られたストーリー」、③「グループで語られたストーリー」、④「グループで書かれたストーリー」であったが、本プロジェクトを進めるなかで、③と④のデータ収集は極めて困難であったので、その分類を修正し、③を「テーマシリーズ」として、本プロジェクトの研究者が行っている特定のテーマ(就職活動に関わるものなど)として、新しい掲載分野を設置し、読者によりアピールするものとした。また、④は「研究論文」とし、本プロジェクトを通して得られた研究成果を公開することにした。
B: 自ら書いた「人生の物語」の投稿の場
第2の目的としては、この「文庫」では、さまざまな人びとが自分の「人生の物語」を書くきっかけとしての役割をはたし、「書かれたライフストーリー」を投稿する場を提供することを、創設当初は考えた。自分の「人生の物語」を自分自身のためだけに書くこともあり、それはそれで本人にとっては意味あることであろう。だが、「自分史ブーム」に見られるように、自分の「人生の物語」を「後世に残したいために」書いたり、「自分のアイデンティティを求めて」書いたりする場合もあるので、それらを投稿してもらうシステムを作った。これはアトキンソンの「ライフストーリーセンター」が20年前から始めたことで、ある程度の成果を上げているという事実に基づいて行われたものであった。
しかし、実際には知人からの問い合わせが1件あった以外は、投稿はゼロであった。この結果は本プロジェクト計画当初の意図からは予想しなかったことであった。なぜ、投稿サイトがうまく機能しなかったかについて、3つの説明が考えられる。
1つの説明として、近年の個人的ブログやソーシャルネットワークの普及により、他人が作り作ったホームページへの投稿は魅力のないものと思われたのではないか。自分の個人的なエッセイは、ブログやソーシャルネットワークで自ら発信すれば、友人からのフィードバックがすぐに返ってくるが、他人の投稿サイトに投稿したからと言って、フィードバックが返ってくるわけではないので、投稿する動機が生まれなかったのではないだろうか。
2つの目の説明としては、極めて個人的なストーリーを他人の投稿サイトに投稿する気にならないのは、プライバシー保護の視点からも当然のことと言えば当然のことであった。投稿を誘うことを目的として、カルチャーセンターで行われている「文章・自分史講座」を訪ね、センターの趣旨を説明したが、そのグループからの投稿は結果的にはゼロであった。その講座で書かれ、発表されていた「エッセイ」は、「人生の物語」のように、今の自分を振り返り、人生について考えるというものではなく、日常的な出来事の断片をエッセイとして、うまく書くことが目的とされたものであり、本プロジェクトの「人生の物語」の投稿募集の趣旨には合わないものであった。本プロジェクトが期待するようなエッセイは、人生を真剣にふり返る「人生の物語」と呼ばれるものであり、そのようなものには、プライバシーの問題が生じる可能性があるので、人びとは他人のホームページに敢えて投稿することはなかったのではないか。
3つの目の説明としては、「エッセイ」の投稿を動機づけるために、「エッセイコンテスト」的な形式を取っていることもホームページ上で謳ったが、有名人が審査し、多額の賞金を懸け、本としての出版の可能性がある「北九州市自分史文学賞」のようなものと比べると、本プロジェクトには、投稿するだけの魅力はなかったのであろう。
以上、「文庫」創設の当初の目的であった「書く機会を与える」という試みは、1年後には、断念された。
C: ライフストーリー研究の交流の場
第3の目的としては、このセンターで公開された「語られたストーリー」と「書かれたストーリー」を研究対象として、ライフストーリー研究の交流の場を提供することである。人びとの多様で豊かな「人生の物語」を研究し、「語り手の視点」「書き手の視点」を重視する、新しい社会学的研究の可能性を求めてこれを「文庫」の第3の目的として、ライフストーリー研究に関する理論と方法論についてのさまざまな研究者の交流の場としたいと考えていた。
本科研のプロジェクト期間3年間で43本のストーリーを掲載し、分析できるだけの蓄積ができてきたので、本報告書においても、掲載されたストーリーを利用した社会学的研究の試みを行っている。その報告書を「文庫」に掲載し、研究の方法論、理論に関しての問題提起をするつもりである。
(3)「ライフストーリー文庫~きのうの私~」の現在と今後の可能性
人びとの多様な「人生の物語」のライフストーリー・インタビューを通して収集すると同時に、共同研究者の授業で学生に書かせている「自分史的エッセイ」を収集し、アーカイヴ化を進めているが、多様性、全体的量の点から見て、まだ不十分である。しかし、その限られた「人生の物語」は大学教育の一環として、授業で有効に使われている(「ライフヒストリー研究」での実践例は第7章で論じられている)。
現在アーカイヴ化されているすべての「人生の物語」に関しては、「検索機能」を導入し、キーワードを入力することによって、見つけることができるようになっているので、利用者が使いやすいようになっている。
今後の展開の可能性について述べておく。
まず、アトキンソンの「ライフストーリーセンター」のアーカイヴ化されたストーリーは270を越える。本研究はまだ、43のストーリーしかアーカイヴ化されていない状態であるので、今後増やす方向で展開すべきであろう。量的に拡大することでより多様なストーリーを取り入れることができるであろう。
第2として、2年目からの実験的試みとして、「テーマシリーズ」を一つの分類として設けている。この「テーマシリーズ」の分類を活用し、いま話題になっているテーマに関したストーリーを集中的にアーカイヴ化することで、「ライフストーリー文庫」の多様性と魅力を増し、一般の人びとへの公開がよりすすむのではないだろうか。
第3として、アーカイヴ化は個別に行われている研究をデータとして蓄積する試みである。質的データのアーカイヴ化の問題点は多く指摘されているが、それらの問題を解決し、アーカイヴ化を進めることで、新しい形の研究の交流が可能になるかもしれない。
第4として、現在、「ライフストーリー文庫~きのうの私~」のアクセスは平均30ほどであるので、3年間でおよそ30,000のアクセスがあったのではないかと推測される。この数値はまだ大きいとは言えないが、ストーリーの数が増え、多様化された段階で、人びとに知られることになった場合には、大きく変化するのではないかと思われる。
第5として、「語り手の視点」「書き手の視点」を重視する社会学的研究はまだ歴史は短いが、それを実践し、ウェブ上で公開し、示していくことで、研究の交流が起こる可能性がある。本報告書でも、その一つの試みとして、2つの「自分史的エッセイ」を例として、「書き手の視点」をベースにした社会学的研究の試みを行っている(第7章「女子高文化―キラキラした彼女たちの中で」、「今までお嫁さんになるために勉強してきたの?」の社会学的分析の試みなど)。そのような「書き手」「話し手」をベースにし、ストーリーそのものを独立したテキストとして提示した上で、別に、社会学的分析を試みるという、ストーリーの社会学の新しい試みを展開できるのではないか思われる。
参考文献
アトキンソン、ロバート、2013年3月のインタビュー
アトキンソン、ロバート、2006、『私たちの中にある物語』ミネルヴァ書房
フォーラム、2012、「質的調査データの公共性とアーカイヴ化」、一橋大学口頭発表
吉田かよ子、2007、『オーラルヒストリーの映像アーカイブの構築及びウェブ上での公開に係
わる諸条件の研究』平成16年度~平成18年度科学研究費補助金(基盤研究⒞)研究成
果報告書
1.はじめに
これまでわれわれは、紙媒体による編集・製本という作業により、ライフストーリーの作品を発表してきたため、こんかいの電子媒体によるウェブ公開という、まったく新しい企画の遂行においては、多くの困難に直面した。ここでは、これまでの作業をふりかえりつつ、その問題点のいくつかを紹介したい。
関係者の尽力のおかげで、表1、表2のように、3年間で、合計43点のライフストーリー作品を収集し、ウェブ公開することができた。その内訳は、「語られたストーリー」13点と、「自分史的エッセイ」30点である。
前者の「語られたストーリー」は、聞き手の要請をうけて語られたものを、主に編集者が編集したもので、そのうち8点は、男性の語り手によるものである。インタビュー調査の記録であることから、自分史的エッセイよりも、あきらかに、実現しにくい。それは、語り手との共同作業が前提となり、相手の都合(ここには、意欲や話好きかどうかということも含まれる)が絡むからである。しかし、いったんそのハードルをのりこえると、他者との相互作用の醍醐味がえられる、ということでもある。
後者の「自分史的エッセイ」は、まず筆者によって書かれ、筆者または編集者によって編集されたもので、全員、女性によるものである。これだけの作品が集まったのは、ひとえに、授業での課題としたからにほかならない。ウェブページでの公開だからといって、ひろく一般からの投稿をつのることは、容易ではない。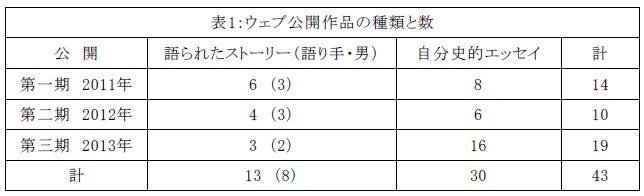
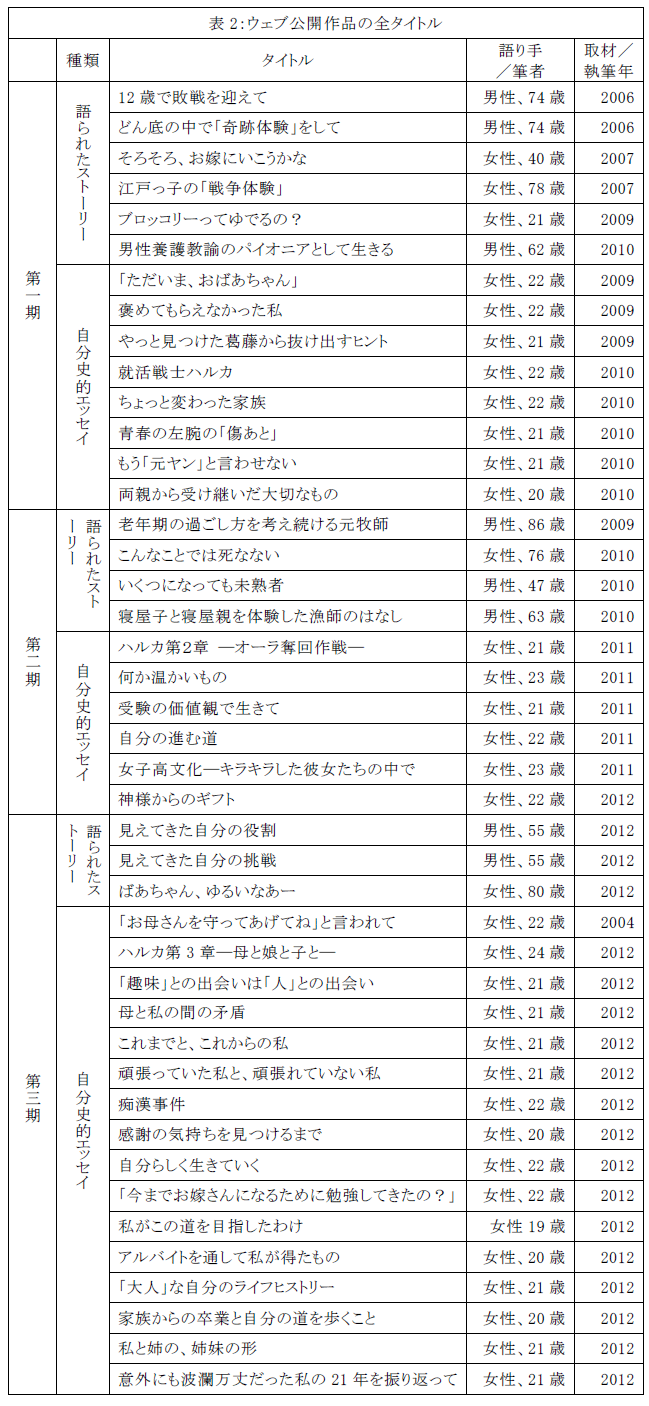
1. ウェブページの構成
電子ファイルとして提出された原稿は、数回以上の校正――なかには、幸運にも筆者や語り手自身による校正が可能だったものもある――を経て、作品となる。こんかいは、読みやすいタテ書きのPDFファイルと、ケータイなどの端末ユーザーのためのHTMLファイルの二種類を用意した。ただ、この“サービス”が奏功したのかについての確認はしていない。
構成で工夫したことといえば、第一画面で、各ストーリーのテーマを象徴する「タイトル」、および、読者をひきつけるための「リード」(表3)を配し、読者がすばやく目的の作品にたどり着けるようにしたことである。また、それぞれの作品の冒頭には、「あらまし」(表4)をおき、作品内容の、いわば〈予告編〉を提供することで、読みこみの動機づけを行った。
さらに、長い作品を2回のシリーズ物にし、読みやすさとウェブの動きを追求するといった工夫もしてみた。たとえば、第一期の「12歳で敗戦を迎えて」と「どん底の中で「奇跡体験」をして」は、一つの「語られたストーリー」を二つに分けたものであり、「就活戦士ハルカ」(第一期)と「ハルカ第2章―オーラ奪回作戦―」(第二期)は、一つの「自分史的エッセイ」を二つに分けたものである。いずれも、結果的にどうだったかという検証はできていない。
いまふり返ってみると、「リード」はともかく、「あらまし」の作成は、本文の校正作業と重なり、時間的にどちらを優先するかという問題をかかえることになった。その結果、第三期では、「あらまし」をつけないものが多くなったが、これも、やむをえない選択だった。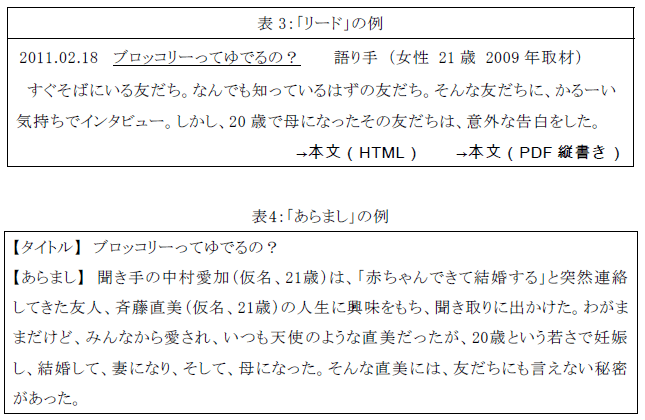
こまかいことだが、英数字の処理は、容易ではない。たとえば本稿のように、ファイルすべてがヨコ書きであれば半角のままでもいいが、タテ書きの場合は読みにくい。タテ書きのみの場合を考えたとしても、漢数字にするのか全角のアラビア数字にするのかといった判断は、いまだに、決着がついていない。
ここで技術的な問題として一つ報告しておきたいことは、こんかいのように、一つの原稿をPDFとHTMLの二種類のファイルとして共有したとき、変換のさい、バグが発生する危険があるということである。たとえば、ルビつきのワード文書をHTMLファイルに変換すると、いうまでもなく、ウェブ上の文章は、ぐちゃぐちゃになる。これを避けるためにわれわれは、やや見ばえは落ちるが、○○(△△)といった形で、○○の漢字のあとに、△△のルビをカッコつきで表現した。
漢字変換については、たとえば、「出来る」は「できる」に、「事」は「こと」にすることで、読みやすさを追求したが、「時」「頃」「今」「行く」「来る」「言う」「見る」などの場合は、一貫性の追求はあきらめざるをえなかった。あるときは漢字で、またあるときは、ひらがなとなった。かといって、それがデタラメかというとそうでもなく、漢字が続くときは、ひらがなに変えるといった、作品の読みやすさを追究した結果といいたい。
2.プロの編集
ホームページの運営一般にいえることだが、より多くの読者を獲得するためには、ウェブ・ページが「動いている」ことを印象づける必要がある。そのためにわれわれには、精力的な編集が求められたにもかかわらず、年一回のウェブ公開、つまり「アップ」が限界であったことである。とはいえ、第一期は、プロの編集者の力を借り、文章表現を洗練させ、作品の完成度を高める工夫をしてみた。たとえば、第一期作品の校正例を一つ紹介しよう。
プロの編集者が手を入れたところを、ゴシック体にしてみた。ここでは、3点のみ指摘しよう。まず、タイトルを「『元ヤン』の私」から、「もう『元ヤン』と言わせない」と変えたこと。「元ヤン」という強烈な言葉を生かしつつ、名詞で終わっている弱点を克服する仕掛けを用意している。静態的な前者にたいして、後者は、読者に向かって叫び、訴えている動態的な感じがする。あきらかに、その効果は、絶大である。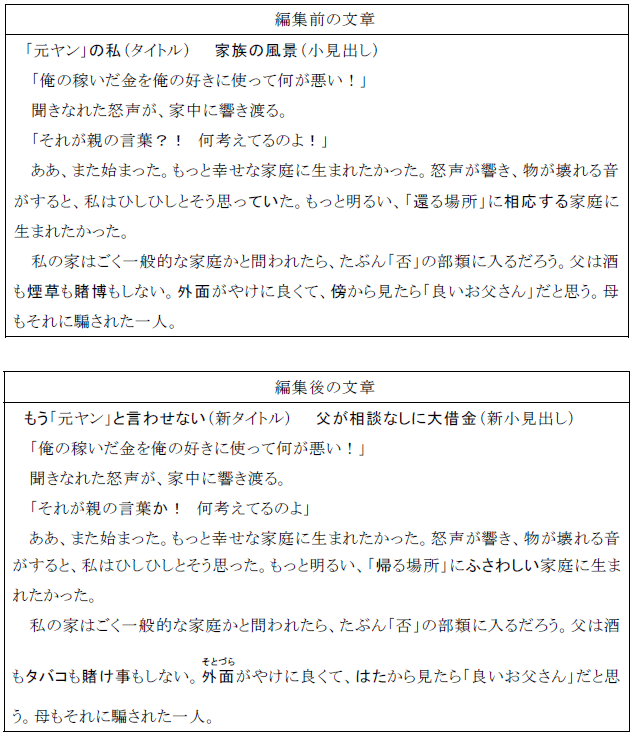
つぎに、「家族の風景」を「父が相談なしに大借金」という小見出しに変えたのはなぜか。あきらかに、前者が、どこにでもある一般的な事象の説明となっているのにたいして、後者は、これから始まるストーリーの前説(まえせつ)――読者を話の内容に惹きこむ仕掛け――として、きわめてインパクトのあるものになっている。さすが、プロの目のつけどころ、と言ってしまえばそれまでだが、おそらく、そのような選択ができたのは、「『元ヤン』の私」という文章を何回も、何回も読みこんで、その筆者の叫び声をきき、それに共振することができているからにほかならない。
もう一つは、煙草を「タバコ」とし、外面に「そとづら」とルビをふっている点である。いきなり、タバコとくれば、漢字の読みにわずらわされることはないし、ともすると「ガイメン」という、意味をなさない音が出てきそうな漢字にたいして、ソトヅラと援護することで、文意をよりはやく正確に伝えることに成功している。そればかりか、そのような表音のカタカナ語は、読者に、筆者が自分のストーリーを創作するために、頭の中で発話したときの〈息遣い〉までを運んでいる。
3.編集の理念
自分史的エッセイにせよ、語られたストーリーにせよ、ストーリーである以上、曖昧な部分は残る。その多義性をそのまま残せば、読者に敬遠されたり誤解されたりするおそれがある。それを避けるために、あえて、編集者の判断で、できるだけ一義的に洗練させることにした。
そんなことはできるはずはないとか、そんなことはしてはいけない――というヴァレリー・ヤウ⑴のような反論も聞こえてきそうだが、ここには、せめてなんとか、こんな生き方をしている人がいる、ということを知ってもらいたいという〈祈り〉がある。それが、「越権行為」であるかという議論は、別の機会にゆずりたい。
ただし、自分史的エッセイは、書かれたものであり、編集者といえども、安易に修正することは許されない。どうしても、書き手にさし返すことができないものは、たとえ、文章表現が乱れていても、慎重に取り扱った⑵。このことは、自分史的エッセイを、いったん、語られたストーリーと同じ水準で、つまり、文章の一義性を重んじた――これをかりに、「第一水準」とする――校正をしていくうちに、「なにか違う」という感じたことからヒントをえた。そのため、さいど原文にさし戻し、こんどはややゆるい、いわば「第二水準」で校正することで、結果的に、エッセイ表現のもつ、〈ゆれ〉を包摂する独自の世界に光をあてることになった。つまりそれは、相手がいる前で語られたものは、もはや、取り消しや訂正はできないが、書くために自分の頭の中で反すうしているうちは、何度でも修正がきくという、自由な世界なのだ。
その過程で一つのおもしろい発見があった。ある6600字ほどの作品に、「わたし」という表現が頻繁に出てくるので、数えてみたところ、なんと72回もの「わたし」が使われていたのである。このこと自体は、別の視点から考察することができるはずだ。ここでは、「私」という漢字で統一することで、語り手にとって特別に大切な自分というものを強調してみた。もちろん、「わたし」というひらがな書きの方が、自分の強調になる、と考えることもできようが。
注
(1)ライフストーリー・インタビューの記録を、歴史的な情報とみなすヴァレリー・ヤウは、トランスクリプトの作成について、「意味があると思われるものはすべてそのままにする」(『オーラルヒストリーの理論と実践』、インターブックス、2011:385)と主張している。
(2)とりわけ、第三期の編集では、それまでと比べて、たとえ平凡なタイトルであっても、筆者のあつい思いがこもっているものには、あまり手を加えない方針をとった。その結果、書かれている内容の核となる部分を象徴しない、ややもの足りないタイトルになっているケースもある。学期途中であれば、この点について、筆者との対話や相談も可能なのだが。
はじめに
社会調査士制度が2004年にスタートして、全国の大学・大学院で社会調査士・専門社会調査士が養成されるようになった。その前後の時期から、実に多くの社会調査テキスト、社会調査関連書籍が刊行されている。
この資格を取得するためには、資格制度に参加している大学でA~G(表1参照。このうちEとFはどちらかを選択)の科目を単位履修する必要がある。これを見ると、「調査票(質問紙、以下略)調査」が大きな柱になっている。したがって、それらテキスト等で「調査票調査」に関する説明中心に構成されているのも当然である。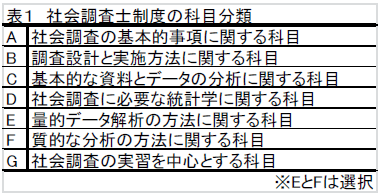 選択科目の一つFは、「質的な分析の方法に関する科目」であり、ライフストーリー・アプローチはこのカテゴリーに含まれる。
選択科目の一つFは、「質的な分析の方法に関する科目」であり、ライフストーリー・アプローチはこのカテゴリーに含まれる。
本章1節では、社会調査テキストにおいて「ライフストーリー」がどのように扱われているかを確認する。2節では、日本オーラル・ヒストリー学会(JOHA)、ライフストーリー研究会(LS研)、生活史研究会という3団体(学会・研究会)で、インタビュー調査がどのような対象・題目等で報告されたのかを検討する。3節では、有末賢・桜井厚というこの分野で代表的研究者と言える二人の近著に触れつつ、ライフストーリー研究の現在地を確認する。これらの作業を通じて、本章の課題「ライフストーリー研究の概観」に応えたい。
筆者は2002年刊行の拙著『ライフヒストリー研究の基礎』巻末で、関連文献を多数紹介したことがある(同時に、関連文献を2006年頃まで独自サイトで紹介更新していた。現在は独自サイトの運営をしていない)。本章では、2002年以降の約10年間を中心に、発表された単行本・論文・学会発表・研究会発表等に言及する。引用は膨大な文献群からするとわずかにすぎないが、筆者なりに、代表的な著作等を中心に紹介している。
2002年は、(倉石 2003)(蘭 2009)(石川 2012)らが異口同音に述べているように、ライフストーリー研究という方法論を明示した桜井厚の『インタビューの社会学』の刊行年である。すなわち、それまでのライフヒストリー研究(あるいは生活史研究)から、ライフストーリー研究へと多くの研究者が続くことになった転換点たる年とも言えよう。そこで、この年からの動向を確認しておくことには意義があるだろう。
なお、本論に入る前に、本章(および5章)における、ライフヒストリー(LH)とライフストーリー(LS)について述べておきたい。
5章で紹介する大久保孝治は、自らのライフストーリー・テキストで次のような説明をしている(大久保 2009)(以下は、筆者による要点抽出の記述)。
① 聞き手の立場=LHは黒子で、LSは共同制作者。
② LHはこれまでの人生全体が対象、LSはエピソード。
③ LHは歴史、過去の回想、LSは未来を展望したものを含む。
④ LSは自己論(アイデンティティ論)と密接に関連。
⑤ LHは個人の語り、LSはそれにとどまらず文化(制度)としての語りを含む。
その上で、大久保は「個人の『語り』としてのライフストーリー」と「文化(制度)としてのライフストーリー」を詳述する。『ワンダフルライフ』(1999年、是枝裕和監督)という映画における死者を演ずる素人(実体験を話す)とプロの役者(役のセリフを話す)の語りを例に、「語り」がバージョン・アップされること、共同制作されること、「語り」が人生の意味付与となっていること、社会(商品広告、映画、スポーツの試合など)全体で「よい語り」が学習されることなどが指摘された。
大久保は、「『語り』とは過去の経験そのものの再現ではなく、また、未来の経験の予言でもなく、現在という時点からの過去および未来への意味付与」だと指摘している(大久保 2009,pp.10-11)。
さて、ライフストーリー論の提唱者たる桜井厚は、ライフヒストリーとは「概念としてはっきりと違いがある」と述べ、ライフヒストリーは「描かれる人生が主に時系列的に編成され」、「オーラル資料のほかに、自伝、日記、手紙などの個人的記録を主要な資料源として利用」している点で、ライフストーリーと異なるという(桜井 2012,pp.9-10)。「ライフストーリー」論文集の編者山田富秋は、その意義を、「個人によって語られた物語が、その人自身に帰属するというよりはむしろ、それが語られた相互行為の文脈に依存すると考える」ことであり、それゆえにライフヒストリーではなくライフストーリーを用いると述べている(山田 2005,p.3)。同時に、「インタビュアーと回答者が共同で社会的現実を構築するひとつの方法」がライフストーリーだと述べる(山田 前掲)。このインタビューに関する認識は、語り手は「回答の容器」ではなく、聞き手と語り手の「協同作業」がインタビューであるとの指摘に準拠するものだろう(ホルスタイン・グブリアム 2004(1995))。この「アクティヴ・インタビュー」の主張は、訳書刊行後、広く浸透したように思われる。ライフヒストリー研究においても、同様の認識をもって研究を進めている人びとは少なくない (1)。
桜井自身、「ライフストーリーは、個人のライフ(人生、生涯、生活、生き方)についての口述の物語である」、あるいは「自伝や自分史など、個人が自らの生活史をふりかえって文字化されたものを含めてライフストーリーと総称される」とも述べている(桜井 2002)。さらに、「ライフストーリーやライフヒストリーだけでなく、生活史、個人史、自分史、生活誌や個人誌、語り、人生の物語、オーラルヒストリーや口述史、証言、身の上話、自伝や伝記、生活記録、ふだん記など」「を包括して、人びとのライフを描きだしたもの、人びとのライフを手がかりに生活世界をとらえようとしたもの」という、小林多寿子が『ライフストーリー・ガイドブック』の「はじめに」で示した広義の「ライフストーリー」もある(小林 2010,p.ⅸ)。本章(および5章)では、この広い意味での「ライフストーリー」という定義で同用語を用いることとする。
本章は、以下、インタビュー調査を中心に、ライフストーリーの現代的課題(のなかで筆者がとくに関心をもつ部分)について言及する。
1.社会調査テキストからみるライフストーリー
筆者は、いずれも10年たたずに新版が刊行された(森岡 2007(1998))、(大谷他2005(1999))を、1990年代の代表的社会調査テキストだと見なしている(川又 2013)。調査票調査を独習できるくらい丁寧に記述されたそれら2冊は、調査票調査以外、例えば後者は写真観察法にも言及するなど、社会調査を広義に見て説明している。
本節では、まず、以下の4冊(多数のテキストが刊行されているが、紙幅の制限から、同一人物編、1990年代までに刊行されたテキストの焼き直しなどは除き、ごく近年に刊行されたものを取り上げた)で、「ライフストーリー」がいかに扱われたかを確認しておきたい。刊行年順で説明することにする。
まず、(新・盛山 2008)では、「事例調査」の章のなかの「『ききとる』という実践」という節で、「ライフストーリー」が取り上げられている。好井裕明が担当するその章では、「実証主義的」「解釈的客観主義」「対話型構築主義」との分類が提示され、「相互行為のせめぎあいから個人の経験を取り出す」「人びとの語りから経験や文化をまとめていく」「『ききとる』営みと世代の差という問題」「相手の〈声〉と出会い、自らのカテゴリー化をつくりかえる」ということでこの研究の特徴や意義が丁寧に説明されている。事例として(蘭 2004)(石川 2007)(桜井 2005)が紹介されている。
社会調査テキストの範疇からすると少しずれるが、2004年に刊行された本の翻訳(ペイン・ペイン 2008)は、社会調査関連のキーワードに関して、できるだけ簡潔な説明がなされ、だが、そのことによって社会調査が浮き彫りになるような構成となっており興味深い。その「社会調査法の授業と調査でもっとも頻繁に登場する50個の鍵概念」のなかには、「自伝/伝記法とライフ・ヒストリー(Auto/biography and Life Histories)」が収録されている。トーマスとズナニエツキ、オスカー・ルイスらの古典的名作の紹介や、デンジン、プラマーら1980年代のテキストの引用、「諸個人の人生に関する個人的解釈をライフ・ストーリーと呼ぶ」というミラーの説明も紹介されている。
次に、「ライフヒストリーに代わってライフストーリーという呼び方もひろがっている」として、両者を同一ととらえたテキストがある(轟・杉野 2010,p.21)。同書は、「語られたことだけではなく語るという行為自体についても強い関心を寄せている」と説明され、その例として、中野の『口述の生活史』と桜井の『境界文化のライフストーリー』が挙げられているが、それ以外の解説等はない。
続いて、「質的調査の理論と実践」として、インタビューに関する説明とグランデッド・セオリーの説明を中心に記述する中で、インタビューの箇所で「ある人の人生全般(ライフストーリー)を聞くこともある」という説明をしているテキストがある(加藤他 2010,p.148)、同書では、分析方法の説明で、逐語分析・内容分析・モノグラフ分析などと並んで、「生活史などを聞きとり解析するライフヒストリー分析」(加藤他 2010,p.157)との記述がある。だが、その語彙の差や具体的な方法などには言及されていない。
このように近年刊行された社会調査テキストにおいて、「質的調査」の代表的な方法の一つとして、ライフスヒストリー、もしくは、ライフストーリーが紹介されている。桜井が近著で、「最近ではかなり認知されるようになってきた」述べたように(桜井 2012,p.170)、この方法が社会調査・社会学のなかで、一定程度の市民権を得たと言えよう。だが、いま確認したとおり、筆者の観点からすれば、社会調査のテキストであったにもかかわらず、粗い紹介が見られた。
1996年に初版が刊行されたライフヒストリーのテキストが、近年、新版として出された(谷 2008)。前版で「ライフヒストリーの教科書は、わが国では翻訳書のほかにはまだ類書がない」と記されていたが、その後10数年を経て「優れた教科書がたくさん世に出て」おり、「価値が認められ、教育現場で重視されている証左としてよい」と、編者の谷自身が記述している(谷 2008,p.ⅴ)。幾つかの章は全面的に、他の章も一定程度の書き換えられ、文献紹介でも新しい作品が収録され、新版にふさわしい内容になっている。
さらに、「質的社会調査」をうたったテキスト本(「技法編」「プロセス編」)が2冊刊行されている。いずれも「ライフヒストリー」について記述されており、そのアプローチ実践について詳しく記されている。
「技法編」全15章のうち、「ライフヒストリー分析」という章が1章もうけられ、「ライフヒストリーが作品になるまで」「分析を終えてインタビューの過程をふりかえる」「どのようなテーマがライフヒストリー分析に向くのか」などを、在日朝鮮人を対象に調査し、論文化した野入直美が説明している。また、別の章では川端亮が、インタビュー・データをライフヒストリーに変換するにあたって、コンピュータ・コーディングを利用するという方法を提案し、自らの実践を踏まえて説明している(「質的データのコンピュータ・コーディング」)。
「プロセス編」全15章のうち、「インタビュー記録を利用する」という章で、「ライフヒストリーのトランスクリプション」の説明や、エクセルを使った処理についての説明がなされている。また、「技法編」の要約をしながらの総論的章「質的社会調査法の方法と意義」では、谷が先の編著を参照しながら平易にライフヒストリーについて、他の方法と並列させる形でまとめている。
なお、「宗教社会学」のテキスト本でも「ライフコースとライフヒストリー」という項目が取り上げられ、筆者が執筆担当した(川又 2007)。
このように少なくとも社会学および社会調査の分野において、ライフストーリー・ライフヒストリーという方法・実践は、『ライフヒストリーの社会学』以降、一定程度、認知されてきていることが分かるだろう。また、『インタビューの社会学』以降、ライフストーリーへの賛同者による研究がより多く見られることは、次節、学会・研究会の動向で確認していこう。
2.3つの学会・研究会からみるライフストーリー
(1)日本オーラル・ヒストリー学会(JOHA)
2003年に歴史学や社会学、文化人類学などでオーラル資料を扱った研究者や聞き取り調査を行っていた各地の人びとが、学際的な学会を立ち上げた。これが日本オーラル・ヒストリー学会である。2013年の大会で同学会は、創立10周年の記念大会を催し、同年刊行される予定の学会誌『日本オーラル・ヒストリー研究』第9号では、10年間の歩みがふり返る特集も計画されている。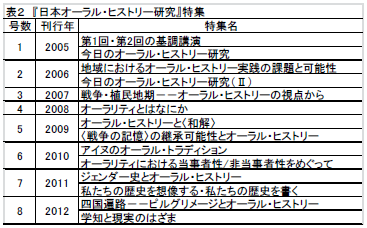 本節では、インタビュー調査という視点で、同学会の歴史をつづりたい。
本節では、インタビュー調査という視点で、同学会の歴史をつづりたい。
第1回設立大会は2003年9月に開催された。記念講演では音声・映像をウェブ上に公開するアメリカの動向が紹介されていた。英国・米国の関連学会とのつながりも示された。
同会の大会では「実践講座」が実施されている。同学会が発行しているニューズレターの第4号から引用してみよう (2)。
この講座では、オーラル・ヒストリーの基本的概念、プロジェクトの立て方、インタビューの技法、書き起こしの仕方、インタビューの解釈、成果の発表方法などについての講義を聞きながら、自らインタビューを体験してみます。当日は聞き取りの歴史や具体的な方法、留意点についての講義を受けられるだけでなく、ライフヒストリー研究やオーラル・ヒストリー研究を先駆的に行ってこられた講師の方々と膝を交えて意見交換をすることができる絶好の機会です。
同学会では、この会以外でも、実践講座としてインタビュー実践に関する、ワークショップをたびたび開催してきた。たとえば、2010年度は年間を通じて「私たちの歴史を創造する・私たちの歴史を書く」というワークショップを開催してきた。その趣旨説明の冒頭部分では、「オーラル・ヒストリーを『録音インタビューに基づく具体的な語りを基に考察する手法』と狭義の意味でとらえ、参加者が自ら小プロジェクトを実践しながら、オーラル・ヒストリーの手法をディスカッションしていこう、という試みを行ってきた」と記されている。インタビューの実践を常に意識した学会と言えよう。
学会誌『日本オーラル・ヒストリー研究』は、学会設立後2年目から刊行されるようになった。表2は創刊号から8号(2012年)までの特集をまとめたものである。学会誌特集は刊行年の前年に開催された学会大会のシンポジウムやワークショップ等に関して、論文化していることが多い。したがって、その特集を見ることで、学会全体の関心が示せるとも言えよう。ここで示されているのは、学会の関心事ということになる。「実践」「歴史」「戦争」「当事者」などが浮上していることがわかるだろう。
また、同学会初代会長吉田かよ子が監訳した『オーラルヒストリーの理論と実践』(ヴァレリー・R・ヤウ著)も、訳者として同学会会員が参加し、歴史学・社会学などの分野を超えて、学際的な交流をより一層深める契機ともなった。
(2)ライフストーリー研究会(LS研)
桜井厚が設立したこの会は、設立当時より、若手研究者・大学院生たちが積極的に自らの研究を発表する場として活発な例会活動を続けている (3)。
近年では書評会的な研究会が見られる。この数年間は日本社会学会でのテーマセッション(2011年第84回大会「ライフストーリー研究の可能性」(司会橋本みゆき))も、この研究会の中心的メンバーが立ち上げるなど積極的な議論喚起の場を提供している。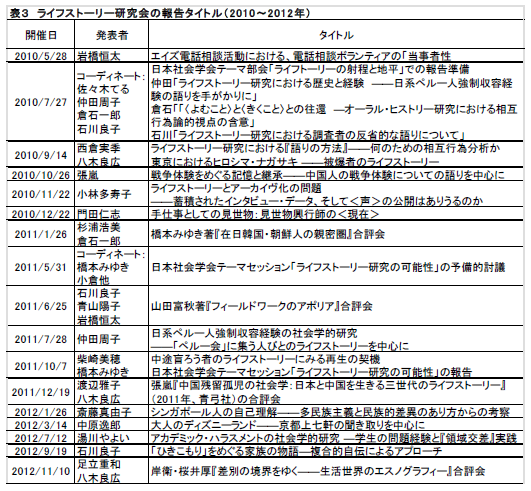 また、桜井が管理しているウェブサイト「日本の経験を語る――ライフストーリー・アーカイブズ」(http://lifestoryinterview.net/wordpress/)では、同研究会に関する記事も掲示されている。表3は、2010~12年の研究会をまとめたものである。それ以前から、同研究会は活動を続けており、これは網羅的なものではない。だが、それでも多様な研究対象が見て取れるだろう。
また、桜井が管理しているウェブサイト「日本の経験を語る――ライフストーリー・アーカイブズ」(http://lifestoryinterview.net/wordpress/)では、同研究会に関する記事も掲示されている。表3は、2010~12年の研究会をまとめたものである。それ以前から、同研究会は活動を続けており、これは網羅的なものではない。だが、それでも多様な研究対象が見て取れるだろう。
(3)生活史研究会
「生活史」に関心をもつ、中野卓と次世代の研究者たちによって立ち上げられた生活史研究会は、1981年11月に第1回例会が開催され、これまで30数年間に亘って、年3~4回の
例会を続けてきた(2013年3月現在114回+特別例会等6回)。
その中心的メンバーが執筆した『ライフヒストリーの社会学』(1995年、弘文堂)刊行と事務局の移動(1997年)は、同会の転換点とも言えよう。だが、その後も、2時間報告・2時間討論という基本的なスタイルを堅持した例会は、現在に至るまで続けられた。
100回記念例会(2006年)を機に、事務局員の高橋正樹が例会報告タイトルをもとに、テーマ等を考察している(高橋 2007)。そこで高橋は、1980年代、1990年代、2000年代と3期に分けて考察し、「方法論への意識」「変わらぬテーマ:『地域』から『福祉』まで」「テーマの変
容」ということを指摘した。高橋の論考から6年を経たが、その間、14回しか例会は開催できていない。本節では、高橋を参考にし、2003~2013年の例会タイトル29を表4に掲示し、そのなかから、特徴を読みとりたい。
複数の発表者がいる特別企画(的テーマ)を除くと、10年間で25回分の発表タイトルがある。それを、高橋の分類を参照し、テーマごとに次のように分類した。すると、職業4、書評3、移民・移動3、方法論2、福祉2、戦争2、死2、研究者2、家族2となった(その他、女性、高齢者、日記、時間、青年、宗教、運動、震災が1)。
高橋の分類では、3期(2000年代)は、方法論・職業・福祉が多かったという。最近10年でも、職業に分類される発表が多く、方法論や福祉も複数いたことが確認された。また、1期、2期と比べ、3期は宗教・時間・日記等が増えているとの指摘があったが、その後、それらは多いとは言えず、戦争・研究者等その時点でなかった対象が見られた。
また、方法論に関連して、タイトルのなかかに、生活史7、ライフヒストリー3、ライフストーリー2、聞き取り2、語り1、インタビュー1という語がそれぞれ用いられていたことも注目しておきたい。生活史が相変わらず多く用いられることと、ライフストーリーというタイトルが2つ見られたことは、2003年以降の特徴と言えるのではないだろうか。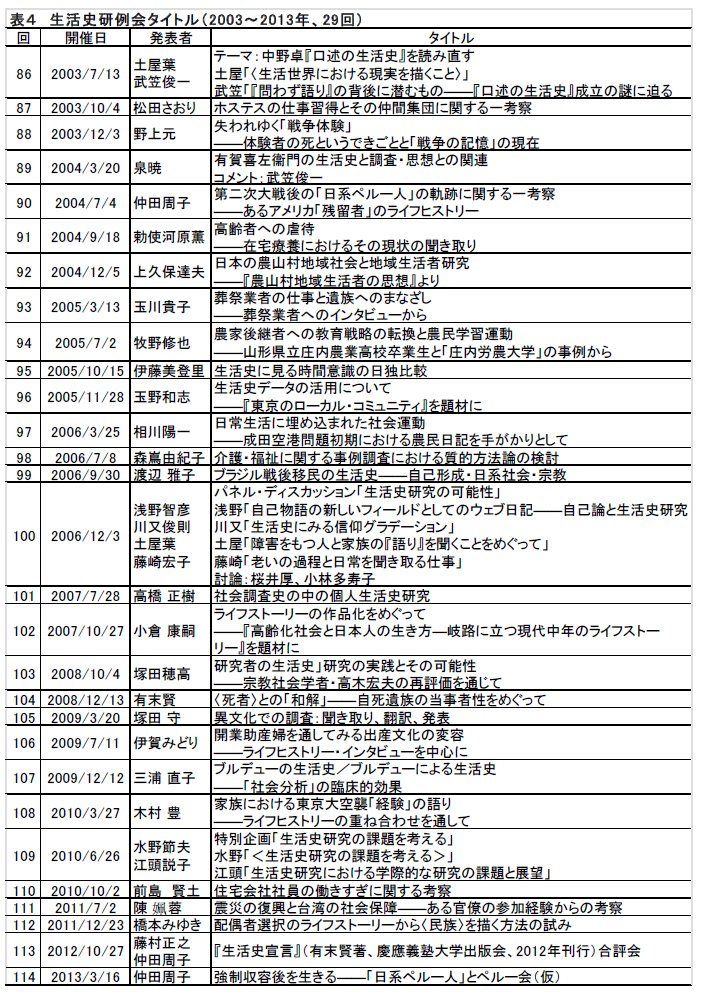 3.『生活史宣言』(有末賢)と『ライフストーリー論』(桜井厚)
3.『生活史宣言』(有末賢)と『ライフストーリー論』(桜井厚)
『ライフヒストリーの社会学』の執筆者で、JOHAでも設立当初から理事等を務めてきた、生活史・ライフストーリー分野の代表的研究者である有末賢・桜井厚が、2012年にそれぞれ単著を刊行した。今後、後続者から参照される文献となるだろう。それらの概要ではなく、筆者なりの観点から、ポイントを数点のみ取り上げたい。
(1)『生活史宣言』の問うもの
同書は、有末が2001年に博士の学位を授与された博士論文が基礎となっている。それから10数年年を経て、新たな調査や論考も含めて刊行された。序章と結章以外、三部構成からなる。第Ⅰ部「現代社会学と生活史研究」では、3章にわたって、生活史(=ライフヒストリー)の社会学的位置づけ、方法論的課題などが議論されている。第Ⅱ部「生活史の意味論」は、有末生活史論のポイントとなる議論を集めている。質的研究・意味論・記憶と時間という生活史の議論の根幹について議論されている。第Ⅲ部「生活史の応用と解釈」は、事例研究にあたる。
すでに表4で示した通り、同書は生活史研究会第113回で取り上げられている。そこで評者だった藤村正之氏、仲田周子氏は同日の発表を、後日、『生活史通信』でまとめた (4)。藤村氏は「生活」および「語りの重層性」「語り得ないこと」に着目し、仲田田氏はライフストーリー研究の立場から、事例部分と理論部分の差異を具体的な内容を含めて問題提起をした。例会では多くの参加者が活発な議論を展開した。
筆者自身は、1990年代から、有末がそれ以前から発表していた生活史研究の理論的な論考を学んできたため、本書でそれらが単行本としてまとめられたことをまず素朴に良かったと思ったが、内容として関心を強くもったのは、第6章「生活史における記憶と時間」第4節の「記憶と『語り得ぬもの』」および、結章「生と死のライフヒストリー」である。
JOHA学会大会で2008年に〈和解〉というテーマを扱ったが、ライフストーリー・インタビューをしていく側は、「語れない」「語られない」「語りえない」部分について、どのように考えていくのか、個別のケースなどをもとに報告され、また、その課題については、それぞれのフィールドの中で経験するものでもあり、インタビュー実践者として、その後も様々な機会に何度も議論されている。筆者自身は、死者に対する記念誌について若干議論したことがある(川又 2010)。3冊の記念誌を事例に、その構成の共通性を見出し、同時に、ある故人の「死後」その「死」に向き合うことで「生を思う」遺族や関係者が存在することを指摘した。記念誌の考察は、単なる一個人の歴史を知るというばかりではなく、広くライフヒストリー研究に寄与することも示した。有末は自死遺族に関する調査研究をしており、それらの調査を踏まえた結章での議論がたいへん興味深かった。
(2)『ライフストーリー論』が描くもの
『インタビューの社会学』から10年を経て、桜井は、「現代社会学ライブラリー」の1冊として『ライフストーリー論』を刊行した。
「ライフストーリーとは何か」という1章で重要な概念を説明し、次に中野卓の一連の生活史研究の業績を社会学の歴史のなかに位置付け、続いて、ライフストーリーの考え方と論点として、「自己」「時間」「共同性」「語りの構造、様式」などを論じていく。さらに、「混沌の語り」では被害者やサバイバーの方々の「語り」に関する問題点、歴史学の側からオーラリティ(口述)への注目が集まり研究が進んできたことが述べられた。最後に倫理の問題を議論してまとめている。桜井のこれまでの業績・調査事例なども数々引用され、欧米での議論も適宜紹介しており、まさに、この1冊で「ライフストーリー研究のいま」が分かるといって過言でないだろう。
その桜井は、「ライフヒストリーからライフストーリーへ」自らの方法論的スタンスを「実証主義」ではなく「対話的構築主義」であると明示した(桜井 2002,p.9)。「ライフストーリーは口述の語りそのものの記述を意味するだけではなく、調査者を調査の重要な対象であると位置づけている」点がポイントとなる(桜井 2002,p.9)。たしかに、中野は「記述に調査者を登場させたものの、それ自体を研究の対象にしたわけではなかった」点で、桜井らのライフストーリー研究とは異なるのだという(桜井 2012,p.37)。また、「語り手が『何を語ったのか』という語りの内容」ばかりではなく、その語りを生み出したさまざまなコンテクストに注意しながら「『いかに語られたか』も吟味する立場」が、桜井らの「対話的構築主義」なのである(桜井 2002,p.28)。
生活史研究会では同書を例会にて書評会として取り上げた。そのときの評者の一人足立重和は書評論文を発表した(足立 2003)。同会は、桜井にリプライを要請し、それが同会通信に掲載された(桜井 2004)。
そのリプライで桜井は、改めて、「調査対象者の『主体性』概念も、なお聞き手/書き手である調査者との共同によって産出されたものであり、それをいかにも調査対象者の『主体性』であるかのようにとらえていないか、そうした偽装を含めて、調査者/著者は自覚的であるべきと指摘した」と述べている(桜井 2004,p.4)。「自らのライフヒストリー研究の実践的な経験を構築主義的な観点に依拠しつつ反省的にとらえ返したもの」が、それまでの「実証主義」に対して、「対話的構築主義」と名付けたのであった(桜井 2004,p.3)。
それ以外にも多くの論者から(桜井 2002)は評価を受け、また、桜井自身のその後の調査研究を踏まえたものが(桜井 2012)なのである。
(3) 生活・ライフ・生活史・ライフストーリー
一見、全く違う方向性をもつように見える有末と桜井だが、上記の両書を見る限りにおいて、両者の共通点として、「生活」(桜井の場合は「ライフ」も同様)という語へのこだわりがあることは指摘しておきたい。
有末はそれこそ1章を割いて「生活」を論じている(第Ⅰ部第2章「生活研究とライフヒストリー」)。そこでは「生活把握の類型」として「生活組織論」「生活システム論」「生活意識論」「生活構造論」を位置づけるなど、生活研究とライフヒストリーの位置関係を検討した(有末 2012)。
桜井は1970年代から「生活」概念が日本で注目され、「生活学会」の設立(1972年)、生産者ではなく「生活者」が注目された1980年代末から1990年代などを、オーラルヒストリーの考え方に通じるものとして歴史的な変遷を示した(桜井 2012)。
この「生活」への強い関心が、この分野で、それぞれのテーマでの豊穣な成果を上げたのだと言えよう。
おわりに
生活史・ライフヒストリー・ライフストーリーを、主要な方法論あるいはテーマとしている論文・報告書・単行本は、近年数多くみられる。それらを隈なく収集し、内容を読み込み、分類するという方針で本章を執筆することもできたかもしれない(が、時間的制約と結果のバランスを考え、筆者は今回その方法は採用しなかった)。
例えば、GeNii(学術コンテンツ・ポータル http://ge.nii.ac.jp/genii/jsp/index.jsp)で、「まとめて検索」を「ライフストーリー」で行ったところ、「CiNii(論文情報ナビゲーター)」で404件、「Webcat Plus(連想×書棚で広がる本の世界)」で226件、「KAKEN(科学研究費助成事業データベース)」で190件、「NII-DBR(学術研究データベース・リポジトリ)」で82件、「JAIRO(学術機関リポジトリポータル)」で79件が検索された(2013年2月26日実施)。
同様に、「ライフヒストリー」では、「664件、283件、506件、202件、115件」、「生活史」では「4589件、2975件、1562件、4200件、517件」が検索された。さらに、これら3単語の同時検索では、「3件、1件、9件、0件、0件」となった。
これ以上の分析はしていないが、件数からも「ライフストーリー」は他の二つと比べて新しく使われていることや、すでに「ライフヒストリー」にすべてのコンテンツで肉薄していることが分かる。今後、これらの対象文献を整理し、分類することで何らかの特徴を見出すという検討は後日に期したい。
筆者は本章で、テキストと関連する学会・研究会の報告などを見ることによって、この分野の研究を概観した。そして、生活史・ライフヒストリー・ライフストリーに関する重要(だと筆者が思っている)具体的な単行本・論文等を幾つか取り上げた。
日本社会学会の学会誌『社会学評論』60巻1号(2009年)では、「『見る』ことと『聞く』ことと『調べる』こと」という特集が組まれ、視聴覚に関する理論化や技法に関する7本の論文が掲載された。本稿に直接関連するものとして(小林 2009)(古賀 2009)がある。「声」、「音」、また先に有末や桜井の著書で触れた「沈黙」など、個々に議論すべきテーマは多い。本章で取り上げられなかった多くのライフストーリー研究者たちは、各人のテーマと同時に、このような大きな課題についても取り組んでいることを付言して本章を閉じたい。
注
(1)井腰圭介は、ライフストーリー関連の論文集を紹介するなかで、『ライフヒストリーの社会学』(1995年刊行)以後、調査方法論を巡る諸問題の議論がそれまでと異なる部分で現れ、とくに、「それを問う研究者の行為をも問い直す方向へと旋回」したことを「研究する『個人』の発見」と指摘し、それを、「1960年代に権威ある学問/学問の権威に対して発せられた『何のための学問か』という問いへの、およそ30年・一世代かけて出されたひとつの解答」とも述べている(井腰 2010,p.352)。これは、(蘭 2009)や(石川 2012)らの論点と重なる問題である。
(2)『JOHAニュースレター』4号,pp.3.
(3)筆者も同研究会のメーリングリストに設立当初より登録している。以下はそのメール情報および、桜井のウェブサイトによる。筆者は遠方を理由に、平日夜に立教大学で開催される同研究会には一度も参加したことがないが、そのメーリングリストでは研究会の概要を丁寧に報告されており、大いに学ばせていただいている。
(4)『生活史研究会通信』79号(2013年)にそれぞれのまとめが掲載されているので参照されたい。
文献
足立重和,2003,「生活史研究と構築主義――「ライフストーリー」と「対話的構築主義」をめぐって」『社会科学論集』(愛知教育大学地域社会システム講座),40・41,pp.219-231.
蘭由岐子,2004,『「病の経験」を聞き取る――ハンセン病者のライフヒストリー』,皓星社。
蘭由岐子,2009,「いま、あらためて“声”と向きあう」『社会と調査』,3,pp.38-44.
有末賢,2012,『生活史宣言――ライフヒストリーの社会学』,慶応義塾大学出版会。
新睦人・盛山和夫編,2008,『社会調査ゼミナール』,有斐閣。
(好井裕明,「事例調査の基本をめぐって」,pp.273-309)
J・ホルスタイン、J・グブリアム著,山田富秋他訳,2004『アクティヴ・インタビュー――相互行為としての社会調査』,せりか書房。
石川良子,2007,『ひきこもりの〈ゴール〉――就労でもなく「対人関係」でもなく』,青弓社。
石川良子,2012,「ライフストーリー研究における調査者の経験の自己言及的記述の意義――インタビューの対話性に着目して」『年報社会学論集』,25,pp.1-12.
加藤千恵子他,2010,『失敗しない社会調査法のすべて』,インデックス出版。
(田中暢子・渋谷英雄,「質的調査の理論と実践」,pp.139-172.)
川又俊則,2007,「ライフコースとライフヒストリー」櫻井義秀・三木英編,『よくわかる宗教社会学』,ミネルヴァ書房,pp.48-49.
川又俊則,2010,「死後に生を思う――記念誌をめぐる一考察」竹内清己編『死の物語研究――文学、哲学、ライフヒストリー、ナラティヴ・アプローチ』(平成19~21年度東洋大学東洋学研究所プロジェクト研究報告書),pp.185-198.
川又俊則,2013,『数字にだまされない生活統計』,北樹出版。
小林多寿子,2009,「声を聴くこととオーラリティの社会学的可能性」『社会学評論』60(1),pp.73-88.
小林多寿子編,2010,『ライフストーリー・ガイドブック――ひとがひとに会うために』,嵯峨野書院。(井腰圭介,「ライフストーリー研究の集積――論文集」,pp.350-353)
古賀正義,2009,「録音素材から調べ構築するリアリティの重層性――インタビューのエスノグラフィーを実践する」『社会学評論』60(1),pp.90-108.
倉石一郎,2003,「書評『インタビューの社会学』」『ソシオロジ』,48(1),pp.146-150.
森岡清志編,2007,『ガイドブック社会調査 第2版』,日本評論社。
中野卓・桜井厚編,1995,『ライフヒストリーの社会学』,弘文堂。
大久保孝治,2009,『ライフストーリー分析――質的調査入門』,学文社。
大谷信介他編,2005,『社会調査へのアプローチ 第2版』,ミネルヴァ書房。
ジェフ・ペイン、ジュディ・ペイン著、髙坂健次訳代表,2008,『キーコンセプト ソーシャルリサーチ』,新曜社。
桜井厚,2002,『インタビューの社会学――ライフストーリーの聞き方』,せりか書房。
桜井厚,2004,「足立重和著『生活史研究と構築主義』論文に応えて」『生活史研究会通信』,53,pp.3-7.
桜井厚,2005,『境界文化のライフストーリー』,せりか書房。
桜井厚・小林多寿子,2005,『ライフストーリー・インタビュー――質的研究入門』,せりか書房。
桜井厚,2012,『ライフストーリー論』,弘文堂。
高橋正樹,2007,「例会報告タイトルから見る生活史研究のうつりかわり」『生活史研究会通信』,63,pp.7-10.
谷富夫編,2008,『新版ライフヒストリーを学ぶ人のために』,世界思想社。
谷富夫・芦田徹郎編,2009,『よくわかる質的社会調査 技法編』,ミネルヴァ書房。(野入直
美,「ライフヒストリー分析」,pp.90-105)(川端亮,「質的データのコンピュータ・コーディン
グ」,pp.134-147)
谷富夫・山本努編,2010,『よくわかる質的社会調査 プロセス編』,ミネルヴァ書房。(谷富夫,「質的社会調査法の方法と意義」,pp.2-19)(近藤敏夫,「インタビュー記録を利用する」,pp.172-185)
轟亮・杉野勇編,2010,『入門・社会調査法――2ステップで基礎から学ぶ』,法律文化社。(杉野勇,「社会調査の種類」,pp.17-32)
山田富秋編著,2005,『ライフストーリーの社会学』,北樹出版。
ヴァレリー・R・ヤウ,吉田かよ子監訳,2011,『オーラルヒストリーの理論と実践――人文・社会科学を学ぶすべての人のために』,インターブックス。
はじめに
第3章で包括的に川又によってレビューされたように、インタビュー調査に基づいた「ライフストーリー研究」は、研究として確立されているが、自分史を研究するということが、「ライフストーリー研究」として位置付けられることはほとんどない。「自分史学会」という名の学会はあり、自分史を研究することを目的としているが、実際に自分史を研究するというよりは、自分史作品を書くことを奨励し、自分史作品を募り、その中の優秀な作品に『私の物語・日本自分史大賞』を授与し、表彰するのが主な活動で、研究活動をしている学会とは言えないであろう。
よって、この章では、数少ない自分史研究とみなされる研究をレビューすると同時に、どのような自分史作品が書かれてきたかを概観し、自分史的作品を書くことの評価がどのようになされているかについてまとめる。
1.自分史を書く目的
1980年代から社会現象となっている自分史ブーム、つまり自分史がどのように生まれ、どのように展開されたかについては、すでにさまざまな形で議論されている(浅野2002年、色川 2000年、小林 1997年、吉澤 1995年)。本章では、自分史を書く動機に言及しながら、自分史を書くことがどのような機能をもつかについて論じていく。さまざまな自分史研究の中でも、小林が書いた『物語られる「人生」-自分史を書くということ』(1997年)は、自分史を書く動機をもっとも簡潔に書いているので、この研究に言及したい。小林は、自分史を書いた人びとのインタビューを行って、その書いた動機について研究を行っている。
一つは、自分が経験したことを「記録として後世に残したい」と思って書く、「歴史の記録」を主たる目的とする。このような目的で書く人びとは、比較的年配で、仕事を退職し現役から退いてから、人生をふり返って書く場合が多い。日本史全体にかかわるのではなく、自分の生きた証しを、子供や孫の世代に伝えたいと思って書き残すものである。具体的には、戦争体験、苦労体験、社会的成功体験など、歴史との関わりで、どうしても残しておきたいと思うことを中心に書いている自分史である。あるいは、家族の歴史、郷土の歴史と関連することを記述しながら、「記録に残す」ことを目的としている。
二つ目は、若者層に多いもので、「自分が何者であるか」を問いながら、自分のアイデンティティを確立するために、生きてきた経験をふり返り、「自分探し」あるいは、「自己理解」を目的とするものである。その記述の中には、それぞれが生きた社会や歴史との関連が書かれることはあまりない。むしろ、比較的短い人生体験の中で、自分にとって「意味ある経験」について書き、「整理」し、今の自分がどのように形成されてきたかについて綴っているものである。
以上の2つの異なった自分史作品で、小林が言っている「歴史の記録」としてもっとも有名なものが、色川大吉の『ある昭和史―自分史の試み』で、太平洋戦争がどのように起こったかを、その時代に生きた自分史を書くことによって、正統な歴史解釈に対して一つの批判を示したものである。また、同じ著者による最近出版された昭和自分史を綴った『廃墟に立つ』『カチューシャの青春』などもまた、歴史学者が、自分史をとして、一般的な歴史的解釈とは異なる「歴史の記録」を書き残したものである。また、社会学者中野卓の『「学徒出陣」前後―ある従軍学生のみた戦争』も、10歳代の著者が見た戦争体験として、従軍慰安婦、国共内戦に乗じた武装残留の陰謀等について書いたものであり、「歴史の記録」を書き残したものである。
研究者でない人たちが書いた「歴史の記録」を残す試みとしては、戦争体験などを綴った早乙女勝元『下町の故郷』や高木敏子『ガラスのうさぎ』なども自分史作品として知られている。特に、戦争体験という歴史的体験の語り継ぎは、自分史作品にはよくみられる。筆者は、「『戦争体験』の語り継ぎ―自分史作品の分析から」(2009年)に、戦争体験を語り継ぐという作品が自分史として書かれることが多いことに注目し、それぞれの著者が、なぜ、そのような自分史作品を書くようになったのかを分析した。ごく最近まで、少なくとも公的な場所であまり話題にされなかった「東京大空襲」を経験した早乙女勝元は、自らが経験した空襲体験を語り引き継ぐことが、戦争の犠牲者たちへの追悼になると思い、最初の自分史作品『下町の故郷』を書き、その後は、この体験を風化させないために、空襲の体験者からの聞き取りに基づいたドキュメンタリー作品『東京大空襲』を書き、「東京大空襲」を語り継ぐ運動を展開し、最終的には、「東京大空襲・戦災資料センター」を2007年に設立し、センター長になり、その記録を残すことを自分のライフワークにしていった。
さらに、戦争体験を庶民の視点から書き、それを一般の人びとに伝えることを目的として、自分史作品を書き、その作品を書いたことで戦争体験を語り、書くことで、記録に残した人たちがいる。その中で特に、有名になった作品には、鈴木政子『あの日夕焼け 母さんたちの太平洋戦争』や高木敏子『ガラスのうさぎ』がある。この二人は、ベストセラー自分史作品を書いたことで、その後も、戦争体験を語り継ぐことをライフワークとしているようである。
次に、若者の自分史作品として、「意味ある経験」について書き、「整理」するものとしては、第4回北九州市自分史文学賞作品『おーい! 新米ママポリス奮戦記』がある。島崎のこの作品は、29年間の人生全体ではなく、卒業後の1年のことが書かれているだけである。地方の県警に婦人少年補導員(ママポリス)として、2年間勤務した、そのはじめの1年だけに焦点を当て書かれたものである。島崎の書いた動機は、「整理する」だけではなく、文学賞に応募して「チャレンジしたかった」からである。文学賞に応募することで、他者の視点をとりこんで書いたものだと言える。この作品の特徴は、「出来事を自分の気持ちや解釈で説明している」点である。それは、現在の自己からみた過去の自己へのまなざしを書いたものである。若い人たちも激動の青年期を生きた自分を整理したい、残しておきたいという気持ちで自己の過去を書き綴っている。その意味では、ベストセラーになった大平光代『だから、あなたも生きぬいて』も自分史だと考えられる。
2.自分史作品の書かれ方
歴史的に見ていくと、自分史は、橋本義夫の「ふだん記」運動から生まれたと言われている。自分の日常的なできごとを書くことによって、生活を豊かにするということが目的で、あまり、文字と接することがなかった主婦たちが集まって、自分史を書いたというものであった。その歴史的な意義は、「ふつうの人びと」が自分の歴史や日常的なことを書き残すことであった。
現在では、各地の行政で行われている自分史講座で自分史は書かれている。愛知県春日井市の場合は、行政が自分史を推進し、毎年、講座を開いている。その講座を受講したものが、「自分史サークル」を設立し、そのサークルのメンバーが定期的に集まり、自分史を書く。それぞれの自分史を輪読し、サークル内で批評しながら、グループで書くという形式をとっている。
行政ではなく、自分史を出版し注目された人が、自分史を書くことの楽しさを伝えるために、カルチャー・センターで講座を開いている場合も多い。名古屋で言うと、中日ドラゴンズの選手だった平野選手の姉、内藤洋子さんは、『わが故郷は平野金物店』を書いた。内藤さんもある文章講座に参加していて、講座の講師から自分史をまとめてみないかと勧められて書いたものである。父親を小学6年生、そして、母親を高校2年生の時に亡くし、姉と弟二人だけで生きた青春物語だった。弟が中日ドラゴンズの選手だったことも話題になりNHKのテレビ・ドラマ新銀河『ようこそ青春金物店』として連続ドラマ化された。それがきっかけになり、内藤さんは有名になりエッセイを書いたり、自分史に関する講演を全国で行ったりしながら、名古屋のカルチャー・センターで長年にわたり、自分史講座を開いている。そこでも、受講生によって自分史が書かれている。
さらに、鈴木政子さんも「母さんの自分史」と評された『あの日夕焼け―母さんの太平洋戦争』という自分史を書いた経験から、自分史を書く意義を人びとに伝えたいと思い、自分史講座を開き、講師として教えた経験を記録にし、『自分史―それぞれの書き方とまとめ方』を出版している。自分にとって強烈な人生の出来事を自分史として書いたことで、自分史を書くことの意義を実感し、そのことが評価されたことで、自分史講座を開き、自分史、あるいは自分史的エッセイを書くことを勧めている。そのような講座に参加する人たちが自分史を書いている。
3.自分史の種類
自分史の種類について少し述べたい。自分史サークルが定期的に集まって、それぞれの自分史を書き、それを手作りで冊子にまとめているような場合がある。一人が書くページ数としては、4~5ページ。サークルの仲間ともに書いたものを共有するという形で、短いエッセイのような自分史を編集するという形式である。講師の平岡さんの指導の下、春日井市自分史の友の会の『わだち』は2011年月で第50号を出版するに至っている。
次に、比較的短い自分史作品を全国に公募したことがきっかけで生まれる自分史。『伝えたい私の物語』掌編自分史作品集は、春日井市民文化財団が全国の人びとに比較的短い自分史作品の投稿を募ったものである。原稿用紙7~8枚という限定で募集し、269の投稿の中から、60を審査委員が選出し、編集した。書いた分量としては、3000字程度の短いものであり、1冊の本としての自分史とは異なった形式だが、それぞれの生きた人生の物語のエッセンスが物語として書かれている。同じような形式で、全国的な規模で「戦争体験」にかかわる自分史作品を募集することも、戦後50年、60年などという節目に行われている。「戦争体験」「戦争被災者体験」などが多く募集されているのもそれにあたる。『戦後六十年 語り継ぎたいあの大戦』などはその代表的なもので、これも原稿用紙で十枚以内のものを編集した本になっている。
4.若い世代の自分史作品の特徴
本プロジェクトの「自分史的エッセイ」として書かれたものは、ほとんどが若い世代のものであるので、どのように若い世代が自分史作品を書くようになったかについて、小林の議論を整理したい。小林によれば、その動機は3つのキーワードで説明される。
第1のキーワードは、「ふり返る」あるいは、「整理する」ことであり、人生の経験を秩序づけるために自分は書かれている。ふり返ることで、過去の自己は現在の自己から立ち上がり、客体化される。文字で綴ることで、読めるものになり、可視化される。可視化することにより自分の経験を秩序づけるのである。その意味で、自分史を書くことで、それまであいまいであった自分を見つめ直し、「自己理解」を深めることができる。
第2のキーワードは、「自分探し」であり、過去の自分と向き合い、現在の自己への連続性を確かなものにするために、自己の物語をつむぎだす。自分が何者であるか、自己のアイデンティを探求するために自分史が書かれる時、それは、「自分に語って聞かせる物語」にほかならない。「自分探し」もまた、自分が何者であるかの理解を深めるという意味で、「自己理解」を深める別の側面であり、一貫した自分の物語を書くことで、現在の自分の安定性を構築しようとしたものである。
第3のキーワードは、「他者への呈示」であり、自己の物語は他者に語って聞かせるストーリーであると言える。自己のアイデンティティは他者が共有してくれることによって、はじめて成立するストーリーである。現在の自己を確かにするには、自分自身だけでなく他者の確認も不可欠なのである。だから、つむぎだされた自己の物語は、他者にも読まれなければならないのである。若い世代にとって、自分史とは、自己と他者との双方へ同時に呈示される自己の物語なのである。この「他者への呈示」という側面は、「語られる自己」あるいは「他人に理解される自己」とは何かを認識することである。そして、自分史の書き手は、他者という鏡に映った自己の軌跡を確認する。他人の視点を入れることにより、「自己変革」にいたる可能性もあると言える。
5.物語論からみた自分史的エッセイ
本プロジェクトで取り扱っている「自分史的エッセイ」を物語と見なし理解することで、自分史的エッセイを書く意味が明確になると思われる。この節では、自分史的エッセイを書くことは、「語られた自己」の記述であるという物語論から、自分的エッセイを書く意味について考えたい。
野口(2002:21-50)は、「語り」と「物語」は区別される関係にあると同時に、相互に関連する関係にもあると言う。伝記や自分史のような文字形式にされたものを含む「語り」から物語が生まれ、物語になった時、人びとへの影響は大きくなる。また、逆に、「語り」が「物語」から生まれるという場合もある。自分史を書いた人は、自分の人生をその自分史のシナリオに沿うような形で「語る」傾向がある。その意味で、「語り」は「物語」の延長上に生み出されていくのである。
では、「物語」という形式は私たちにどのような機能を果たすのであろうか。論理的に説明のつかない異常で不可解な事件でも一つの「物語」として理解された時、その事件を理解したと感じる。その意味で、「物語」という形式は現実に一つのまとまりを与え、了解可能なものにしてくれ、「物語」は現実を組織化し、混沌とした世界に意味の一貫性を与えてくれる。ただし、「物語」は以上のような「現実組織化作用」だけでなく、現実理解の方向づけをする「現実制約作用」もあるという。いったん語られた「物語」によって、それぞれの生き方が制約される可能性があるので、「物語」は何度も語り直されなければならない。
その語り直しの際に重要なことは、「物語」としての一貫性は、「現在」が「物語」の結末になるように組織化されるということで得られるという点である。野口の言葉を借りれば、
現在、自分がしていること、現在、自分がおかれている境遇、現在の自分の苦しみや悩み、
それが物語の結末とならざるを得ない。逆に言えば、この「現在」を説明する形で、「過去」が配列される。
この「現在」に関係しないような「過去」の出来事は、省略されたり、無視されたりする。そうすることで、
物語としての一貫性が保たれる。したがって、「現在」が変わるたびに、物語は書き換えられなければ
ならない。(野口2002:44-45)
やまだ(2000:28-30)もまた、「物語」形式によって自己が語られ、構築されると述べ、「物語としての自己」の4つの重要な側面に言及している。まず第1に、物語は、「相互作用」の中で語られるので、自己は個では定義されず、本質的に他者に媒介される存在、関係概念と見なされる。「自己」は個人の内面に閉ざされたものではなく、他者を媒介とし、他者に向かって語る時に、自己が生成される。第2に、自己の構成に文化や社会や歴史的文脈がかかわる。自己を時間的存在、歴史的存在としてみることは、自己が他人になる、あるいは他人が自己になる、変身の可能性を含んだ存在としてとらえることができる。第3に、物語は過去と現在の自己を結ぶだけでなく、未来の自己、可能性としての自己を有機的に意味付け組織する。第4に、「物語としての自己」という見方は、「自己の語り直し」を促し、自己を生成的に変化さる可能性をもつものである。このように、やまだによれば、「自己の物語を語ることは私的で個人的な作業でありながら、共同体の歴史を作る作業とも重なって」いくのである。
小林(2000:89-91)もまた、自己の経験を物語として語ることの意味について、3点にまとめている。第1点目は、自己を物語る主題は、「秩序づけたい経験であり、表出したい経験であり、読まれたい経験」で、「一つのプロットで描かれ、物語で秩序づけようとする経験」である。第2点目は、物語は一つでなく、主題が異なれば別のヴァージョンの物語がありうるということである。第3点目は、語ることは自己確認と他人による批准の重要性である。このように自己を物語化することによって、何かの自己変革が起こることを、また、物語ることで現在の自己を肯定する作用があり、このような物語効果はセラピーの分野でも実践され、物語ることがナラティヴ・アプローチの実践にも通ずる可能性があることを、小林は指摘している。
自己変革を伴う物語生成あるいは「語り直し」には、良き聞き手、良き読み手と出会うことが重要である。人生の書き換えの可能性について論じている榎木(2002)は、「人はだれも物語的文脈で生きており、その物語的文脈に沿って目の前の現実を解釈し、日々の行動のとり方を決定し、また、過去の自分を回想し、自分の未来を予想する…」とし、自己の物語の書き換えで、過去も変わると論じている。
だが、書き換えと言っても、過去に起こってしまった出来事を起こらなかったことにすることなど
できるはずがない。できるのは、事実として出来事のもつ意味、その出来事が自分にとってどんな意味を
もっているかについての解釈のし直しである。それは、出来事の意味を解釈する文脈として機能する
自己物語の書き換えである。(榎木2002:83)
榎木(2002:113)は、良き聞き手に出会うことによって、人は、自己開示の3つの効用を感じると論じている。
まず第1に、カタルシス効果である。自己開示というのは、自己について他者に知らせること、つまり自分の考えていることや感じていること、過去の経験や将来の展望など、自分がどんな人間であるかがわかるような情報を他者に伝えることである。カタルシス効果というのは、胸の奥深くおしこめられていたものを誰かにぶちまけることによって、気持ちがスッキリし、ストレスが軽減されることをさす。
第2に、「自己洞察効果」である。それは、自己の体験や思いをありのまま何度も繰り返し語ることによって、自己の内面に対する洞察が促進され、考えがまとまったり、気持ちの整理がついたりすることをさす。
第3は、「不安定低減効果」である。同じような体験をした者同士が自己の内面をさらけ出しあうことによって、他の人も同じような思いや悩み、症状をもっていることを知り、それによって自分の反応が正常なものであることが認識され、不安が低減することをさす。
さらに、ロバート・アトキンソン(2006年)も、自分史を書かせる、ストーリーを語ることについて、以下の10つの機能をあげている。
① 学生たちが語り、書くストーリーは、自己発見の道具でもある。
② 語り、書くことで自己変革の可能性が生まれる。自らは人間という存在以上の、
もっと神聖な存在であることに気づく。
③ ライフストーリーを語ることは、人生に意味を与え、意味づけを必要とする過去の出来事を癒し、
自己をそのまま受けとるもっとも重要な方法である。
④ 今まで曖昧だった自分自身の体験と感情が明確になり、そこに新しい意味解釈が生まれる。
⑤ 自己認識が深まり、肯定的な自己イメージが生まれ、将来に対してポジティヴに考えるようになる。
⑥ 自分が経験したことは自分だけの体験で、他の人と共有できない特異なものであると感じていたことが、
実際は、そのような体験は他人にも起こっていることであることを知り、他人と共有することで
新しい解釈が生まれる。
⑦ 自分の体験を他人と共有することで、喜び、満足、内面の平穏を得られる可能性がある。
⑧ ある種の重荷から解放され、経験が正当化される。
⑨ 自分が孤立した人間であるという視点を超え、「人間の共同体」と自分を関係づける可能性がある。
⑩ 語り、書くプロセスで、自分の視点だけでなく、他人の視点が入り、人生の見方が変化する。
以上、自分史的エッセイを書くことを物語、ストーリーを書くことと見なし、それがもつさまざまな意味と機能について述べてきた。第7章では、物語論の視点から、ライフストーリー研究の教育実践の可能性を考察したい。
参考文献
アトキンソン、ロバート 2006、『私たちの中にある物語』ミネルヴァ書房
浅野智彦 2001、『自己への物語論的接近―家族治療から社会学へ』頸草書房
色川大吉 2000、『“元祖”が語る自分史のすべて』草の根出版会
色川大吉 1978、『ある昭和史―自分史の試み』中央公論社
色川大吉 2005、『カチューシャの青春 昭和自分史』小学館
色川大吉 2005、『廃墟に立つ 昭和自分史』小学館
榎木博明 2002、『〈ほんとうの自分〉のつくり方―自己物語の心理学』講談社
かすがい市民文化財団 2006、『伝えたい私の物語』サンライズ出版
語り継ぎたいあの大戦編集委員会、2005、『戦後60年 語り継ぎたいあの大戦』揺濫社
小林多寿子 1997、『物語られる「人生」―自分史を書くということ』学陽書房
小林多寿子 2000、「人生の語りとナラティヴ・アプローチ」大村英昭『臨床社会学を学ぶ人の
ために』世界思想社:72-91頁
早乙女勝元 1981(初版1961年)、『下町の故郷』理論社
早乙女勝元 2007(初版1971年)、『東京大空襲―昭和20年3月10日の記録―』岩波新
書
鈴木政子 1980、『あの日夕焼け 母さんの太平洋戦争』立風書房
鈴木政子 1986、『自分史 それぞれの書き方とまとめ方』日本エディタースクール出版部
高木敏子 2000、『ガラスのうさぎ』金の星社
塚田守 2009、「「戦争体験」の語り継ぎ―自分史作品の分析から」『椙山女学園大学研究論
集』第40号(社会科学篇):13-28頁
内藤洋子 1991、『わが故郷は平野金物店』エフェー出版
中野 卓 1992、『「学徒出陣」前夜―ある従軍学生のみた戦争』新曜社
野口裕三 2002、『物語としてのケア―ナラティヴ・アプローチの世界へ』医学書院
やまだようこ 2000、『人生を物語る―生成のライフストーリー』ミネルヴァ書房
吉澤輝夫編集 1995、『現代のエスプリ―自分史』338号
はじめに
本章は、JOHA第9回大会(2011年9月11日)で報告した「男性養護教諭へのインタビューとアーカイヴをめぐって」を、全面的に改稿したものである。
本科研で、「ライフストーリー文庫~きのうの私~」(https://blog.sugiyama-u.ac.jp/user/
mamoru/index.html)というウェブサイトの立ち上げは中心的な取り組みの一つであった(2011年3月~)。そのサイトの重要なコンテンツに、「自分史的エッセイ」と「語られたストーリー」がある。後者は、大学生たちの授業実践として行われたインタビュー(2章と6章で横家が考察)と、筆者ら研究者によるインタビューを編集した語り(本章の対象)が掲載されている。本章は、「語られたストーリー」に収録された「男性養護教諭のパイオニアとして生きる」(2011年2月18日掲載)を扱う。
本章は、インタビュー(聞き取り)に関する近年の議論およびテキストの説明を整理し(1節・2節)、アーカイブ化されたライフストーリー・インタビュー例を確認し、「語られたストーリー」に関して若干説明する(3節)。そして、筆者の事例(ウェブサイトでの記述)と、それをもとにした考察を示す(4節)。
本章で取り上げる対象者は、(元)男性養護教諭である。いわゆる小中高校等の保健室の先生は、全国で約4万人いるが、そのなかで男性はわずか50人しかいない。これまでこのテーマに関する調査研究は、養成校関係者(養護教育学等)らによる質問紙意識調査をもとになされ、複数配置での可能性や男性であることの長所短所等が議論されてきた。筆者は社会学の立場から、幾つかの論考を示している(川又・寺田 2008他)。本科研の調査として、元養護教諭や現職養護教諭・志望者たちへインタビューも実施した。それらの調査から見出された現代的課題を示しつつ、この語り手をウェブサイトに掲載した意義を振り返りたい。
1.ライフストーリー・インタビューに関する議論
3章で「ライフストーリー」の方法論的議論を確認したが、本節では、インタビューに関連する議論として、(蘭 2009)によるライフストーリー論の的確なまとめを見ておきたい。
蘭は、(桜井 2002)が提示した方法論を、自分なりに整理し、「語り手の語りを文書資料などで補強し、歴史などの外的基準に見合った唯一のライフヒストリーを再構成することをめざす実証主義的アプローチでもなく、あるいは、1人ひとりの語りを複数重ね合わせることで唯一のライフヒストリーに迫ろうとする解釈主義的アプローチでもなく、語り手と聞き手の相互行為を基盤としたライフストーリーの構成のあり方に焦点をあてて語りの分析や解釈をおこなおうとする第3のアプローチ」としての「対話的構築主義アプローチ」が登場したとことに賛同し、その方法論的展開に、自らも続いたと位置付けている(蘭 2009,p.38)。
蘭は、このライフストーリーの調査手続きについて、「録音を前提としてインタビューをおこない、それをトランスクリプションすること、トランスクリプトの作成方法も、従来と大きく異なり、聞き手側の質問や語りも語り手の語りと同じように、省略されることなく書き起こすこと、また、インタビューの最初から最後まで、継起順序にしたがって書き起こすこと、そして、語り手にトランスクリプトを返してチェックをしてもらい、インタビュー・テクストを確定することなど」が広く共有されていることを指摘している(蘭 2009,pp.38-39)。
しかし、蘭は方法論が確立したことに比して、ライフストーリー論文から語り手の「“声”や“リアリティ”がもうひとつ聞こえてこない、見えてこないように思えることもしばしば」だと述べ、その理由として、方法の標準化や方法論の内部の問題を論じた。そして、「アクティヴな聞き手としてインタビューの場に」臨むこと、具体的には「論文で聞かせるべき“声”を語り手の口から語ってもらうように」、聞き手は、「幅広い『背景知』をたくわえ、聞き取りのリソースを増やしておく必要が」あると主張した(蘭 2009,p.41)。もちろん、インタビューにおいて、聞き手側の基本的な態度というものはあるだろう ⑴。
上記の議論からすれば、「ライフストーリー文庫~きのうの私~」に掲載されている「語られたストーリー」における筆者の試みは、「対話的構築主義アプローチ」ではない。インタビュー場面で得られた内容を、聞き手・語り手の確認のもと、相互修正によって構成しているが、最終的には、あくまでも語り手が独白している形で記述しており、「自分史的エッセイ」に近い。学生たちの作品は、会話形式で記述されているが、「読者」を想定した大きな編集も入っている(2章参照)。
石川良子は、調査者の経験を記述することの意義として、調査協力者の経験のより深い理解を可能にする点、読者を加えた三者関係としてとらえる点を挙げている(石川 2012,p.41)。本科研での試みは、読者に重きを置いている部分で、石川の後者の指摘に関連するものもあるだろう。
本科研のウェブサイト「ライフストーリー文庫~きのうの私~」は、同サイトに記述されているとおり、「自らのストーリーを語ることは、自分自身への贈り物であると同時に、他の人びとへの贈り物になる」という考えが基本にある。筆者は、自らがこれまで出会った多様な語り手の方々に了承を得て、その語りを広く公開したいと考えている ⑵。
2.インタビューからライフストーリーへ
数多くのライフストーリー関連書が刊行されているが、テキストの中で、調査過程はどのように説明されているのかを、本節で確認しておこう。
(1)桜井厚の説明
桜井は、小林多寿子との共編著で、ライフストーリー・インタビューの具体的な方法を解説している(桜井・小林 2005)。その第3章では、「ライフストーリーをもとに概念構成や理論構築へつながる道筋を検討」している(桜井・小林 2005,p.130)。
まず、インタビューの語りの内容だけではなく、場の状況説明や、しぐさや表情、沈黙などを含めたトランスクリプトの記述の必要性が述べられる。また、解釈の軸として、「語られた〈物語世界〉のナラティヴの特質に照準するもの」と「インタビューの相互行為をふくむ社会的、制度的コンテクストに照準するもの」があるとされる(桜井・小林 2005,p.163)。そして、語りが、自らをコミュニティや全体社会と関連づけること、今まで語られなかったことが語られる可能性、調査者側で気をつけるべきことなどが丁寧な具体例とともに説明されている。
(2)大久保孝治の実践
大学の社会学調査実習ゼミで調査を実施し、ライフストーリーの報告書を作成している大久保孝治は、ブックレットに「ライフストーリー・インタビュー」の流れを簡潔にまとめている(大久保 2009)。紙幅制限が厳しい(と推察する)なかで、的確に説明している。
大学生たちの社会調査としての実践は、少なからぬ大学・短大等で実践されていると思われるが、テキスト化されたものは多くない ⑶。本項でこれを少々紹介する。
大久保は「データの収集」「データの加工」「データの分析」という三段階で説明をしている。
まずデータの収集は、準備と実践である。対象者選定、インタビューのアポイントメント、インタビューでの持参物、「現在の生活」から聞く聞き方、「これまでの人生」のアウトラインを聞くアプローチ(学校経歴、家族経歴)、人生年表(ライフコース整理表)によるまとめ方、「転機」へのアプローチ、「これからの人生」など、インタビュー場面での動きが説明されている。
次に、データの加工は、ライフストーリーの編集と、その検討である。録音データの文章化(トランスクリプション)についてPCでの作業が説明されている。
最後に、データの分析は、事例を基づいた説明がなされている。ライフストーリーを読んで分析テーマを見つける作業と、特定の分析テーマの視点からライフストーリーを読み返す作業を何度か繰り返し、テーマを見出す。大久保の学生は、テーマを自由に決める場合と設定されたテーマで分析する場合とがあり、それぞれ長所短所があると説明される。そして複数のケースを読むことで、「多数派の語り」(「支配的な語り」)と「少数派の語り」(「下位文化的な語り」「対抗文化的な語り」)、「オルタナティブな語り」を見出し、「個々人の『語り』の背後に存在する『語り』のパターンについて考察するとともに、なぜある対象者はある『語り』のパターンを採用し、別の対象者は別の『パターン』を採用するのかを各対象者の経歴や現在の状況を踏まえて考察する」のだと述べている(大久保 2009,p.46)。
大久保は、「ライフストーリー分析」とは「人びとが『人生を生きる』仕方の分析であり、それを通して、人びとが置かれている社会的状況と、その社会的状況への人びとの適応について考察しようとするものである」と説明している(大久保 同上)。
(3)野入直美の実践
3章でも言及した野入直美は、「共同研究として体験した在日朝鮮人のライフヒストリー調査と分析過程を振り返り、聞き取りから作品化にいたる過程」の実践を説明している(野入 2009,p.91)。
谷の調査に同行した野入は、ある語り手の話に圧倒されつつ、「豊かな〈個〉のありように肉薄した、質的な深みのある調査は、結果として、〈構造〉の把握に向かう新たな仮説へ」導く可能性を感じた(野入 2009,p.92-93)。だが、「〈個〉のデータから〈構造〉を見出していく作業の困難さが、目の前に大きく立ちふさが」る(野入 2009,p.93)。その共同研究では、のべ20人ほどの研究者たちが、57人分のトランスクリプト(逐語録=インタビュー資料)と向き合い、4つの家族・親族集団に分け、年長者から若年者に通読し、「世代間の〈関連と比較〉」を行うことになった(野入 同上)。
さらに、キリスト教信仰を継承してきたV家の分析を担当した野入は、通時的な理解を通じて、世代による隔たりを見出し、また、「戦前移動世代」と「戦後世代」の分類を通じて、社会変動と結びついた理解が進み、さらに、世代を超えた共通のパターンとして「家族の文化と個人の意味づけの相互作用、〈継承〉と〈獲得〉の関連が見えてきた」という(野入 2009,p.94-99)。
3. ライフストーリーのアーカイブ化
ライフストーリーは報告書に記述されたり、論文化されたりするばかりはない。ウェブサイトに文字、録音、映像データが公開される例も近年見られるようになった。アーカイブ化に関しては、音声データばかりでなく、映像も視野に入れた議論、収集や管理に関する問題などすでに幅広い議論がある(安倍・加藤 2008他)。ライフストーリー(安倍らの用語では、オーラルヒストリー)のインタビューについて、本節ではその幾つかの事例を確認しておきたい。
(1)ウェブ上での実践例
本科研を進めるために参照した幾つかのプロジェクトを確認しておこう。
① ロバート・アトキンソン「ライフストーリーセンター」
塚田の紹介により、同サイト(http://usm.maine.edu/olli/national/lifestorycenter/)を確認した。そもそも、このサイトの日本語版を目指したのが本科研の計画の一つであった。
塚田がアトキンソンの実践を学び、そのサイトの管理運営も参照しながら、本サイトのコンテンツ等を議論した(1章参照)。
② ディペックス・ジャパン「健康と病いの語り」
乳ガン・前立腺ガン患者自身が語りを公開しているウェブサイト「NPO健康と病いの語り ディペックス・ジャパン」(http://www.dipex-j.org/)がある。体験者しか分からないことを語ることは、同病者にとって、大いに助けになるだろう。
同サイトでは、データシェアリングも推進している。一つの病気について、12~15時間分がウェブサイト上で公開されているが、それは実際のインタビューの10~20%であるという。非公開分については、利用したい者がいれば、非営利目的で申請し、ディペックス・ジャパン倫理委員会が審査して許可された場合、有料でテキスト形式のデータが一定期間貸与されるとされている。
③ 桜井厚「ライフストーリー・アーカイブズ」
本ウェブサイト作成時期(2011年秋)に、桜井厚によるウェブサイト(http://lifestory
interview.net/wordpress/)も確認した。「日本の経験を語る」と題されたこのサイトでは、「戦争体験」「境界文化」「問題経験の現代史」「オーラル資料」などのカテゴリーが設定されている。
制作中らしき様子だが、2013年2月に確認したところ、「戦争体験」のアーカイブとして、5人のインタビューの一部がテキストデータと音声データが掲載されている。桜井の応答も含まれて、インタビューの様子が数分ずつ確認できる。「映像データ」の項目も設定され(リンクはされていないので制作途中と思われる)ており、「アーカイブ化」の検討と実践がなされるのだろうと推測される。
④ 全米日系人博物館
3章と本章で紹介したテキストにおいて野入は、「ライフヒストリーの共有に向けて」という節を設け、全米日経博物館の「ディスカバー・ニッケイ」(http://www.discovernikkei.org/ja/
interviews/)のことを記述している(野入 2009,pp.104-105)。同サイトでは、日系人のインタビューが、映像とテキストデータで紹介されているが、2013年2月に確認したところ、140人以上のインタビューが収録されていた。
(2)本科研のもう一つの目標
本科研の目的の一つは、これまで紙媒体で公表してきた作品を、デジタル化し、ウェブ上公開することで、より多くの読者へ提供することにあった。先述の通り、独自のウェブサイトを立ち上げた。そこに含まるもの(現状のサイトでは「研究論文」というコンテンツを準備していた)として、これまで各人が収集したライフストーリー(研究論文等)を、広く一般向けの「読み物」として提示することが議論された。だが、この3年間は「自分史的エッセイ」と「語られたストーリー」を中心に進めてきたこともあり、現時点でこのコンテンツは完成していない。
① 方針
語りは数時間から十数時間に及ぶものもある。研究ということであれば、その長さ自体に意味が付与され、内容整理もその観点からの切り口があるだろう。だが、一般向けということであれば、ある程度の縮減が必要であるという認識は、本科研メンバー3名のなかで共有された。
② 注意点
ウェブ上で公開の問題点として、プライバシー保護が議論された。「個人が特定される情報は掲載しない」という基本原則が決まった。また、ウェブサイトの維持期間もとりあえず「3年」という限定をかけた。また、改めて、同意書等の共通フォームを定め、共有化した。各事例において、語り手たちに再度内容を確認してもらい、同意書を得たもののみウェブ上に公開することとなった。
(3)「語られたストーリー」とA氏の事例
本科研において筆者は、「語られたストーリー」に、過去の調査とこの3年間の調査で得られたなかから選択するつもりでいた。なかでも、近年インタビューをしている「男性養護教諭」と「元牧師」は、筆者自身の興味関心とは別に、その個人の語り自体に、読者側から興味をもたれるのではないかと考えていた。
筆者は、近年、「老年期の宗教指導者」(仏教、神道、キリスト教、新宗教他)、「過疎地域の人びと」、「放課後児童クラブ指導員」、「海女」などに関する調査をしている。これらを広く括る語彙に「マイノリティ」が挙げられよう。かねてから述べられてきたように、統計的分析が困難なマイノリティの研究において、個人の生活史を聞き取るインタビューは有効であろう。
次節では、「語られたストーリー」としてA氏を紹介する。A氏へのインタビューは、2009年、2010年に行い、それぞれトランスクリプト(逐語録)を作成し、確認していただいた。また、紀要論文作成のご許可をいただいた(川又 2011)。
本科研のウェブ公開に関して、筆者自身の調査を振り返り、どのような語り手がいいかを検討し、まず、A氏をと考えた。氏には、掲載内容を再度確認していただき、加筆修正を行い、掲載した。まあ、編集において、ウェブ一般公開を考え、読みやすさという視点での修正も行った。ただしこれは、自らでは完了せず、編集者に依頼し、その赤入れでの確認作業も行った(2章参照)。
4.事例
(1)A氏のライフストーリーの概要
看護師として精神科で働いた語り手A氏は、大学特別別科で養護教諭免許状を取得する。ある県の小学校で1年間勤務し、学校現場で健康を守る養護教諭の重要性を認識。その後、看護系高校で看護教員として10数年の勤務を経て、定時制高校の養護教諭として復帰した。とくに男子生徒から歓迎され、女子生徒へも手洗い触診や多様な健康相談で対応した。その高校では、不登校気味の生徒を100%卒業へ導いた。
その一方で、男性養護教諭の認知度を向上させるため、彼は講演活動も行っていた。男性を強調するのではなく、養護教諭の能力があれば性別は変わらないことを主張した。その後、山村留学の小中学校で勤務し、現在では退職して、後輩たちにエールを送る立場になり、「男性養護教諭友の会」の基礎作りを行った。
(2)語り手について
A氏は退職した元養護教諭である。筆者が初めて出会ったときは、すでに退職されていた。彼の特徴は、看護師免許を保持していることである。養護教諭は養護教諭免許状(専修、1種、2種)を取得し、教員採用試験に合格してなる職種である。免許状は大学・短大の養成校卒業によって与えられるが、看護師免許保持者は、大学特別別科1年の学びで免許状が取得可能である。
彼の養護教諭としての現場経験は10年に満たないが、その背景には、病院での看護師経験と、看護教員としての10数年の勤務がある(クラス担任経験)。これらの経験は、彼がその後の高校や小中学校での養護教諭経験に役立った。
養護教諭の資質能力形成過程の研究からは、性格的資質(前向き、素直、謙虚、慎重、強い意志)、学習資質(努力、向上心、自己成長)、専門能力(連携能力、対応力、情報管理能力、観察力、判断力、行動力)等が見出されている。A氏には、上記の能力が含まれていることが語りのなかから理解されよう。とくに、前向きなところや、連携能力、行動力面で彼は卓越している。さらに情報発信能力にも優れており、講演活動のみならず、高校勤務時代以降、彼の存在は、後に続く男性養護教諭志望者にとって、理想的な存在となっていた。
彼の保健室経営の方法は、決して男性養護教諭特有だということではない。彼は現役時代、研修会等で保健室経営に関する講演を何度も行っている。だが、女子児童生徒に対してできる限りの配慮を心がけた対応の例は、他の男性養護教諭の参考になっている。
彼は既婚者でもあり、高校勤務時代の彼の年齢は、生徒たちにとって保護者世代に相当する。教員は年齢性別等で、児童生徒からの対応も異なる。男性養護教諭も既婚未婚、年齢等は、彼らの養護教諭としての資質以外の要素として、今後考慮する必要があることに、筆者は、彼の語りを聞きながら気づかされた。
(3)A氏の語りと男性養護教諭のキャリアパターン
① 採用試験合格まで
A氏:入学後、私と指導教官と二人で教育委員会に行って、男性の養護教諭についての話をしました。
でも、理解してもらえない訳ですね、男性養護教諭のことを。そして、希望を与えてくれないような
お話をされました。大きくは三つ。一つは、「PTAが許してくれないだろう」。それから、「男性は
初潮教育できるんですか」。そして三つ目。「女子児童にも触れることあるでしょう。
あなたは、触れますか」。そんなの常識で考えたら分かりますよね。
A氏は、大学の特別別科在学中、上記のような対応を受け、同県での男子採用がないと言われる。結果、男性養護教諭の採用実績のある県を受験して合格した。
教員採用試験を目指す受験生は、自分なりの理想と厳しい現実のギャップに悩む。現役合格者はわずかであり、多くは何度も採用試験を受け続けている(5年以上の浪人経験もいる)。「もしかしたら、自分は男性だから(養護教諭として)採用されないのではないか」との考えが頭をよぎる者もいる。彼らは、合格するまで落ち着かない不安な日々を過ごす。他の道へ転ずる人もいる。
大学(短大・大学院)を卒業した彼らは、非正規教員(有期常勤や非常勤という雇用形態)で学校現場に立てる者もいれば、受験勉強に専念する者もいる。希望しても臨採(臨時採用による養護助教諭勤務)の声がかからない場合、アルバイトで食いつないで受験勉強を続ける。採用までその生活が続く。養護教諭の倍率は他の科目同様、ほぼ10数倍である(もちろん女性の志望者も、同様の経路を辿る)。
養護教諭以外の教員免許状、たとえば小学校教諭等の免許を取得している場合、転ずることも考えるという。教員採用試験こそが当事者の最大関心事である。自らが不合格で知人・友人の女性だけが合格だった場合、それは「性差」が理由ではないかとの疑念も起きる。採用試験の点数等の情報が開示されるようになってきたため、結果を確認できる近年では、それらの疑念も払拭されているだろうが、採用試験を突破できないなかで、彼らが疑心暗鬼に駆られるのもやむを得ないかもしれない。
② 若手教員
A氏:保健室には、意外と心配なく、小学校6年の女の子も来てくれました。でもそれは、5年生の
担任の女性の先生でW先生が、性教育の時間に私を教室に入れてくれて、女子に対する性教育を
見学させてくれたんです。それがよかったかなと思います。当時は、男・女を分けて(性教育を)行って
いて、それを私に見学させてくれた。そういうことが、後で、ああこういう話なんだな、こうすれば
いいんだなと役に立ちました。W先生は、とても熱心ですごく理解がありました。
それで、授業(で教室)に入っていたこともあって、女の子たちも(私に対して)安心してくれて、
保健室の利用率は、前年度の先生より高くなったんです。
同僚たちの協力もあり、このように1年目を順調に過ごしたA氏だが、故郷の県から声が掛かり、結局、そちらの看護教員として転勤した。
「実際の活動のなかで男性だからという理由で不都合に感じたことは現時点ではありません」と述べる現職者もいるが、実際に職場に就いてみると、想像以上に「男性」「女性」の差はなかったというのが彼らの実感である。
もちろん、勤務当初、同僚教職員・管理職・保護者たちが「男性養護教諭」に慣れていない場合、彼ら自身が周囲の人びとへ自らのことを詳しく説明する必要も出てくる。女性教員との連携が必要な場面もあり、周囲との信頼関係が構築されるまでは、気をつけなければいけないことも多い。だが、どちらかというと、「男性」としてというよりは、むしろ、一人の教員として信頼してもらえるように、日々誠実に仕事をこなしていくことが重要だと彼らは感じている。教員としての経験値が低い彼らは、一般の教職員を含め、周囲から多くを学ぶ。
養護教諭において、単数配置(保健室に養護教諭が一人配置される)と複数配置(二人以上の養護教諭が配置される。大規模校など)とでは大きく違う。後者の場合、一緒に仕事をする相手から多くを学べる可能性もある。「『男性なので、どこまでできるかな』って思っていたと言われたことがあります」と語る彼は、結果的に、ペアを組む年配の女性養護教諭から多くの経験を学んでいった。逆に、相手とうまくいかない場合、困難を抱え込むこともある。建前として、職務である以上個人的感情は関係ないと言えようが、どの職場でも、人間関係の問題は多かれ少なかれ存在する。
勤務校の管理職や一般教職員の理解度も、彼らの勤務に影響を与える。一般的に、若手教員はそもそも年齢が若い。ある20歳代の教員は、養護教諭一年目を歩むなかで「『男性』というよりも『若さ』により、親しみやすさなどのメリットを多々感じます」と、若さという利点を自覚する。「さまざまな経験を通して生徒と寄り添い、学び、自分の武器を見つけたいと思います」と言う。たしかに若いということは大きな利点である。児童生徒のなかに飛び込んでいくことができる。そして、彼女ら彼らと積極的に交流し、児童生徒への理解が深まり、養護教諭として実践に役立つ。そういう利点がある間に、他の自分らしさ(利点)をもてるよう努力しようと考える。若いが故に、児童生徒側が、男性性を強く受け取る場面もなくはない。多くの経験を積み重ねながら、彼らは成長を続ける。
③ 中堅教員
A氏:(高校赴任後)保健室に興味関心を引き入れる作戦をするわけです。結果的には、全部成功
しましたね。一つ目は、廊下で会う度に、「こんにちは。今度、二人で保健室に遊びに来てください」と
(生徒たちに)声をかけまくりました。向こうは何だろうと思ったと思います。でも、男性養護教諭という
興味もあったと思いますが、休み時間に来てくれました。(‥略‥)二つ目は、女子に対する処置や
触診です。捻挫や打撲、皮膚疾患などで触れることが必要なときは、手を石鹸で必要以上に洗って、
声をかけて見せました。胸やお腹の触診が必要なときは、もう一人来ているので、その子に指示を
出して触ってもらっていました。保健室から出している「保健便り」も、A4サイズで文章を短く、電車の
中吊り方式で、見出しで勝負しようとして、とにかく見てもらおうとしました。
看護教員を10数年経験した後、ある定時制高校で、養護教諭として赴任した。
10年前後の経験を積み、中堅的立場になる頃には、多くの問題に対処できるようになる。自らの個性を生かした教育活動を進めたいという意欲から、年度ごとに様々な健康相談活動のテーマを定め、工夫した内容を考え実践したり、自ら研究調査を行ったりする者も多い。
男子生徒は男性養護教諭を、女子生徒は女性養護教諭を求めるのではないかという短絡的理解に対し、逆に「男子生徒の場合、(養護教諭に)母性を強く求める部分もある」ことも実感する。児童生徒たちには、養護教諭の性別は絶対的なものではなく、必要とされる内容も多様だと分かり、それに(教育的指導も含めて)臨機応変に応じられるようになっていく。
「(女子生徒に対して)ここからは踏み込めない、ここまで踏み込めるというラインがある(=見えてくる)ので、それをうまく使いながらやっていけばいい」という考えもある。その場合、ペアの女性養護教諭との連携が重要であるが、意思疎通ができていれば問題ない。また、「(ペアの女性養護教諭が)すごく優しすぎるというか、甘やかしすぎと感じることもある」との感想をもつ場合もある。しかし、ペアとして必要な対応をとり、お互いの対応を理解し合うことで、保健室を有機的に機能させればいいと考えられている。
部活動等の顧問をしている者もいれば、校務分掌を複数受けもつ者もいる。彼らは「保健室」ばかりではなく、学校内外へ教育活動の範囲を広げていく。「部活動の顧問をしているっていうのは、こどもたちの健康なときの姿を見ておけば、相談に来たときの悩みを違う意味で解決してやれると思っているからです」という彼は、部活動顧問と「保健室の先生」という二つの顔をうまく使い分けている。養護教諭の研修会や他の勉強会・研究会などに積極的に参加する者も多い。そして、多様な事例検討会の学びを通じて、自らが学内で抱えている諸問題を解決する方策を身につけていく。
④ ベテラン教員
A氏:(地元紙にA氏の紹介記事が掲載され)年間30回位の講演依頼がありました。
(高校は)定時制で出勤は午後2時半でよかったので、午前中の講演はできるかぎり受けるようにして、
時間の調整をしました。自分のやっていることを、講演の機会があったらどんどん言って。
男がいいとかは一切言わずに、「こうしてやっていました」と。講演活動して、「男もこうしてやっています」
と伝える。
A氏は、高校と小中学校で養護教諭勤務をし、その間、講演活動や男子学生実習の受け入れなどもしていた。そして、定年を迎え、退職した。
筆者は彼以外に、特別支援学校(赴任時は養護学校)で30年近く勤務されたベテラン教諭からも話をうかがった。単数配置も複数配置も転勤も多く経験している方からの語りからも、キャリアパターンの変遷のなかで、困難を乗り越え、ベテランの域に達した様子がうかがえた。
(4)小括
前項で、キャリアパターンで4区分し、他のインタビュー調査を通じての考察を記述した。同時に、ウェブ上で紹介したA氏の同時期の様子の語りを示した。教員としての成長、前段階での問題が次の段階で解決している様子などが示された。
若い(新卒)養護教諭の働きかけは、一方向的・画一的なものに陥りやすいが、経験を重ねることで、担任教師・管理職・保護・専門機関等、連携相手が増えると同時に、周囲からの信頼を得、連携が相互的に働くことという研究報告もある。ごく当たり前の結論だが、同様の流れを確認できた。
教員志望段階では、大学時代の環境や教員採用試験の困難状況等から、「男女の差」(の有無)を強く意識するが、若手教員として勤務すると、赴任当初以外は「男女の差」よりむしろ「養護教諭」としての自らの力量不足を実感する。周囲の教職員・保護者(の理解度)等の環境面の違いもあるが、資質向上こそが重要だと認識して努力を続けた中堅教員になると、ある程度の自負も出てきて「男女の差」(男性であることのマイナス)はないとの見解をもつようになる。
圧倒的マイノリティたる男性志望者は、各都道府県での採用実績が乏しい状況で、横のつながりがほとんどなく、孤独に努力してきた。何名もが突破したが、今後は、2010年8月に結成された「男性養護教諭友の会」(2012年に第3回の研究会実施、会報創刊)の存在は、同様の目標をもつ志望者(学生・非常勤講師)たちにとって、大きな意義をもつだろう。A氏など退職されたパイオニアたる先輩や現役活躍中の中堅教員の存在も、彼らには心強いに違いない。
むすびにかえて――出会いと思いと
本科研代表の塚田守は、「ライフストーリー研究の醍醐味」として、中野卓や蘭信三の例を挙げつつ、「人との出会いから始まる」ことの重要性と、にもかかわらず、論文等では捨象されがちなポイントであることを指摘している(塚田 2011,p.205)。これを受ける形で、筆者が現時点まで「語られたストーリー」で掲載している語り手たち出会いを記し、本章を閉じることにする。
本章で事例に取り上げた「男性養護教諭のパイオニア」との出会いは、新聞記事紹介にある。筆者は勤務校で養護教諭養成(に関する授業担当およびゼミ担当)に携わる者として、共学化して男性の免許保持者が出ても、正規採用がなかなか出ない現況から、この記事を見たとき、ぜひ一度お話をうかがいと思っていた。そして、勤務校へ手紙を送ったところ、逆に、当方に関心をもっていただき、数回のやり取りの後、お目にかかることになったのである。以後は先述の通りである。
「老年期の過ごし方を考え続ける元牧師」(2012年2月29日掲載)での語り手ある元牧師との出会いは、筆者が1990年代に実施したキリスト教会の死者儀礼調査であった。その時現役牧師だった彼は、地方の教会で熱心に死者儀礼へ関与して多くの信者を集めた方だった。その後引退し、数年ケアハウスに居たことを、その後の年賀状のみのやり取りで知っていたが、筆者の短大勤務に伴い、実に10数年ぶりに再会した。そして、老年期の宗教指導者という大きなテーマを発見した。奥様(牧師夫人)からもお話をうかがうことができ、研究調査を通じた関係であっても、それぞれのライフコース上の様々な変化を考える機会を与えていただいたと思っている。
「寝屋子と寝屋親を体験した漁師のはなし」(2012年2月29日掲載)での語り手の漁師との出会いは、地元関係者の紹介による。鳥羽市答志島の寝屋制度は、民俗学的に注目され、これまで数多くの調査がなされている。マスメディアにもしばしば取り上げられている。筆者は泉正幸氏とともに共同調査を3年以上続けている(泉 2011)(川又 2012)。この方は、とくに詳しく寝屋の過去と現在および自らの体験を詳しく教えていただいた方であった。その後も、現地を訪れるたびに、挨拶を交わし、近況報告等をさせていただいている。
筆者は、20年ほど前から、自らの興味関心により、全国各地の様々な年代の人びとから、それぞれの生活史を聞き取るインタビュー調査を続けている。これまで、実に多くの方々から多くの学びを得た。これまでそのごく一部しかアウトプットできていないし、今後も、数多くを出すことはできないだろう。だが、アウトプットできてない「出会い」からも、多くの知見を得、そこからさまざまなアイディアが浮上したり、ヒントを得たりしている。言うまでもないことだが、それらすべてが、現在進行形の研究者・生活者たる筆者を作っているのだとも言えよう。
語り手の方々とは、ある時期に頻繁に会っていても、やがて、ある程度調査研究が落ち着くと、しばらく会わない時期が生ずる。それは、同級生や他の知り合いとも同様かもしれない。研究者の都合で語り手の方々との交流が粗密になるというのは、ずいぶん身勝手だとも言えよう。だが、研究者としての歩みを進める中で、先の元牧師との再会のようなことは、今後もあるかもしれない。そして、そのこと自体、インタビューを中心にした調査の研究テーマの一つになるかもしれない。筆者たちは、語り手の方々の人生の一部を共有しつつ(逆に、筆者の人生において、語り手の方々は確実にその一部を占めている)、今後も、多くの聞き取りを続け、それぞれのテーマを共に考えていきたい。
注
(1)塚田守は、ライフストーリー・インタビューの基本的態度として「無知の態度」「共感的理
解」「人としての興味関心を示す態度」を挙げている(塚田 2005)。筆者自身もそのように思
っている。
(2)当然と言えば当然だが、語り手が皆、ウェブ上の掲載を許可するわけではない。いったん
掲載を許可した後、内容を自ら大幅修正し、さらに、読者に誤解を招くかもしれないと、最終
的に掲載否という例もあった。
(3)その数少ない実践例が、横家純一の実践である(横家 2001他)。本報告書でもその実
践が報告されている。生活史研究会では、第79回例会(2001年10月14日)で、その横家
と村田貞雄が報告者となった「社会学教育における生活史調査」というシンポジウムを行った
(コーディネーターは筆者)。塚田守は学生の卒業論文を材料に「病いの体験」の再解釈を
論じている(塚田 2012)。卒業研究等でライフストーリー・インタビューを行う例は、本科研メ
ンバーだけではなく、広く教育実践されていると思われる。
文献
安倍尚紀・加藤直子,2008,「組織的に体系化されたオーラルヒストリー――研究機関に基盤
を置き、組織的な研究方法を用いるオーラルヒストリーの可能性」『日本オーラル・ヒストリー
研究』,4号,pp.65-84.
蘭由岐子,2009,「いま、あらためて“声”と向きあう」『社会と調査』,3号,pp.38-44.
石川良子,2012,「ライフストーリー研究における調査者の経験の自己言及的記述の意義―
―インタビューの対話性に着目して」『年報社会学論集』,25,pp.1-12.
泉正幸,2011,「答志における寝屋子研究」『鈴鹿短期大学紀要』,35号,pp.35-40.
川又俊則・寺田圭吾,2008,「養護教諭とジェンダー(1)――保健管理センター助手の事例よ
り」『鈴鹿短期大学紀要』,28号,pp.123-147.
川又俊則,2011,「養護教諭とジェンダー(2)――あるベテラン男性養護教諭のライフヒストリー
を中心に」『鈴鹿短期大学紀要』,31号,pp.12-17.
川又俊則,2012a,「養護教諭とジェンダー(3)――看護師・保育士との比較」,川又俊則他編
『養護教諭の複数配置に関する社会学的研究』,川又研究室,pp.12-17.
川又俊則,2012b,「『男の』と問うのは誰か」『中学保健ニュース』1530号付録,pp.4-5.
川又俊則,2012c,「答志の寝屋制度と『放課後』」『生活コミュニケーション学年報』3号,
pp.35-42.
大久保孝治,2009,『ライフストーリー分析――質的調査入門』,学文社。
野入直美,2009,「ライフヒストリー分析」谷富夫他編『よくわかる質的社会調査技法編』,ミネ
ルヴァ書房,pp.90-105.
桜井厚,2002,『インタビューの社会学――ライフストーリーの聞き方』,せりか書房。
桜井厚・小林多寿子,2005,『ライフストーリー・イタビュー――質的研究入門』,せりか書房。
田口純一編,1994,『こころの運動会――女子大生たちのライフ・ヒストリー研究』,北樹出版。
田口純一編,1995,『いのちの舞い――ウィットネスたちがみた人生ドラマ』,六法出版社。
塚田守,2005,「インタビュー調査の反省的検討理論枠組みと方法論をめぐって」『椙山女学
園大学研究論集』,36号(社会科学篇),pp.25-34.
塚田守,2011,「書評 小林多寿子編著『ライフストーリー・ガイドブック――ひとがひとに会う
ために』嵯峨野書院」『日本オーラル・ヒストリー研究』,7号,pp.203-206.
塚田守,2012,「語りによる「意味ある体験」の再解釈の可能性」』日本慢性看護学会誌』,6(1)
号, pp.2-8.
横家純一編,2001,『ショータイム――女たちのライフ・ヒストリー』,あるむ。
横家純一編,2002,『ミラクル・ハンター――椙大生活史研究第1号』,椙山女学園大学横家研究室。
横家純一編,2007,『至福のとき――椙大生活史研究第2号』,椙山女学園大学横家研究室。
横家純一編,2008,『バナナパフェ――椙大生活史研究第3号』,椙山女学園大学横家研究室。
はじめに
「ライフヒストリー研究」という授業の中で、学生たちにインタビュー調査とその記録の提出をお願いしている。その結果、毎年、何点かの作品ができ上がる。その中から、人びとのライフストーリーとして価値あるものを選びだし、作品として公開している。また、卒論のデータとして、「語られたストーリー」や「自分史的エッセイ」を利用したもののうち、やはり、ライフストーリーとしてふさわしいものを選び、公開したものもある。いうまでもなく、いずれも同意書をもらっている。
何をもって、「価値あるもの」とか「ふさわしいもの」とみなしているのかという議論は、別の機会にゆずり、ここでは、これまでの授業活動における、書物として手にとって読みこむという過程が、ディスプレイ上の文字をながめる作業に置き換わったことの意味について考えてみたい。
前者は、近くにあるものをいつくしむ、いわば求心的な態度であるのにたいして、後者は、遠くにあるものを見つづける、いわば遠心的な態度といえよう。求心的な態度では、大切なものがいま・ここにあること、つまり定着していることを前提としているため、その場での議論が深まりやすい。それにたいして、ウェブ公開に不可避である遠心的な態度においては、どうやら本質的なものはいつか・どこかにある、あるいはまた、ゆれ動くものこそが本質である、というような想定を伴っているためか、議論が深まりにくい。さらにいえば、もうすでに、議論がしつくされているかのような印象さえうける。
1.制作の動機づけ
通常15回の授業の中で、それぞれの受講生が、一人の語り手にたいして、60分以上のインタビューをし、その結果を、1本の作品とする。ライフヒストリーというものに、はじめて出会う学生に対して、その概要を説明することは、容易ではない。いくつかの工夫が必要となる。
まず手はじめとして、学生たちのふだんの日常生活と命(ライフ)との接点をさぐる。言いかえると、人間の「働きかけ合い」⑴の中で生まれる命(ライフ)の輝きを指摘する。たとえば、つぎの事例1や事例2のような、命(ライフ)の輝きが絶頂にたっする転機や節目の紹介は、効果的である。
この事例1は、身体的にも精神的にも、ギリギリの「どん底」に追い詰められた語り手が、神に向かって、「責任取れ!」「文句あるか!」とせまると、神から、「文句なし!」という応えが返ってくる場面である。言い換えると、「文句なし!」という神の言葉を、語り手が訊きとるという、奇蹟の場面でもある。これにたいして、科学的な見地から、「そんなはずはない」と断定することほど、ライフストーリー研究の立場から遠いものはない。人の主観の偉大さを読み取るのが、ライフストーリーの醍醐味であるからだ。ただし、受講生たちは、この段階ではまだ、狐につままれたような、半信半疑の状態にとり残されたままである。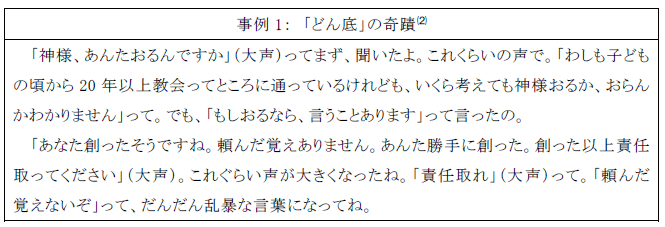 つぎの事例2は、彼女につられて、大学に入った語り手が、彼女にふられたため目標を失い、一応、サッカー部に所属しながらも、孤独な毎日をやり過ごしている場面である。
つぎの事例2は、彼女につられて、大学に入った語り手が、彼女にふられたため目標を失い、一応、サッカー部に所属しながらも、孤独な毎日をやり過ごしている場面である。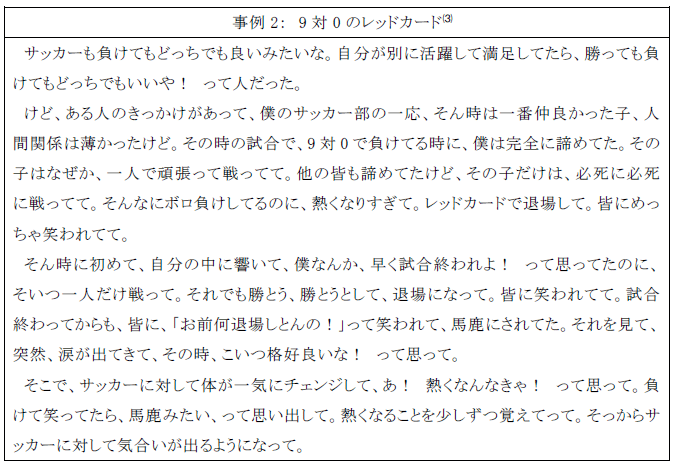 9対0の負けでのレッドカード退場という、「その子」の無謀な行動が、語り手の突然の涙をさそう瞬間は、神こそ出てこないが、事例1の奇蹟体験と等価であろう。周囲に笑われようが、いや、そうであるからこそ、自分の「熱くなんなきゃ!」という思いの優位性が確認でき、それにつづく行動選択の正当性までを保証したのである。
9対0の負けでのレッドカード退場という、「その子」の無謀な行動が、語り手の突然の涙をさそう瞬間は、神こそ出てこないが、事例1の奇蹟体験と等価であろう。周囲に笑われようが、いや、そうであるからこそ、自分の「熱くなんなきゃ!」という思いの優位性が確認でき、それにつづく行動選択の正当性までを保証したのである。
このような事例にふれると、不思議なことに、どんな受身的な受講生であっても、そこに登場する他者の人生に興味をもつようになる。そして、このことがさらに加速すると、実際の聞き取りの場面で、他人の人生が自分の人生の指針になるかもしれないという気づきにもつながる。それはいわば、まっとうな社会認識の形成プロセスともいえる。
2.語り手さがし
以上のような、先行研究の「味わい」⑷をすすめるにつれ、しだいに、自分独自の語り手さがしがはじまる。これまでの多くの作品が示すように、この語り手さがしほど学生たちを苦しめるものはない。たとえば、つぎのような事例がある。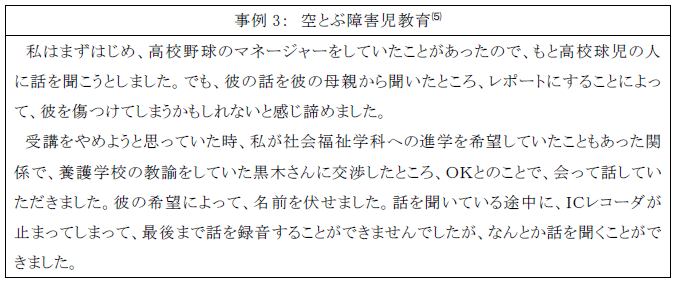 この事例3は、「彼を傷つけてしまうかもしれない」という母の忠告を、たんなる「おせっかい」とみなすことのできなかった学生の見識の限界を示しているだけでなく、われわれの人生が、そういった人と人との働きかけ合いにより形成されていることの、具体的な実践報告とみなすべきであろう。それにしても、学生に、せっかくの授業の「受講をやめようと思っていた」といわせるほどの、重荷はいったいなんなのか。
この事例3は、「彼を傷つけてしまうかもしれない」という母の忠告を、たんなる「おせっかい」とみなすことのできなかった学生の見識の限界を示しているだけでなく、われわれの人生が、そういった人と人との働きかけ合いにより形成されていることの、具体的な実践報告とみなすべきであろう。それにしても、学生に、せっかくの授業の「受講をやめようと思っていた」といわせるほどの、重荷はいったいなんなのか。
「語り手さがし」の重荷とは、住みなれたふだんの生活空間とはやや違ったところへ、自分の意思で出向き、自分が何者であるのかを説明しつつ、他者と交渉しなければならないプロセスからくる。多くの場合、それは、おそらく初めての経験であり、実行力や意欲が乏しい場合は、周囲の圧力により、すぐさま挫折という結果になってしまう。しかしそうであるからこそ、このプロセスで学べることも多い。自分のために、誰かに動いてもらうよう依頼し、相手の厚意にたいして感謝すること、そうすると逆に、自分の中に、人に支えられたという安心感がうまれ、かつ、自分の働きかけが相手に喜んでもらえるかもしれない、という貴重な体験となるからだ。
語り手さがしと前後して、ICレコーダの操作実習をする。実際に、自分の声を録音・再生することは、たんにその技術習得が目的ではない。インタビューされる人の気持ちや戸惑いを思いやり、それにきちんと対処するという、重要な学習を伴っているのである。この経験ののち、実際にインタビューを開始する。インタビューは、通常、1回で終了するが、相手や自分の都合で、2回以上の面会になることもある。
ここでの注意点は、いうまでもなく、録音に頼りきってしまうことの危険性を指摘することである。聞かせていただいているという態度を示しつづけるというマナー上の問題のほかに、その場でメモをとることで、音声表現の曖昧さを確認し、補完することもできるからだ。
3.文章化の作業
こうしてようやく、文章化の作業がはじまる。第2章でも述べたが、そもそも、聞き取りは音声言語である以上、漢字があるわけでもないし、点やマルもない。改行もなければ、カギかっこもない。これらすべては、編集者の裁量で決まる。加工することもあり、創作することだってある。かといって、それがすべて、恣意的であるとはいえない。この点にかんして、桜井厚は、さいきんの著書で、つぎのように言っている。
インタビューが個々の語りの解釈を語り手と交渉していくコミュニケーション過程であることを認めた
上で、トランスクリプトをもとに、さらなる解釈をともなう最終的なストーリーを描く権限は、調査者側に
あることだけは確認しておきたい⑹。
この「最終的なストーリーを描く権限」という、やや力強い表現が、「インタビューの倫理」と題された章での指摘であることを考えると、編集の恣意性といったレベルをつきぬけて、この研究の可能性を称揚しているように思われてならない。
そもそも、音声を文字に変換・加工する技術と実践の中に、人の文化活動の醍醐味をみつけることができる、と力説したい。いくら、ライフストーリーをめぐる音声や映像のアーカイブ化の流れがすすんでも、このような文字文化のもつ創造性を排除することはないだろう。
文章が完成したからといって、終了ではない。ベタ打ちを、読み物に変換する編集がまっているからだ。ここでもっとも重要なのは、タイトル決めである。語り手の生き方の、いわば、「テーマ」⑺をつかみとり、それを印象づける10字ほどの文を考案しなければならないからだ。テーマ選びのベストな方法は、まず全文にわたって小見出しをつけ、それらを貫くメッセージをみつけることである。
しかし、いうまでもなく、人の人生テーマは、一つでない。タイトルが一つである以上、そこには矛盾が生ずる。編集者の仕事は、締め切りのギリギリまで、この二つ以上のものから、一つを選び出すという、強調・焦点化の作業である。だからといって、限界があるという消極的見解をもっているわけではない。しょせん、といっては聞こえが悪いが、人間の活動である以上、バイアスはつきものと考えるべきであろう。絶対的な真実をつかむことは不可能と考えた方が、安全である。むしろ、このようなバイアスの中で〈ゆらぐ〉ものこそ、真実であり、われわれが探しもとめているものかもしれない。
4.作品の考察
さいごに、作品の分析・考察について考えてみたい。これはおもに、研究者や卒論執筆者によってなされるものだが、おおきくわけて、二つある。ある特定の作品を1点とりあげ、その語り手の人生全般について詳細に検討していくもの。もう一つは、いくつかの作品をならべて、それらの特徴について比較するものである。
前者の場合、語り手が生きた時代背景はもとより、その親族関係、交友関係、職業生活で遭遇した転機や重要な他者をめぐる考察がおもな作業となる。後者は、たとえば、「検閲」という視点から、しゃべりすぎてしまったことを語り手自身が反省し、編集の段階で言い換えたり、カットしたりする行為の背後に見え隠れする信念を発見することである。ここには、読みやすくするためにストーリーを加工する、編集者の姿勢についての議論もふくまれよう ⑻。
ただし、「ライフヒストリー研究」といえども、通常の授業では、ここまでの展開はない。にもかかわらず、たとえばつぎのような、提出レポートの中の「おわりに」という文章から察すると、受講生は、「ライフヒストリー研究」という授業をとおして、「一人一人違う人生を歩んでいる」という世界観とともに、「毎日ちゃんと生きなくちゃ」という前向きな人生観を獲得しているらしいことが、やや手前味噌ではあるが、窺えよう。
この授業を受けて思うこと。世界にはたくさんの人がいて、一人一人考えが違い、一人一人違う
人生を歩んでいる。現在だけでなく、過去にも、そして未来も……。そうやって考えると、
私は、変な気持ちになる。毎日ちゃんと生きなくちゃ、とも思う。なぜか、人に優しくしなくちゃ、とも思う。
そうやって考えさせる授業は、初めてだ。こんな重い授業だったっけ(笑)⑼。
注
(1)1989年のある授業の中で、当時中京大学の教授であった中野卓は、「働きかけ合い」について、つぎのように述べている。
その人との生活の絡み合いの中で、その人が自分の生活とどういうふうに関係したか、その人から
どういう影響を受けたか、その人にどういう影響を与えたか、というふうな、お互いの相互作用、
働きかけ合いというものが、その人の歴史を作ってきた、そういう話が自然と出てくる。
個人と個人との間の出会い、そして影響の与え合い、そういう共同生活、あるいは協力生活。
(田口純一編『こころの運動会』、北樹出版、1994:239)
ライフヒストリー研究については、通常、「相互作用」といったやや淡白で、物理的な定義で終わらせていることが多いが、これだけ簡潔で、しかも要をえた説明は、ほかにないだろう。それは、「働きかけ合い」や「影響の与え合い」といった、人間の営みへの、あたたかい、かつ、するどいまなざしを表現しているともいえる。
(2)塚田守「「決定的瞬間」についての語りの考察」『言語と表現 第7号』、椙山女学園大学国際コミュニケーション学部紀要、2010:24。
(3)武川まり・杉浦那津美「触るじゃん! やっぱり。」、横家純一編『バナナパフェ―椙大生活史研究 第3号』、2008:38。
(4)有末賢は、生活史研究が主題的に興味をもたれた場合、「「こんな人間もいる」というようなユニークで、珍しい体験や生き方や「語り」を収集し、それを味わい、楽しむという「読み方」」が行われるとしている。『生活史宣言』、慶應義塾大学出版会、2012:4。
(5)鈴木とも子「空とぶ障害児教育」、横家純一編『ミラクル・ハンター―椙大生活史研究 第1号』、2002:69。
(6)桜井厚『ライフストーリー論』、弘文堂、2012:168。
(7)「テーマ」について、中野卓はつぎのように言っている。
ライフ・ヒストリーは私達が調査を通じて、ライフ・ストーリーとして聞くわけです。相手は自分の
生活の、生涯の、あるいは半生の物語として、お話をしてくれるのです。初めがあって終わりがある。
それから、強調している点がある。何かの点を強調している。生活史にはテーマがある。私の生涯の
中でこういうことが大切だったと思う。こういうことだけはあなたに話しておきたいんだ。このことは
どうしてもわかって欲しいんだ。あるいは、そのとき私はこういうふうに考えたんですよ……というふうな、
その人が重要だと思っていることを、強調しながら話してくれることです。
それは、主観的な話です。その人が現在そう思っているという話。ですから、人にたいする誤解も
あるかもわからないし、人にたいする愛情をこめて、美化して話すかもわからない。
それでも構いません。その人が自分の人生をどう考えているかを、知りたいのですから。
田口純一前掲書(1994:240-241)
この時点(1994年)で、「ライフ・ストーリー」と発言していることもさることながら、われわれの人生にはテーマがある、と宣言することで、人の命の活動を高らかに謳いあげているようでもある。
(8)たとえば、口述と記述のあいだにひそむ緊張関係を考察したケースとして、田口純一「自己検閲の論理と心情」(『解放社会学研究、第6号』、1992:113-124)がある。そこでは、いったん口述された個人の生活史が、編集者によって記述されるプロセスにおいて、語り手自身により“検閲”をうけるケース――小さなものでは、単純な思い違いや表現上のミス、大きなものでは、民族差別表現とか体制批判の言説――の検討がなされている。
(9)森美穂「ボケボケするな!」、横家純一編『至福のとき―椙大生活史研究 第2号』、2007:127-128。
森美穂が、「重い授業だったっけ(笑)」という名言を残してくれたのが、2006年。それから5年後、つぎのような受講生に出会えたことを、ここに付記しておきたい。
この人は、自分の卒論のデータとして、8万字をこえる「自分史的エッセイ」(その約4分の3が、こんかいの「就活戦士ハルカ」(第一期)、「ハルカ第2章―オーラ奪回作戦―」(第二期)として結実している)をしたため、そのノリで、卒業後、自発的に語り手をさがし、インタビュー取材(第三期の「見えてきた自分の役割」と「見えてきた自分の挑戦」として結実している)を試みたのである。やや例外的ではあるが、人の人生をきくことと、自分の人生をふりかえることが、一つの人生の表裏一体の関係であることを、われわれに教えてくれる、貴重なケースといえよう。
はじめに
この章では、「自分史的エッセイ」の教育実践のまとめと、物語としての「自分史的エッセイ」の社会学的分析の可能性について書いている。
第1節では「自分史的エッセイ」を授業の課題としている「ライフヒストリー研究A」(半期科目)は何を目的として授業がなされているのか。また、実際にどのように授業が運営され、学生がどのように参加しているのか。物語としての「自分史的エッセイ」を書くプロセスはどのようなものであったか。授業という場でそのようなエッセイを書くことの効用と満足とは何か。さらに、「ライフストーリー文庫~きのうの私~」との関わりに触れ、ライフストーリー(自分史的エッセイ)を用いた授業の可能性について考えている。
第2節では、「ライフストーリー文庫」に掲載されている、学校教育の過程で「偏差値」にこだわって生きた二人の学生の「自分史的エッセイ」を事例として取り上げ、物語としての「自分史的エッセイ」を独立したテキストとして提示した上で、社会学的分析を試みている。また、物語として、テキストとして「自分史的エッセイ」を読み解くことで、共通のテーマとは何かを考察し、テーマを一つに限定し、さまざまなデータを使う横断的な社会学的分析とは異なった分析を試みる。具体的には、二人の学校体験を自分史という時間軸を考慮し、その時間軸が学校文化とダイナミックに交差する中で起こる、「自己変革」のストーリーの社会学的分析の可能性を考えてみたい。
1. エッセイを書く授業の実践
(1) 「ライフヒストリー研究A」という授業の内容と目的
「ライフヒストリー研究A」は、『私たちの中にある物語』にある、個人史の書き方を学び、今までの自分の人生でもっとも意味あると思われる体験について「自分史的エッセイ」を書くことを通して、「いままで語ることのなかった事」を語ることで、「今までの自分」とは異なる「新しい自分」へ変わる一つのきっかけを作ることを目的としている。
自分の体験を書き、語ることには変革的機能があるということを前提にし、この授業を通して、受講者の「自己変革」が起こることを期待し、「ライフヒストリー研究A」のシラバスには以下のように書いた。
この授業では、ライフヒストリーの社会学の視点から、人の人生における転機に焦点を当て、
人の生き方とはどのようなものかを考察する。授業の前半では、ロバート・アトキンソンの
『私たちの中にある物語』について講義し、人びとがストーリーを語る意味を理論的に整理し、
その理論を理解した上で、自分的エッセイをどのように書くかについての実践的方法を学ぶ。
後半では、同世代の自分史的エッセイを読み、解説し、身近な自分史的エッセイをどのように
書くかについて講義する。最後には、受講生たちの書いたエッセイを授業で読み、相互にコメントを
しながら、それぞれの人生を考え、自己理解を深める。
授業の方法としては、相互に議論をする参加型をめざすものである。受講生たちは、事前学習として、前半では、『私たちの中にある物語』の該当する章と配布された自分史的エッセイを読んで授業に臨むことが期待されている。また、授業を履修している学生は、学生自身が書いたエッセイを授業時間中に全員で読み、コメントあるいは感想を言うことも期待されている。
この授業では、前半では、該当の章と配布された自分史的エッセイに関するリアクションペーパーを提出し、後半では、自分が書いたエッセイの草案を随時、担当教員に提出することになっている。よって、すべての受講生は、「自分に関わるテーマでエッセイを書くことが必修課題となるので、書きたいテーマをもって履修すること」という条件で、履修することになっているので、履修する学生は、すでに「語りたい、書きたい物語」が曖昧な形であれ、自分の中にある学生だと言える。授業で「自分的エッセイ」を書くことが必須だとわかった段階で、授業の履修を取り消す学生は2~3人いる。しかし、履修した学生は、自分が書いたエッセイが読まれることを前提にし、書き、担当教員に提出して初めてこの授業の単位が与えられるので、全員が「自分史的エッセイ」を書くことになる。
(2) 学生の中にも「語る物語」はある
一般的に自分の個人的な経験をあえて話したいとは思わないと理解されているが、どんな人、どのような年齢であっても「語りたい物語」を心の中にもっているということを前提にこの授業を始めている。
アトキンソンが言っているように、「ほとんどの人はたいていの場合、自分の話を聞いてくれる人、自分の話に興味を示してくれる人を必要としているので、そのような機会があれば、自らの自伝を喜んで語るであろう」(2006:172)。たとえ、それが1970年代の極左翼連合赤軍のメンバーやテリアビブで集団銃殺テロ事件の犯罪者であろうと、「判断されず自分の話を聞いてくれる人がいれば、かかわった事件に関する物語を話すものである」と言ったのは、戦前の転向問題を研究し、1970年以降は、連合赤軍メンバーのインタビュー調査を、それぞれの囚人の拘置所で何度もインタビューをしたスタインホフ教授である(1986年)。また、筆者が15年以上続けている教師のライフストーリー研究で、「あまり話すことはない。私よりもっと適任な人に話を聞いた方がよい」と言っていた先生たちが、自分の若い頃の教師体験、今の自分の教育哲学、価値観などを、インタビュアである筆者に長時間語ってくれた(1998、1991)。それは、アメリカ人の教師も同じであった。インタビューの最初は、日本から来た身知らぬ研究者にアメリカの教育について教えてやろうという話ぶりで話していたが、その内、自分が生きてきた社会、個人史などを語り始め、その人の人生の中のもっとも「意味ある体験」を筆者は聞くことができた。その中には、長い間自分の中で封印していた学生時代の「公民権運動への関わり」に関する語りもあった。それらは、聞かれなければ語られない物語であった(2008:82-84)。
そして、自らの人生の「意味ある体験」を語り終わった後、多くのインタビュー対象者は、自らの「人生の語り」をインタビュアである筆者に語ったことに満足した、という発言をした。曰く、ヒスパニック系のある教師は3時間ほどのインタビューを終えた後、「こんなインタビューだったら何回でも受けるから、いつでも声をかけてください」と言ってくれた(2008:324)。あるいは、自分の経験を話し、自分の人生をふり返ることができ、インタビューをもとに書かれた「自分史」を娘や息子に読んでもらうことができて良かったと、自らの「ライフヒストリーを語る」意味を積極的に評価してくれた教師がいた(1998:483-384)。聞かれて初めて話し、そのように話したことで、自らが言葉にしてこなかったことを語るプロセスを通して、一つのまとまった「人生の物語」を語ることができたことに満足することができたと言ってくれた、インタビュー調査の中で出会った教師たち。彼らも「語る物語」をもっていたのである。
しかし、ある程度長い間生き、さまざまな経験をもった教師たちとは異なる、20年前後しか生きていない学生たちには、「語る物語」はないのでは、と思う人も多くいるであろう。実際は、年齢に関係なく、今生きている私たちは、それぞれの成長段階で、「語る物語」をもっていることは、「ライフヒストリー研究」「人間論」を履修した学生によって書かれた「自分史的エッセイ」あるいは、創作的「卒業研究」として書かれた自分史を読んだ経験から言える。いじめ体験、いじめられ体験、学校教育での葛藤、家族のこと、友達のこと、非行体験、性同一性経験、親の死などについて書かれたものを筆者は読んできている。20年間生きてきたにすぎない学生たちの中にも、多様な「人生の物語」があった。もちろん、年齢層が上の世代で経験されるほどの多様なものではないが、筆者が社会学研究の知見から理解していた家族問題、学校問題などとは異なったレベルの、生き生きとした物語が「自分史的エッセイ」として書かれていた。
「学生たちにも語る物語ある」という前提で、その物語を聞く、読む機会としてこの授業を展開している。一般的には、自分史は本人が書きたいと思い、何らかの動機があって書き、何らかの手段(自費出版、自分史サークル、自分史の文化講座で作られる冊子、ブログ、ホームページなど)で、自主的に書くことはありうるが、授業の中で課題として出された「自分史的エッセイ」を、学生がどれだけ本気に書くのかという疑問があるかもしれない。しかし、実際に授業をやってみると、自らの人生上の意味ある体験について考え、熱心に書いたレポートを読むことができている。そして、筆者には、それらの書かれた「自分史的エッセイ」は単なる課題以上のものだと思えた。そのような授業の経験から、学生たちにも「語る物語」をもっていると確信するに至った。そして、そのことは既に、この報告書の第1章でくわしく描写したように、実際、アトキンソンも大学院の授業でやっていたことを、後で知ることになった。アトキンソンが著書の中で議論を展開しているように、だれの心の中にも「語る物語」をもっているという前提で、この授業も展開してきている。
(3) 授業の実践の内容―授業の段階的展開
半期の授業で、実際にどのような流れで行われているかについて具体的に描写する。
第1段階: 物語を書く、語る意味についての講義と話し合い
まず第1段階である最初の数回の授業は、「物語を書く、語ること」の意味と機能について、教科書として用いているアトキンソンの議論を読むことを課題として与え、その章の内容に解説を加えながら、「物語を書く、語ること」は、自己理解、人生への意味付与、人生の体験の再解釈などの機能をもち、最終的には、書くことで「自己変革」が生まれる可能性があるということを、理論レベルで説明する。また、書くことが「自己変革」につながったと思われる例を、担当者である筆者が解説も行う。受講生は、自分自身の語る物語をもって授業を履修していることが前提であるが、「物語として書く意味」の重要性を授業の中で強調することで、書く意欲の動機付けしている。その授業形式は講義ではなく、課題として読んできたものについて話し合うという、参加型の授業で行われている。
第2段階: どんなものを書くかのイメージづくり
授業を受講した学生が書いた「自分史的エッセイ」をサンプルとして配布し、その内容について議論することで、どのようなものを書くべきかのイメージ形成を促す作業を行う。「物語を書く意味」を理論的に解説するだけでは、受講生たちを十分に動機づけることは難しいので、具体的に先輩たちが書いた「自分史的エッセイ」を呈示する。「ライフストーリー文庫~きのうの私~」のウェブに掲載されている「自分史的エッセイ」あるいは、担当教員が以前に編集した『私たちの告白~9人のライフヒストリー』などから、2~3のエッセイを「書かれた物語」のサンプルとして配布し、その内容についてディスカッションする形式で授業を行っている。学生たちにとっては、書きたいと思っている自分の中にある「物語」を、どのように文章として書くことができるのかが解決されるべき課題としてあり、何を書きたいか、どこまで書くべきかについても曖昧なまま授業に参加している学生が多ので、いくつかのサンプルを読むことにより、先輩たちはどこまで書き、どのような物語を書いているのかを具体的に理解し、「自分史的エッセイを書く」ということのイメージを形成していく。
第3段階: 自分史的エッセイの書き方について
具体的な自分史的エッセイの書き方についての解説的講義を行う。『私たちの中にある物語―人生のストーリーを書く意義と方法』の第4章「自分にストーリーを与えよ―自伝的に書く」の章の具体的なサンプルと「書くためのガイドライン」を中心に読み、解説的な講義を行う。そこで述べられているキーワード「自分のために書くこと」「内なる声に耳を傾ける」「記憶を呼び起こし、掘り起こすこと」などを強調し、「話すように書くこと」について解説し、この「自分史的エッセイ」は基本的に他人のため、他人に自分を顕示するために、あるいは、他人に評価されるために書くのではなく、自分のために書き、自分理解や自己変革を目的として書くということを強調して説明する。そして、学生がそれまでに書いてきた「作文」や「小論文」のとの違いを明確にする。小学校から高校までの文章は、それぞれの段階での教師の評価を意識して書かれるので、自分の気持ちや考えを表現するのではなく、むしろ、自分の気持ちを抑え、期待されていることを書き、良い評価を得ることを目的としていたと講義した上で、それとは対照的に、「自分史的エッセイ」は他人の評価を気にすることなく、文章としての上手さや日本語としての表現の良さなど気にせずに、「話すように書くこと」で、自由に自分の経験、気持ちを表現してよい、ということを強調している。そしてあくまでも、「今も自分がこだわっている」「自分にとって意味あった」と思える体験、出来事について書けばよい、とも説明する。その意味では、どんな些細なことでも本人が重要であると思えることこそ、書くに値するのだということも強調している。
第4段階: エッセイを書く段階
書く枚数を規定して、最初の草案の締切りを6月中旬までとして、授業が終わる1か月以上前までに「自分史的エッセイ」の締切りを設け、草稿としてA4判で3頁程度を書くようにと指示する。この段階で、「宿題」となった課題の提出が近づく段階では、「書けない」という声が聞こえることが多くなる。「書きたいことがある」受講生であるにもかかわらず、書きだそうとした時に、書けないという現実にぶつかることが多いのである。そこで、担当教員としては、何枚でも良いので、書けるだけ書くことを基本として、「締切り厳守」を再確認する。そして、締切りに間に合ったものから受け取り、それを授業で読むという現実的な対応をしている。受講生のなかで、他でもエッセイ・ライティングなどの授業を履修した学生がまず書いて、提出する場合が多い。そして、エッセイを書いた受講生に書いた時の感想を言ってもらい、書くことの難しさと楽しさを、その学生自身の言葉で語ってもらう。受講生は五月雨式にエッセイを提出することになるが、その都度、書いた時の心境を他の学生に伝えてもらうことにしている。そして、共通して言えることは、「いったん書き始めると、止まらない」ということが受講生に共有されることになり、書き始めさえすれば、どんどん書けると確信し書き始め、ほとんどの受講生が第1草稿を1~2週間のうちに提出することになる。
これは、いったん書きだしたら、どんどん書いてしまうという「人生の物語」を書く行為のもつ特徴だと言える。いったん書き始めたら、一つの心の扉を開けることになる。あるいは、いままでとは違う理解に達することができた結果、と言えるかもしれない。
大学教育でのレポートの提出は、成績を付ける最後に設定している場合がほとんどであるが、この授業の場合、最終レポートに対して成績を付ける点においては通常と変わりはないが、第1草案を6月中旬に提出させて、それを授業の中で、全員で読み、そのエッセイに対して、出席者全員からコメントや質問を受けるという方式をとり、受講生間での意見交換や質疑応答を通して、エッセイを書いた学生が、第1草稿を推敲し、書き直せるようにしている。
第5段階: 読まれたエッセイを相互にコメントする段階
個人的なこと、今までだれにも言ったことのない「人生の体験」について書いて、それが読まれるということの心理的プレッシャーは、たとえ授業という限られた空間でも20歳前後の女性にとっては、大きなものである。いままで語り得なかったことを初めて書いて、他人に書いたことを授業で発表し、それを共有する形でコメントをお互いに交換することは困難なことである。そこで、提出された第1草稿で、担当教員が読ませたい、プライバシー保護の点から読んでも良いと判断し、本人がクラスで読まれてもよいと同意したものを、名前などを消して匿名にして(本人が同意すれば、実名で)、全員がコメントをするという方式をとる。そして、本人がコメントする時に、何らかの「不自然な行動」をとる場合、そのエッセイを書いた執筆者だとわかることになるが、基本的には、だれが筆者であるかを追求しない前提で授業を進めている。
コメントする時も、いくつかのルールを設けている。まず、評価的なコメント、書かれた内容が良いか悪か価値判断するコメントを禁止している。次に、書かれたエッセイの理解しがたいこと、不明な点、もっと説明がほしい点などを中心に質問するという形式のコメントをする。第3に、反発を感じる点ではなく、共感する点だけに限定してコメントをする。クラスの中に書いた本人がいることが前提なので、エッセイの執筆者にとって、ポジティブで意味あるコメントだけをいうことを基本的なルールとしている。最後に、この授業で話されたことは、基本として、他の人に「うわさ」として話さないこととしている。授業の最終課題として、授業に参加していた受講生からいろいろなコメントを加味した上で、担当の教員が最終的なコメントを文書で書き、執筆者はそれを参考にして、そのエッセイを深めて、修正された最終草稿を提出することになっている。
授業を以上のような5段階で行いながら、受講生たちは、「自分史的エッセイ」を書き、自らの人生の意味ある体験、今のこだわっている出来事などをエッセイとして「語る」ことで、自己理解、それぞれの体験や出来事の再解釈を行うことが期待されている。時には、書くことを通して、「自己変革」が起こる場合もある。
(4) 2012年度の授業実践から考える物語としての「自分史的エッセイ」のもつパワー
この9年間、匿名にして読むという方式で行ってきたが、2012年の授業で初めて、一人以外は、実名でエッセイを発表し、読み合うという参加型の授業が行われた。そのようになった主な要因は、受講生9名という少人数であったと推測される。また、4年生が4名、3年生3名、2年生2名と、上級生が多かったことも要因になっていたかもしれない。授業の第3段階が終わり、第4段階に移行する時、「人数が少ないので、それぞれの提出されたエッセイをオープンにして、実名で発表するのはどうですか」と提案をしてみたところ、一人以外は賛成した。その一人の学生が書いている内容を考えると、確かに、プライバシー保護の点から本人が拒否する理由が推測できたので、その学生を例外として、他の8名に関しては、書かれた草稿を全員で読むということを決定した。
人数が少数だということもあり、ゼミでよく行われているように、エッセイを読む第5段目からは、お互いの顔が見えるように円座で座ることも、みんなの同意のもと行われた。その頃から、1回の授業で平均、二人分のエッセイを授業で読むことができた。誰が書いたか明らかにされていたので、通常の授業よりも、コメントや質問が活発に行われたような印象が残っている。ゼミ形式の参加型で行われたので、お互いの信頼関係ができたことがその要因であったのかもしれない。
文章を読み、コメントをお互いに言う中で、それぞれの「自分史的エッセイ」に書かれたテーマの共通性に対して、共感が表現されるコメントが2012年度の授業では特に多かった。次の節で社会学的分析の対象としている「今までお嫁さんになるために勉強してきたの?」の執筆者Aさんは、授業中にサンプルとして全員で読んだBさんの「女子高文化―キラキラした彼女たちの中で」のコメントをしている最中に、「自分も受験で苦しんだ経験があるので、つい、共感してしまった」と声を詰まらし、突然、涙を流し、自らの受験の体験を話し始めた。AさんはBさんと同じように、「偏差値」を気にして生きた高校時代を経験したことを思い出し、その当時の「受験勉強の苦しさ」を思い出し、泣いてしまったようだ。Aさんの泣きながらのコメントについて、同じように受験で苦しんだという他の受講生からのコメントが続き、日本の高校受験、大学受験をテーマにディスカッションが展開される授業になった。次の節で、この2つの受験に関わるエッセイを物語として読み、その社会学的分析の可能性について論じるが、身近な先輩Bさんの物語をAさんが読むことで、共感し、過去の受験時代の私をふり返り、Aさんもまた、その苦しかった高校時代をテーマとして「自分史的エッセイ」を書くことになった。
これは、たまたま起こった一つの例に過ぎないこと、ではなかった。他にも同じようなことが起こった。匿名の書き手が書いた「もう『元ヤン』と呼ばないで」に対して、授業中一人ずつコメントした時のことであった。この「自分史的エッセイ」の内容は、父親と母親の仲が悪く、経済的な問題も関係し、家族が崩壊状態の中、書き手自身は、「ヤンキー」と呼ばれ、喧嘩を繰り返し、非行に走っていたが、おじいちゃんの支えのもと、頼りにしてくる弟を守るために、「ヤンキー」を止め、生まれて初めて勉強して、その後、今の大学に入学したというものであった。家族崩壊に面と向かうようになってから変わったという「自己変革」の物語であった。「ヤンキー」と呼ばれた中学時代と、その当時の家族崩壊の実態が具体的で鮮明なタッチで書かれた物語。その経験について「自分史的エッセイ」が書けるほどの精神状態になっている点で、執筆者Cさんの「今の自分」にとって意味ある体験としてあり、その時の苦しさや大変さは、過去の出来事になっている。
しかし、Cさんが描いた家族崩壊についてのエッセイについて受講生Dさんがコメントしようとした時、Dさんは家族崩壊のまさに渦中にいた。葛藤していた日々の中で、まさに今の自分の家族の状況を描き出しているエッセイを読み、共感し、「自分の事」「自分の問題」として考えてしまったのである。「今の自分の家族崩壊」を見るようで、その苦しい思いで精神が高ぶり、一言も言えず、泣いてしまった。Cさんの意味ある過去の物語がDさんに直接語りかけ、Dさんがいままさに自らに起こっている「家族崩壊」と直面することになった。その段階まで、エッセイの課題を提出していなかったDさんは、翌週には、今進行しつつある家族崩壊の現状を報告するエッセイを書いて提出してきた。そのエッセイは、物語としてまとまったストーリーになっていない、現状報告のようなものであったが、Dさんが、Cさんの物語を読み、みずから見ようとせず、逃げていた現実について書く作業を通して、直面しようとしたものであったと思われる。その半年後、Dさんは、授業で書き始めた「自分史的エッセイ」をさらに展開させ、それを名古屋市が募集するエッセイコンテストに応募し、そのエッセイは一つの賞を与えられた。見たくなくて、避けていた家族崩壊の現実をエッセイとして物語化することによって、ある程度の「解決」をした例と言えるかもしれない。
以上、AさんがBさんのエッセイを読み、涙を流し、自分がこだわっていた苦しい高校時代について書いたこと、また、DさんがCさんの家族崩壊の物語を読み、当時起こっていた自らの家族崩壊に直面し、そのことをエッセイとして書いたことは、一つの物語が、同じような体験をもった読者に直接的に働きかけ、影響した例と言えるであろう。影響を受けたAさん、Dさんは、自分の中にある「今まで話せなかった体験」を物語化することで、その共感する思いを表現し、その渦中にいた自分とその後の自分の理解をしながら、「自己変革」を経験していったのではないだろうか。この二人のケースを考えると、他人の「人生の物語」「意味ある体験」は単なる他人事として読まれるのではなく、自分自身の物語のように自分に語り掛けてきたと言えるのではないであろうか。因果関係的説明をする社会科学的説明様式を超えた、物語形式のもつパワーをここにみることができたように思える。
「ライフストーリー文庫」に掲載されている「私の物語」は、教室のまさに隣にいる学生の声を「物語」として表現している。そこには計算され、作られた作品のような完成度はないが、学生自身の「生の声」のもつパワーがあると言える。そこには技巧が施された美しい表現はないかもしれない。流れるように書かれた文章ではないかもしれない。しかし、まさに未完成であるが故に、隣にいる学生たちの「ふつう」の感覚に直接的に響くのではないか。「自分と似ている人」「自分と同じ体験をもった人」として共感が得られた時、人は自分の経験していることは、自分だけではないと思い、癒され救われることがある。問題を抱えた家族、問題の渦中にいる人びとの「ふつう」の話を読むことで、元気づけられる。その意味では、すべての人が自分の中に「語る物語がある」とアトキンソンが言っていることが、今筆者が描写した授業実践の一コマからも言えることである。
(5) テーマシリーズ「就職活動」の物語―分析よりも物語が共感を生む
本研究を進めていくプロセスで、大学生の就職活動に関する聞き取りや「自分史的エッセイ」を読み、いまの女子大生が直面する問題を「物語」として理解する試みを行った。その一部は、「ライフストーリー文庫~きのうの私~」に掲載しているが、まだ、未完のままで終わっている。未完ではあるが、それまでに至るプロセスを描写し、伝統的な社会学的説明にはない、「物語」がもつ「共感パワー」について論じたい。
2011年度のゼミ生の就職活動を支援しながら、学生たちが抱える就職活動の特徴を描写し、後輩の学生たちに役立てたいと考え、ゼミ生20名全員の就職活動の物語を『就職活動のさまざまなストーリー―20人の女子大学のキャンパスライフと就職活動―』(未刊行)としてまとめた。学生一人ひとりに「就職活動メモ」や「私の就職活動エッセイ」として書いてもらったもの、ゼミ担当者の筆者が、就職活動を支援し、就職のための履歴書やエントリーシートの書き方を指導するなかで、聞いた学生たちの語り、さらに、学生たちの就職活動に関する筆者によるフィールドノート、この3点を組み合わせて、それぞれの就職活動のストーリーを書いた。
その書き方は、社会学研究をしている筆者の分析的解釈を加え、就職活動に関するアドバイスなどを含むものであった。『就職活動のさまざまなストーリー』を就職活動を始めたばかりの学生に読んでもらったところ、学生の体験を分析した「社会学的解釈」などは、学生にはまったく興味がもてないものであった。学生たちは先輩たちがどう活動したか、その経験に関する「生の声」にもっとも興味を示し、その他の部分は飛ばし読みをしたようであった。
そして、読んだ学生の多くにとっては、20人の中で最も能力があり、自分の強い意志をもって就職先を決め、第1志望の企業に内定を受けた「成功物語」がもっとも不評であった。曰く、「あの物語を読んで、嫌になった」「私とは別の世界に住む人間だ」「私はあの先輩ほど能力はあるわけではないので、関係ないです」ということであった。つまり、自分とはあまりにも異なる世界にいる人の声など、あまりにもかけ離れていて、興味をもつことはなかったのである。学生たちが好んで読んだストーリーは、就職活動の中で葛藤し、苦しんだというストーリーであり、その苦しみや葛藤を共有することで、その物語に共感し、「自分もがんばろうと思えた」というコメントをした学生が何人かいた。これは、アトキンソンの「最良のストーリーは誰かが他の人の苦しみについて私たちに語っているものである。そのような他人の苦しみのストーリーは私たち自身の苦しみを耐え抜くための強力な治療方法になりうるのである」(2006:206)でも言われている通りである。
今就職活動をしている学生たちの就職活動に関する本の読み方を理解した上で、就職活動している学生の「生の声」、あるいは一人称で書かれた物語の方が、社会学的解釈を含んだストーリーより、物語としてインパクトが大きいと思い、『就職活動のさまざまなストーリー』の中の筆者が行った社会学的解釈を全て取り除き、9人の「私の就職物語」を入れたものを『就活女子』(未刊行)として、編集し直し、まとめた。そこには、9人の学生が就職活動のさまざまな局面で、苦労しながら葛藤した一人称によるストーリーが書かれている。社会学的分析を含まない「私の就職物語」である『就活女子』を読んだ学生は、物語として書かれている、詳細で具体的な内容に共感し、読書後は、「就職活動で悩んでいたけれど、この本を読んで、がんばってみたいと思った」という感想を述べ、その時まで就職活動を避け、考えないようにしていたが、具体的に就職活動をし始めた、という。一人称で書かれた物語が読者に共感を生み、元気にさせるパワーをもっているのではないかと言える。
とするならば、読者の共感をえるためには、一人称で書かれた物語を呈示することがもっとも効果的であると言える。そのことを理解した上で、本研究は、一人称で書かれたストーリーである、さまざまな「語られたストーリー」や「自分史的エッセイ」をホームページにアーカイヴ化し、広く人びとに公開し、社会に発信し、多くの人に利用してもらい、利用した人が自らの体験と似た体験についてのストーリーを読み、自らの人生をふり返り、その人生をより深く理解し、意味付与することで人生上の体験や出来事を再解釈する機会をもつことを期待しているものである。本研究はまた、ストーリーをアーカイヴ化し人びとに発信するだけでなく、ストーリーの社会学的研究を促進することも目的としている。では、物語のもつパワーを失わせない、社会学的分析は可能なのだろうか。次の節で、ストーリーの社会学的研究の試論を行う。
2. ストーリーの社会学的研究の可能性―ストーリーと社会学的分析の関係性―
山口(2004:11-13)は、ブレナーの2つの思考様式についての議論を簡潔にまとめている。ブレナーによれば、思考には2つの様式、つまり論理科学的思考モードと物語的思考モードがあり、両者は経験を秩序立て、現実を構築する異なる思考様式であり、お互いに補完的であるが、片方を片方に還元することはできない。論理科学的モードは科学的パラダイムであり、「真か偽か」という問いかけによって答えが導かれるが、物語的思考モードは2つ以上の出来事がどのように関係づけ陳述されるかが問われるとしている。普通の人が普通にやっていることを知りたいならば、物語的思考モードによる心理学が必要であると言っている。
本研究の中心的テーマは、ストーリーのもつパワーを理解した上で、ストーリーの社会学の可能性を考えることである。ストーリーとしての「自分史的エッセイ」を中心に論じ、ストーリー、あるいは物語を呈示することで生まれるパワーが、同じような状況にいる人が自分のおかれている状況を理解する助けになると述べてきた。その意味で、「ライフストーリー文庫~きのうの私~」の創設は、ストーリーをウェブ上にアーカイヴ化し、普通の人のストーリーを普通の人に多く提供することで、似た状況にいる人に対して、共感と理解を深める機会を提供することをめざしている。より多様なストーリーをより多くアーカイヴ化することで、より多くの人びとの自己理解、他者との共感を得る可能性がある。
アトキンソンが言うように、ストーリーを書く、語ることによって、私たちは、主観的リアリティを追求している。「自分史的エッセイ」「語られたストーリー」は、書き手、語り手自身の真実である。彼らは私たちに、書きたいストーリー、語りたいストーリーのみを提供している。私たちは、彼らが真実としていることしか読むことはできない。それは、書き手あるいは語り手の主観的リアリティの世界である。自分史的エッセイを書くことは、自分の経験を反省的にとらえ、それに意味付与し、それをストーリー化することである。ストーリーを分析的に考えるなら、そのストーリーを、語り手あるいは書き手が、「生きられた生」について私たちに語りたい何かをもつテキスト(text)として受け入れなければならない。ストーリーの多くは、彼ら自身にとってもっとも重要なことを話す(書く)ので、共有される「神聖なる瞬間」であることが多い。それを解釈するために3つの重要なポイントがある。
第1に、そのストーリーを評価するのではなく、そのストーリーそのもののもつ意味を追求すること。第2に、ライフストーリーはほかの分野でのドキュメントと同じように、テキスト(text)である。それ自体で存在していて、小説や詩と同じようなもので、読者の考え方に基づいて、ある一定の反応を生み出すものである。第3に、私たちは、お互いにとって教師である。小説や詩のように、ライフストーリーも私たちに人生について言う何かをもっている。私たちは私たちが聞いた、あるいは読んだストーリーから何かを学ぶことがある(アトキンソン2013:19-21)。
だから、ストーリーに解釈を入れて分析するのではなく、ストーリーそのものを示すことがこのセンターの目的であるし、この研究の目的であった。しかし、それとは独立した社会学的分析の展開も可能であると考え、ライフストーリーの社会学的分析の可能性について考えてみたい。
まず、テキストそのものを読みながら、論理科学的思考モードとしての社会学的解釈を付け加え、書き手の主観的リアリティついての論理的整理としての社会学的分析を試みる。具体的な方法としては、「ライフストーリー文庫~きのうの私~」に掲載している、2つの事例を取り上げ、それぞれの文章の中の「書き手の主観的な語り」に下線を引き、その下線部に対する社会学的分析のコメントを時間軸にそって付けくわえることで、「書き手」の「自己変革」のプロセスを説明的に描写し、「書き手」の主観的リアリティに焦点をあてるライフストーリーの社会学的分析の試論を行う。また、この2つのエッセイを分析した後、その2つを比較し、同世代を生きている女性に共有された「主観的リアリティ」とは何かを考え、現代の日本社会の学校教育の問題を、それを経験した本人の視点と時間軸という2つの要素で分析することで、数量的社会学の枠組みで展開されている制度的、統計的分析とは異なった、ストーリーの社会学的分析が可能ではないかと考えている。
(1) 事例1:「女子高文化―キラキラした彼女たちの中で」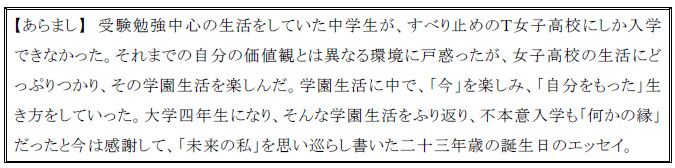 中学は勉強だけだった
中学は勉強だけだった
私は中学一年生から本当に優等生。とーっても真面目な生徒だった。定期テストの点数はいつも学年十位以内。学年一番をとったこともある。通知表は、一年生の時から全ての科目オール5。4をとったのは三年生に体育で2回だけ。部活も部長とペアでテニス部。すごーく真面目に練習していた。部活の後は週に2回の塾。塾は中学一年生の頃から三年間、卒業まで通い続けた。帰ってきたら宿題して、テレビ見て、寝る。特別な趣味もなければ特技もなかった。
でも、この生活が普通だった。その時はこれで充実していると思っていた。みんなから「頭が良くて羨ましい」と言われたけど、それだけの勉強をしていたから点数とれるのは当たり前だ。人より勉強したら人より点数はとれるものだ。定期テストってそういうもの、そう思っていた。だから、テスト前は毎日塾に通っていたし、土日も塾で朝から夜まで勉強していた。朝九時から夜九時までとか。そんなテスト勉強が普通だった。
こんなにしなくても点数がとれる人もいるのかもしれないが、私にはそれだけの時間が必要だった。それだけの量をこなしていた。テストの結果が出て自分より点数が高い人がいたら、「私の今回のテスト勉強は足りなかったんだ」って、「もっと勉強しとけば良かった」っていつも思っていた。「次はもっと準備しないと」って。別に無理をしていたわけじゃなかった。この私が私だった。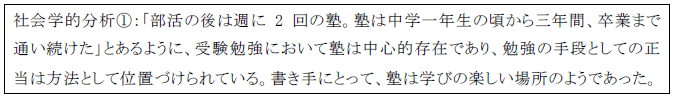 テストの点数がよかったから、成績がオール5だったからって親からお小遣いがもらえたわけでもないし、ご褒美に何か買ってもらったことだって一度もない。結果を見せると決まって他人事のように言われた。
テストの点数がよかったから、成績がオール5だったからって親からお小遣いがもらえたわけでもないし、ご褒美に何か買ってもらったことだって一度もない。結果を見せると決まって他人事のように言われた。
「毎回、毎回よくやるねえ、お母さんにはできないわ〜」。とりあえず、これが母のいつもの感想だった。「次はもっと頑張りなさいよ」なんて言われたことがない。父からは特に褒められたこともないし、「勉強しなさい」なんて言われたことも、もちろんない。両親にとっても、この私がいつもの私だった。私は私のために勉強していた。学期末、学年末、良い成績を残すために、定期テストで高い点数をとる。美術や音楽なんかも普通に頑張ってたいら、いつも良い成績がもらえた。
「良い成績があれば、偏差値の高い高校に行ける。偏差値の高い高校に行けたら、良い大学に行ける。良い大学に行けば、就職は大丈夫」
今思うと、とてーも甘ーい考え方をしていた。周りから見るととっても優等生な中学生。これが私だった。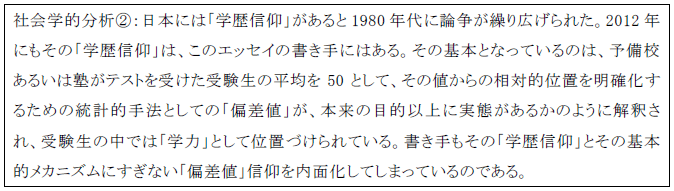
高校入試に向けて
中学三年生にもなると、学校でも塾でも受験についての話題が自然と増えた。
「あの高校の制服可愛い」
「あっちの高校の校則は緩いらしい」
「学園祭が楽しそう」
「早く決めたいから推薦が欲しいなー」
それまで偏差値の高い高校に入るためにあれだけ勉強してきていたのだから、私にとっては待ちに待っていましたという話題のはずだった。でも、何故か私は全く高校に進学するということに関して興味がもてなかった。 「高校生の私」なんて、その時は全くイメージができなかった。皆盛り上がっているけど、私はなぜか冷めている時。
中学三年生の春、担任に聞かれた。
「どこの高校に行きたいんだ?」
「わからない。行けるところに行くよ」
「そうか、おまえならどこでも大丈夫だ」
私は思った。
「この人は私のどこを見てこんな簡単に、こんな無責任なことが言えるんだ?」
担任の先生は決してきらいではなかったし、どちらかと言うと、とても生徒に真剣で、面白くて私はとても信頼していた。でも、この時に、「あー、この人に受験の話はできないなー」なんて感じた。当たり前の話だが、担任は私の定期テストの「結果」しか知らなかった。
高校受験を考えた時、学校の成績に意味がないことは私自身、よくわかっていた。私はあくまで、定期テストのために勉強していた。教科書を暗記したり、授業中に先生がくばったプリントばかり復習したり。実力ではない。塾では、「一年生の時から実力をつけろ」と言われ続けていた。塾で言われたことは全てこなしていたし、全校テストの成績もまあまあ良かった。
でも、自分の実力には全く自信がなかった。良い成績を残していたのはあくまで偏差値の高い高校に入るため。成績はある。あとは実力をつけるだけ。特に深く考えずにこの辺の一番偏差値の高い高校を受験しようと思った。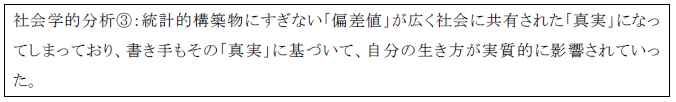 「A高校に行こう」
「A高校に行こう」
私の答えは案外簡単に出た。でも、ひとつ問題点があった。A高校はほぼ私服登校だったことだ。私服に関して若干、面倒に思っていた私は、とりあえず、高校までは制服が着たかった。これが私の志望校選びの悩みだった。ばかばかしくて笑えるかもしれないが、本当にどうしようかと悩んでいた。
学校のやりとりから数日後、塾の先生と全く同じやり取りをする。
「どこの高校に行きたいんだ?」
「分からない。行けるところに行く。でも、『良い』高校に行きたい。A高校とか興味あるよ。先生、どう思う? でも、私服なんだよね」
私は、その時思っていたことをそのまま伝えた。
「おまえに、『良い』学校があるんだ」
先生はそう言った。
「B高校知ってるか?」
「知らない。どこそれ?」
そこは、A高校の次くらいに偏差値が高いと言われていた高校だった。先生に言われるまでB高校に関して全く知らなかった。というか、他の高校に関しても全く知らなかった。先生は付け加えた。
「制服があるぞ、しかも、スカートには黒いリボンが入っていてとっても品がある。あの制服着てれば、すぐにどこの高校かわかる。一種のステータスみたいなもんだな」
「なんで私にその高校がいいの?」
「勉強できる生徒ばかりだし、部活動も活発だ。おまえみたいに、こつこつ頑張るタイプの生徒が多い雰囲気だな。A高校はおまえには自由すぎて戸惑うんじゃないか?」
「ふーん、じゃあ、その高校に行く」
この会話で私の志望校は変更された。塾の先生は、一人でも多くの生徒に偏差値の高い学校に合格してほしいと思っていることは、その時の私でもわかっていた。でも、学校の先生より塾の先生の方が私自身を見て学校を考えてくれているように思えた。学校の先生は私の結果しか見ていないけれど、この先生は私の結果に至るまでの時間を知って、この高校を薦めてくれているのだと思った。今までの私を認めてくれている。そんな気持ちになった。
「先生、私、さすがに一校だけだと不安なんだけど、後、どこ受ければいいかな?」
「なら、公立はもうひとつ、○○高校。私立は、△△高校、T女子高校、□□学園の順でいいんじゃないか?」
こうして、私の志望校の五校は塾の先生によって全て決められた。私は、何か具体的にやらなければいけないことができると頑張れるらしい。第一志望を決めてから、それまで以上に勉強に打ち込んだ。学校の成績はもちろん、落とさない。部活も中学最後の夏、大きな大会が控えていた。部活も本当に忙しかった。土曜日は練習試合で潰れたし、部活の時間がどんどん増えていった。
でも、今の私の実力ではトップの公立校なんて無理だとわかっていた。だから、しっかり実力をつけようと基礎から勉強した。定期テストのための勉強の他に、公立高校一般入試のための勉強、加えて、受験予定の三つの私立の入試のための勉強をどれもしっかりとこなしていた。私立の入試はそれぞれの学校のテストに特色があり、厄介だったが、やらなければいけない。「不合格なんてありえない」と受験する全ての高校に合格しようと、ただひたすら勉強していたように思う。
夏休みには近所の通っていた塾にプラスして、地下鉄で十五分ほどの同じ塾の違う校舎に特別講座のために通う日々だった。そこには他の校舎の生徒が、「同じ思い、良い高校へ」という強い気持ちで集まってきていた。私の通っていた校舎からは、私しかその講座をとっておらず、友達はいなかった。でも、みんなそれぞれの目標は明確だった。友達とおしゃべりにわざわざ来ている訳ではない。自分の実力をつけるためだ。今までの塾の教室の雰囲気とは全く違うものを感じた夏休みの経験だった。
その教室での私の順位は平均だった。もっと勉強している同級生を見て、私もまだまだなんだと考え直された。今思い出しても、よく頑張っていたなと、あの時の自分を褒めてあげたい。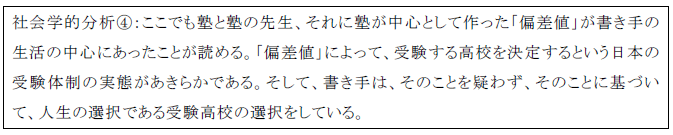 不本意入学
不本意入学
これだけ勉強していても落ちる時は落ちる。私立の第一志望は不合格。その次のT女子高校と、その次の滑り止めはなんとか合格。私立の一般入試は二月。その後に公立。私立が一つダメだったことは全然気にもしていなかった。「私はB高校に行くから大丈夫だよー」。何の根拠もない話だった。それでも、笑いながらそんなこと言っていたのを覚えている。それだけ勉強していると思っていたし、自信があったのだと思う。三月の公立入試の本番まで、私のB高校に対する思いはだんだんに強くなっていった。
公立は2校とも不合格。あれだけ憧れをもっていた、B高校の制服を着るという目標は果たせなかった。中学の集大成、このテストに全てを懸けていた。その時は、高校受験が私の人生を左右する全てのように思えていた。公立高校合格発表から帰宅。2校とも不合格。この事実は、T女子高校に入学することを示していた。泣いて、泣いて、泣いた。 「あなたが頑張ったなら、それでいいじゃない」
「あなたが頑張ったなら、それでいいじゃない」
母はとても冷静だった。でも私は後悔の塊だった。
「あの時、もっと…」と考え始めたら切りがなかった。
「T女子高校に行くくらいなら、高校には行きたくない」
この一言に母は言った。
「あなたのおばあちゃんたち姉妹は、みんなT女子高校の卒業生なのよ」
私の母方の祖母は、母が六歳のころに亡くなっている。今のおばあちゃんは、後妻さんだ。亡くなった祖母は五人姉妹だった。みんな女。祖母は長女。よくできた人だったと話だけは聞いていた。
祖母はもう一人いるという事実を母から聞いたのは、私が小学三年生のころ。曖昧に親戚だと言われてきた人たちが沢山いたことは、小さいながらとても不思議に思っていた。亡くなった祖母方の家族だったのだ。今のおばあちゃんは祖母の話を嫌がった。もちろんその気持ちも周囲は分かっているから、自然と亡くなった祖母の話はしてはいけない暗黙のルール。祖母の妹たちを含めた親戚の話ももちろんしてはいけなかった。
でも、私には関係なかった。亡くなった祖母に会ったことはなく、今、目の前にいるおばあちゃんが私のおばあちゃんだ。だから、私もその件に関しては何も聞かずにいた。
その祖母の姉妹たちみんなが、T女子高校卒業だというのだ。しかも中学から。全く知らなかった。公立2校に不合格になり、私がT女子高校に入学することが決まって、その時初めて言われたのだ。母は付け加えた。
「お母さんは、あなたが私立の第一志望に落ちて、T女子に合格したことは何かの縁だと思っていたの。B高校よりも、もっとあなたにとって良い学校かもしれないと思っていた」
そんなことを言ったのだ。私は腹が立って仕方がなかった。私があれだけ勉強してきたことを全否定されたような気持ちだった。この言葉をきいて更にT女子高校に行きたくなくなった。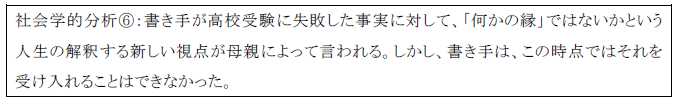 どうして、これほどまでに行きたくないと拒否をしたのだろう。あれだけ勉強してきていたのに認められず、結果が出ず、目標を達成できなかった。なんだか大きな勝負に負けたような気持ちだったのだ。その負けを素直に認めることができなかった。それまでにこんなにも大きな負けを感じたこともなかった。ずっと勝ちたい勝負は勝ってきたように過ごしてきていたのも、ひとつの理由かもしれない。
どうして、これほどまでに行きたくないと拒否をしたのだろう。あれだけ勉強してきていたのに認められず、結果が出ず、目標を達成できなかった。なんだか大きな勝負に負けたような気持ちだったのだ。その負けを素直に認めることができなかった。それまでにこんなにも大きな負けを感じたこともなかった。ずっと勝ちたい勝負は勝ってきたように過ごしてきていたのも、ひとつの理由かもしれない。
入学式の日
私も現実を見て、T女子高校への入学に同意したが、入学まで、その敗北感から立ち直ることができなかった。入学式の日になってもまだ、顔は不機嫌でいやいや感がたっぷりだった。入学式当日、体育館にクラスごとに並べられたイスは各クラス2列ずつ。1列はT中学からの生徒、片方は外からの入学生。きれいに分けられた。一目見て、違いは歴然としていた。T中学からの子たちは慣れ親しんだ友達とおしゃべりに盛り上がり、全く入学式の緊張感はなく、リラックスした様子。私たち、外からの入学生はもちろん、知っている友達もおらず、緊張感たっぷり。女子だらけの四〇人のクラスだった。その時の私はもちろん不機嫌で加えて、不安でいっぱいだった。
入学前のT女子高校のイメージはいいとこ育ちのお嬢様がたくさんいて、いじめとかもたくさんあるのかな、とか。女子の特有なグループ意識も特に強かったりするのかな、なんて思っていたりした。そんなところ絶対馴染めない。入学前からそんなことを決めつけたりもしていた。
入学式後、教室に移動。その時の私の正直な感想。
「うわー、女子しかいないー。すごい変な感じ」
クラスに女子だらけ。一年生のころは先生も女性の先生だった。はじめ教室内は、自然と中学からのあがりの子たちと、それ以外の子たちで分かれていた。でも不思議なことに、帰る頃になるとそんな境界線なんかなく、みんながわいわいしていた。私も中学あがりの子二人、YちゃんとTちゃんとと仲良くなり、三人で駅まで帰ったりした。どうしてあの二人だったのかはよく覚えていない。でも、二人が話かけてくれたことは覚えている。とっても気さくで面白くて、とっても個性的。その後クラスが分かれたりもしたが、高校三年間とても仲良かった。
大学も学部は別々だったが今も連絡をとっている。その二人がいたから私がもっていたT女子高校のイメージは、初日にどこかにいってしまった。二人からT女子高校のはじめの一から十まで教えてもらったような気がする。校舎内のことから先生のこと、T女子高校の暗黙のルールみたいなこと、T中学出身の子たちの情報まで、ありとあらゆることを教えてくれた。
入学式から帰宅。私の一言は、「結構、楽しかった」。その言葉に母はびっくり。私自身はそんなこと言ったことを覚えていなかったが、後から母が言うには、それは、それはびっくりするくらいの態度の変わりようだったらしい。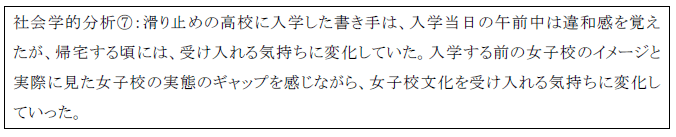 学園生活
学園生活
T女子高校の生活がスタートして私の考え方は大きく変わった。T中学出身のクラスの友達たち、T高校という環境の影響がとても大きかった。上手く言葉に表すことができないが、彼女たちはみんなとてもキラキラしていた。みんな、それぞれ違う「自分」をもっていた。自分の好きなこと、興味あること、自分が思うがままに、「今」をとても楽しんでいるように見えた。ただ、「今」だけではなくて、「未来の自分」についてもしっかり考えをもっていたし、物事に関しても自分の意見もしっかりもって、発言する力もあった。
中学時代、私があれだけ頑張っていたテストに関しては、「テスト勉強はそこそこに!」が、みんなそろっての合い言葉だった。私にとっては全く違う世界に来たようだった。
私も一年生の時点では、大学進学は内部推薦でT大ではなく、他大受験を考えていたため、中学同様、今まで通りテスト勉強に励んだ。またT女子高校は、公立高校の授業のカリュキュラムと大きく違いがあったため、その差を埋めるため、また新たに塾にも通い出した。
T女子高生活の中で私の気持ちが全く変わった。高校三年間に出会った友達、先生、起こった出来事全てが私の考え方を変え、世界を新しくした。いつの間にかT女子高校の先生についても詳しくなって、テストの傾向もつかみ、授業で力を抜くようになった。後輩もでき、球技大会のドッヂボールに全力を注ぎ、朝練することにも全く違和感がなくなり、体育の授業ではちまきをつけることも、ラジオ体操の第二しかしないことも、冬には体育館でフォークダンスを踊ることも、文化祭の出し物に数か月の全てをかけることも、全く不思議に思わなくなった。T高校生活をおおいに楽しんでいた。
特にT女子高での文化祭の比重はとても大きかった。出し物の案について話し合いを始めるところから、みんな「超」真剣。T中出身の子たちがとりあえず、目の色を変えて、体を乗り出し、話し合いに挑む姿勢は一年生の私に大きな衝撃を与えた。準備が進む中で仲間割れもしばしば。真剣になりすぎて、泣き出してしまう子も。いつもおちゃらけて、部活バカな友達も、文化祭と聞くと顔が変わった。文化祭の出し物の順位の結果発表でも、泣き出す子は当たり前。嬉し涙、悔し涙、みんな本当に素敵だった。三年生の頃には、こんな生活も当たり前すぎて自然なことになっていた。
こんな話を同じ中学出身の公立高校に通う友達にすると驚かれ、少し引かれる。テストの点数、成績、部活だけの生活に充実感を感じていた頃とは変わり、T女子高校独特の生活、友達との旅行、おしいいランチ、映画を楽しんだり、コンサートに行ったり、読書する時間も増えた。一年生の頃から水泳部に入っていたが、体調が思わしくなく、二年始めには退部。それからは時間もできたので、「アルバイト!」と思ったが、T女子高校では高校生のアルバイトは禁止。でも私は、親戚の伝手で家のお手伝いという名目で歯医助手として働き始めた。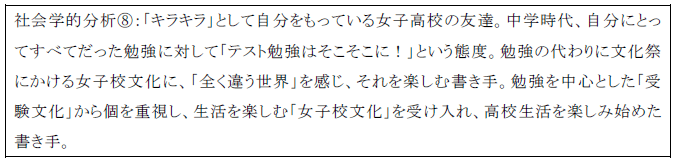 七年たった今でもそこでのアルバイトは続いている。その歯医者で高校生を雇うのは私が初めてで、多分最後。何も知らない、分からない、高校生の私に教えることはとても大変だったと思うが、先生やパートのおばちゃんたち、その時の大学生のバイトの先輩には本当に感謝している。「働く」ということに関して考えるようにもなったし、電話対応から、患者さんへの対応、器具の準備、片付け、厳しく注意されることも多かったが、ここでの経験はとても貴重なものだ。私の高校生活は、中学の頃とは違う意味でとても充実していた。
七年たった今でもそこでのアルバイトは続いている。その歯医者で高校生を雇うのは私が初めてで、多分最後。何も知らない、分からない、高校生の私に教えることはとても大変だったと思うが、先生やパートのおばちゃんたち、その時の大学生のバイトの先輩には本当に感謝している。「働く」ということに関して考えるようにもなったし、電話対応から、患者さんへの対応、器具の準備、片付け、厳しく注意されることも多かったが、ここでの経験はとても貴重なものだ。私の高校生活は、中学の頃とは違う意味でとても充実していた。
大学受験に向けて
高校二年生と三年生の担任は同じ数学の男性の先生だった。私の考え方が変化していくのを一番知っている人かもしれない。二年生の時点でもまだ、他大の受験を考えていた私は、担任の先生に素直に相談した。先生は、「T大への進学に少しでも興味があるのなら、一つの選択肢として残しておいた方が良い」と言ってくれた。私は何故か中学の頃から理系で、数学も理科も得意科目だった。高校でも何故か、頑張って勉強しなくても数学や理科のテストはなかなか点数が良く、数学の先生だった担任も「将来、真剣に理系の職を考え、大学進学するなら決断は早めに」とアドバイスをくれた。
逆に、文系のテストはイマイチ。中学ほどテスト勉強に打ち込まなくなった私は、苦手な科目の成績は良くもなく悪くもなく、くらいだった。英語、国語、社会、どの科目も好きだったが、成績は普通だった。長文読解は元々、読書が好きだったので得意だったが、古文の暗記に近い勉強はとても苦手。英語を聞くのは好きだったが、教科書の暗記は苦手。歴史が好きで日本史も世界史も好きではあったが、カタカナの人名、地名はまるっきりダメだった。
今思うと、これが私なんだと思う。すごーく普通だ。数学も理科も好きだったが、理系に進みたいという思いには至らなかった。数学は一つの解答にたどりつけた時の達成感が好きだったし、理科は、世の中の不思議なこと、化学だったり、物理、生物であったり、それぞれの分野を理解していくことが面白かった。基本、学ぶことが好きなことは中学の頃と変わらなかった。
でも、三年生にもなると理系のクラスには本当に数学、理科が好きな子、理系の学部を他大で受験する子たちが集まった。私はそこまでの気持ちはなかったし、自然に英語や国語の授業を選択。でも、成績はイマイチ。特別に勉強したい分野もない。軽く、壁にぶつかった。「他大で特に行きたいところもない。なら、残りのT女子高校での生活を多いに楽しみ、T大に進学しよう」。それが、三年生の春、決意したことだった。この決意も両親ととても驚かせた。
高校の成績はトップではなかったが、とりあえず、T大の学部を選べるようなくらいにはいたので、これ以上落とさないように、少し上げるくらいの気持ちでいた。夏休みはもちろん、クラスの出し物の準備に全身全霊を込めていた。公立高校の友達は受験勉強のために予備校に毎日通っていたが、私は毎日学校にいた。劇の準備のために。私の夏休みはこんな感じだとは到底、その友達たちには話せなかったのを覚えている。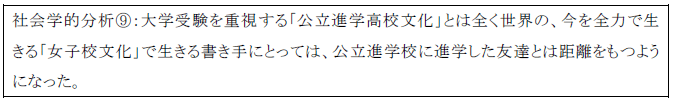 学部選択も、高校受験した時の志望校選択となんら変わらなかった。T大の内部推薦は高校の成績順で選択権が与えられるようなものだった。管理栄養学科は成績トップクラスの子たちで定員いっぱい、こんな状況だった。私たちの大学入学から新しく教育学部ができた。担任には、「数学が好きなら数学の先生の道もある」と、勧められたが、先生になることにイメージがもてず、教育学部は断念。特にデザインなどにも興味がなく、なぜか自然に、国際コミュニケーション学部を選択していた。管理栄養学科の次くらいに言語コミュニケーション学科の目安成績が高く、私の成績ではギリギリだったが、とりあえず、第一志望は、「国際言語コミュニケーション学科」だった。
学部選択も、高校受験した時の志望校選択となんら変わらなかった。T大の内部推薦は高校の成績順で選択権が与えられるようなものだった。管理栄養学科は成績トップクラスの子たちで定員いっぱい、こんな状況だった。私たちの大学入学から新しく教育学部ができた。担任には、「数学が好きなら数学の先生の道もある」と、勧められたが、先生になることにイメージがもてず、教育学部は断念。特にデザインなどにも興味がなく、なぜか自然に、国際コミュニケーション学部を選択していた。管理栄養学科の次くらいに言語コミュニケーション学科の目安成績が高く、私の成績ではギリギリだったが、とりあえず、第一志望は、「国際言語コミュニケーション学科」だった。
三年の秋、文化祭も終わってそんなに時間もなく、すぐ内部推薦の選考だった。なんか普通に考えてありえない感じではあったが、それは軽くやってきた。
「いついつまでに最終志望を決めて」
「おおーこんな簡単にやってくるのか」
と、その時は思ったが、何故かすんなり受け入れられた。
「これがT女子高校の流れなんだなー」
と思い、流れに沿っていた。しかし、結果は残念。
一部の成績上位の子が最後にして志望を変更、私は「言語」の定員に入ることができず、第二志望の表現文化学科に。その時はもちろん号泣。高校受験の結果を思い出した。
でも、表現への入学は案外早く受け入れることができた。どちらの学科も同じような授業が選択できると知っていたし、テスト勉強も手を抜いていた。成績が十分でなかったのは自分の責任であるし、「表現」へ行けば行ったなり、自分の道を見つけ、楽しめると思った。おそらく中学生の頃の私だったら、こんな考え方はできなかっただろう。こんな風に考えるようになったのもT高校での生活の影響だと思っている。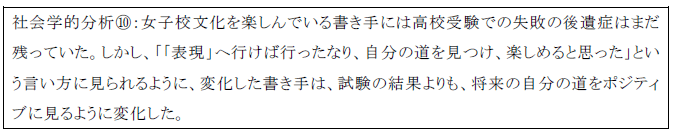 大学生として
大学生として
今は、表現文化学科に来て本当に良かったと思っている。今まで興味をもっていなかった内容の授業も取ることになったりして、新しい発見が多い学科だったように思う。休学までして留学もした。英語は苦手科目だったのに不思議な話だ。自分で休学したい。なんて行動に移すことも以前の私では考えられなかった。でも、留学でまた、新しい人たちとの出会いもあったし、考え方も変わった。
今、中学の頃の友達に会うと、私は高校に入って本当に変わったと言う。「自分があるね」って言われることがとっても嬉しい。T女子高校に通って、人と比べないようになった。もちろん、今でも勝負事は負けるととても悔しいが、「自分のままで勝負している」感じがする。人と比べない。私には私の考えがあって、人に押し付けることはしたくないが、伝えたいとは思う。相手の思いを聞く時間もとても好きなんだと。これまで自分と向き合ってきての発見だ。
T女子高校では、こうして自分と向き合うこともできるようになった。普通に公立高校に進学していても、自分について考える時は誰にでもくると思う。でも、私にとっては、そういった時間をT女子高校という環境の中で過ごすことができたことは本当に嬉しく、感謝している。
私にとってT女子高校で出会った友達、後輩は本当に個性的で頼もしい。彼女たちの存在なしでは「今の私」はいない。それぞれが、それぞれの方法で輝いているし、かっこいい女性ばかりだ。私は彼女たちをとても尊敬している。これからも今まで通り切磋琢磨して支え合っていきたい。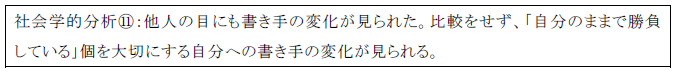
今の私―祖母との縁に感謝して
母と私の今までについて話したことがある。「あなたは高校生活をT女子高校で過ごして本当に良かったね」と言われたことがある。母も私の変化に気づいていたのだ。母も私も、T女子高校でおきた私の変化は良い変化だったと思っている。あの時、高校受験で第一志望の公立高校に合格していたら、T女子高での充実した生活はなかった。こんな風に自分について考えることはなかったかもしれない。T大に来ることもなかったかもしれない、休学して、留学してなんてことを考えることもなかったかもしれない。
でも、今はこうしていまT学園の一員として学べていることがとても嬉しい。これから社会人になって大変なこともたくさんあると思うが、私は私らしく乗り越えられると信じている。
「第一志望に落ちて、T女子高校に入学するのも何かの縁かもしれない」
これは、私が高校受験で第一志望に落ちた時に母が言った言葉だ。あの時、私はこの言葉に本当に腹が立ったが、本当に良い縁だった。亡くなった祖母は、T女子高校が私に良い場所だとわかっていて、あの時の私に「T女子高校で学べ」と天国から言っていたのかもしれない。
二〇一一年年七月三日二十三時、二十二歳最後の日がもうすぐ終わる。二十三歳の一年はどんな年になるのかな。小学生の頃に描いていた二十三歳の女性ってもっと大人な感じだったような。二十二年間の私の時間を振り返ってみても、何ひとつ後悔はない。
「本当に…?」
やっぱり少し違うのかもしれない。後悔はたくさんある。でも、後悔しないように気持ちを変えることができるようになったのだと思う、この二十二年間で。私の人生に起こった出来事には全てに意味があって、「今の私」をつくるために、「未来の私」のために必要な時間だった。
そう思えるようになったのは、明らかな私の中の変化だ。T女子学園の一員として学び始めてから、私の世界は新しくなった。あれからもう七年がたった。八年目の真っ只中、この学園の学生であることを誇りに思い、最後の一年を大いに楽しみたい。T女子学園が私に与えてくれた経験全てに、感謝して…。
最後に、神様は、これまでT女子学園で成長してきたであろう私にちゃんと大きなご褒美をくれた。第一志望の企業に内定。二十三歳を思い、考えることは沢山あるが、後悔はひとつもない。大きすぎるご褒美にとても感謝している。これからもっと世界が広がって、沢山の人たちに出会って、新しい発見をして、苦しいこと、大変な時を乗り越えながら楽しく生きていくことが楽しみで仕方ない。
これからもT女子高校、T大学で出会った友達と自分らしく生きていきたい。来年の誕生日はきっとお仕事が大変だろう、その時、私はどんなことを考えているのだろう。楽しみだ。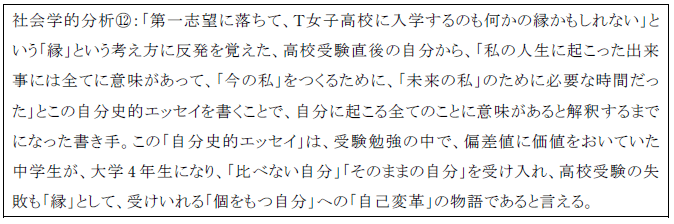 (2) 事例2:「今までお嫁さんになるために勉強してきたの?」
(2) 事例2:「今までお嫁さんになるために勉強してきたの?」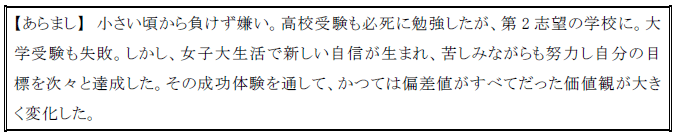 高い偏差値の高校をめざして
高い偏差値の高校をめざして
私は、小さい頃から負けず嫌いだった。だから、小学校の頃から授業をしっかり聞き、テスト前には自分自身で勉強するといったように過ごしてきた。中学にあがってからも、より一層勉強を頑張った。できるだけ高い偏差値の高校に入学するために。毎日の授業はしっかり聞き、きちんと宿題もこなし、週に何度かは塾にも通っていた。テスト、二~三週間前からは、夜遅くまで勉強し、土日は塾の自習室に行き、夜遅くまで残り、納得がいくまで分からないところを、先生に質問したりもした。塾で宿題として出されたプリントは、もちろんすべてこなし、新しい他のプリントをもらって勉強することもよくあった。そのかいもあって、いつも定期テストは、ほとんど見た事のある問題ばかりを解いていく感じであった。負けず嫌いな私にとって、テストでの順位や、模試での偏差値は、とても重要であった。そうして、次第にできるだけ偏差値の高い高校に入学することを目標とするようになった。三年間、勉強をおろそかにすることなく頑張ってきたのに、第一志望の高校には合格する事ができず、第二志望の高校に進学することになった。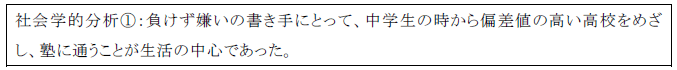 進学高校での受験勉強生活
進学高校での受験勉強生活
私は、いわゆる進学校と呼ばれる高校に入学した。私の高校の学生は、一見派手で自由に学生生活を送っているようにみえるが、実際は違った。校則も緩かったため、化粧もしている子もいれば、髪の毛を染めている子もいた。しかし、みんな勉強に対しての熱意は鋭かった。どんなに派手に見えて、勉強になんて興味なさそうに見えても、「やるべきときはやる子」ばかりだったのだ。みんな国公立を目指し、できるだけ偏差値の高い大学に入学しようと一年生の頃から頑張っていた。高校の先生も、私たち学生にいつも、こう教えた。「できるだけ偏差値の高い有名大学へ行け。浪人して当たり前。有名大学に通えば、それが就職を成功へと導くんだ!」と。そのような高校で3年間を過ごす中で、私も自然に、全国的に有名な大学に進学することを夢見るようになった。そして、私はいつからか、人生の最終ゴールは大学名にあると思うようになっていた。
高校三年生の秋、私は大学受験を控え、とても悩んでいた。それは、価値観の違いが生んだ大学選びの違いだった。偏差値を重視する大学選び、そこに重点を置かない大学選び。私は、大学受験に向けて、最終的に受験校を決定しようとしていた。私は、全国的に名の通った大学に行くために、県外の大学へ進学したいと思っていた。家族にそのことを相談すると、「女の子が1人暮らしをするのは危ないし、心配だから。家から通える大学にしなさい。」と言われてしまった。その頃の私は、高校の先生や、周りの友達の影響もあって、家族の心配など、まったく受け入れがたいもので、大学受験において妥協など許されないと思い込んでいた。そこで、私は家族との相談の結果、新幹線で家から通える大学と、両親が勧める女子大を受けることに決め、志望校調査票を担任の先生に提出した。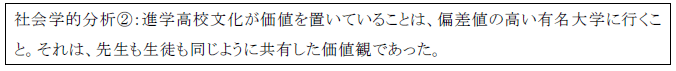 どうして女子大を受験するの?
どうして女子大を受験するの?
それからすぐに一人ずつ、その調査票をもとに、担任の先生と話し合う機会があった。私は、今の自分のレベルからは挑戦にあたる県外の大学と、両親の勧める女子大の二校を受験するつもりだと言うと、先生の表情が曇った。そして、先生は「どうして女子大を受ける必要があるの?あなたは、なんのために、この高校に入学して、今まで勉強してきたの?結婚をするために、今あなたはこの高校にいるわけじゃないでしょ?」と私に問いかけた。私は衝撃を受けて固まった。自分でも、女子大を受験することに対して、少なからず抵抗はあったものの、あれほどまで先生に言われるとは思いもしなかった。今でも、この情景を思い出せるほどだ。それ以来、先生や学校の友達の前では、「努力もできず、すぐ諦める子なんだ。」というレッテルを張られるのが怖くて、それと同時に恥ずかしく感じられ、いくら滑り止めであったとしても、女子大を受験することなど、口が裂けえても言えなかった。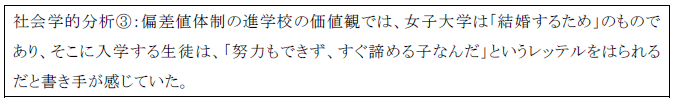
女子大に入学することを決めて
そうして、受験も終わり結果発表。残念ながら、第一志望の県外の大学に落ち、もう一つの女子大に合格するという、私にとって信じがたい結果となった。三年間進学校で過ごし、「偏差値がすべて。有名大学が人生のすべて。」と思い込んでしまっていた私にとって、この結果はとても簡単には受け止められるものではなかった。私は、すぐに家族に、「一年間浪人させてください。」と話をしてみた。しかし、家族は「浪人はやめなさい。女子大に通えばいいじゃない。大学に入るのに、偏差値がすべてではないよ。もっと視野を広げなさい。」と言った。家族は春休みの間中、ずっと私に女子大に通うよう説得し続けた。家族の中だけにいれば、日に日に「女子大に行くのも悪くないんじゃないか。」と思えたりもしたが、高校の友達に会えば、そんな感情は一気に吹き飛んでしまった。「自分は本当にこれでいいの?みんなは、行きたい大学に入れるまで浪人する意気込みなのに。」と自分自身によく問いかけた。私の高校三年生のクラスの子は、半分ほどが浪人を決めていた。彼らにとって、一年間行きたい大学に入るために他の子たちに遅れることなど、全然恥ずかしくないことで、逆に誇りさえ感じられた。そういう姿を見ると、余計に自分自身が恥ずかしく、自分のこれからの人生は終わったようなものだと思った。
春休みが終わる頃、私は大学で留学をさせてもらうことを約束に、しぶしぶながらも女子大へ入学することを決めた。家族はみんな「日本の中なら、どこの大学に行っても、自分次第で同じことを学べる。でも、海外に留学すれば、今までは見た事、感じた事のない事がたくさんあって、そこでしか学べないことがある。だから、同じ一年を過ごすなら、浪人に費やすのではなく、留学した方が、もっと有意義な時間になるんじゃない?」と私に言った。中学生の頃から、いつかは留学に行きたいと思っていた私は、この言葉を信じてみることにした。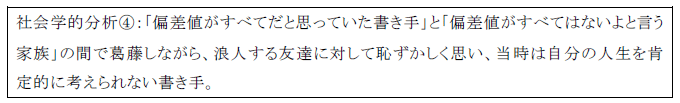
女子大で自信が生まれた
入学式当日。気が進まなかったが、一応入学式へ行った。会場に入ってみると、今までとは違った周囲の雰囲気をすぐに感じ取り、それと同時に戸惑った。「やっぱり私の行きたい大学はここじゃない。」と強く思った私は、家に帰り、母に泣きながらお願いした。「来年もう一度受験して県外の大学に行きたい」と。春休みの間、ずっと私を説得し続けてきた母も、さすがに、私を女子大に通わせ続けるのは無理だと感じたと、あとから聞いた。私は女子大に通いながら、受験勉強を並行してやり、来年もう一度、受験することを心に決めた。
記憶が曖昧だが、たしか入学式の次の日はオリエンテーションがあり、その中で英語のクラス分けのテストがあった。これまで偏差値ばかり追い求めてきた私にとって、テストは重要なもの。そんな私は、このまま女子大に通い続けるのは嫌なのにも関わらず、どうしてもこのクラス分けテストを受けずにはいられなかった。そして、そのテストの結果、私は一番上のクラスに入る事ができた。高校の時には、なかなか結果を残すことができなかった私にとって、このとき中学生以来の快感を久しぶりに味わう事ができた。
こうして始まった大学生活。嫌々とは言いながらも、中途半端は嫌だった私は、心を入れ直して、勉学に励もうと心に誓った。大学での授業を受けるうちに、高校時代は、努力しても、なかなか自分が思うような結果が出せなかったが、ここの大学では自分が頑張れば、頑張るほど、自分の力になり、それが成果としてでるような気がした。その感覚が、私にとって快感になった。高校では、自主自立が基本で、先生は勉強に対して口出しはしても、温かくサポートはしてくれなかった。でも、ここの大学の先生は違った。私が望めば、望むほど、より一層それが叶うように、相談にのってくれたり、温かくサポートしてくれる。そのうえ、だんだん友達も増え、徐々に私は、この女子大に通うのも楽しいかも!?と思えるようにまでなり、自然に来年受験をし直そうという気持ちはなくなっていった。だからといって、周りの人に胸を張って、女子大に通っていることを言えなかったが。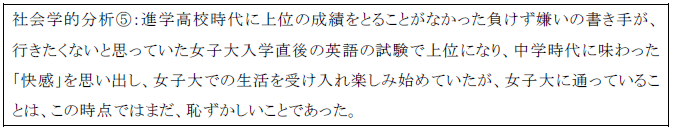 カナダへの留学
カナダへの留学
私は、大学生の間に、英語をペラペラと話せるようになることを夢みていた。二年生の後期に中期留学として、私は大人気であるカナダに留学したい一心で、その選抜に使われる一年生の冬のTOEICでの勉強を頑張った。その結果、TOEICの点数自体は決していいとは言えないが、なんとかカナダへ留学できることになった。そこで、私はその担当であった一人の先生と、一緒にカナダに行く四人の友達に出会った。留学に向け、何度かミーティングをするうちに、カナダに行った先輩方とお会いする機会があり、先輩方の英語の流暢さに感動すると同時に、私たちもこうなりたいとグループ全員で思った。カナダに行くグループの伝統として、留学から帰ってきてからのTOEICの点数の伸びが他に比べ、すごく良いということも知った私たちは、留学前にTOEICグループ全員六百点達成という目標を掲げた。それから二カ月間、範囲となった部分の問題集をやり、随時先生による確認テストが行われた。私は、もう大学生活失敗したくないと思い、確認テストで高得点を取れるように勉強した。しかし、一回目の確認テストは、最悪のものだった。自分ではやったつもりだったが、それは単なる「やったつもり」であって、全然自分の力になっていなかったのだ。その時、先生に言われた言葉は「これで、本当に勉強したの?」だった。私は、本当に悔しかった。でも、この悔しさが私を変わらせてくれた。やったつもりではなく、自分の力になる勉強をしなきゃいけないと。それからは、勉強方法も変え、今まで以上に努力した。ただでさえ、大学の英語の授業は宿題が多いというのに、そのうえにTOEICの勉強もしないといけなかったため、ほぼ毎日三時間ぐらいしか寝られない日々が続いた。学校でも、お昼や空き時間、少しでも時間があれば、TOEICの勉強をした。そんな生活が時々、嫌になることもあり、たまに泣きながらTOEICの公式問題集を解いていたような気もする。しかし、その結果、私は留学前に、六百点を超えるという目標を達成する事が出来た。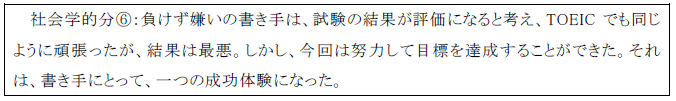 ある程度TOEICの点数もあることだし、会話も困らないのではないかと、甘い考えでカナダへと飛び立った。そして始まった七か月間のカナダでの留学生活。はじめに直面することになった困難は、ホームシックであった。私は、日本にいる間は家族に頼ってばかりの生活を送っていたため、初めて家族から離れて生活をすることになり、とても戸惑った。それに加え、私は自分の語学力の足りなさ。はじめは自分が相手に伝えたいことを、まったく伝える事ができず、自分の語学力の足りなさを痛感させられる日々が続いた。楽観的に、留学に行きたいなどと言った自分に、とても後悔し、毎日日本に帰れる日までの残りの日数をカウントした。そんなとき、いつも周りの友達が私の心の支えになってくれた。そのおかげで、カナダの生活にも慣れてきた頃、徐々に「このまま気持ちが落ち込んだままでは、せっかくの貴重な七ヶ月が、なにも残らない無駄な七ヶ月になってしまう」と思い直せるようになった。
ある程度TOEICの点数もあることだし、会話も困らないのではないかと、甘い考えでカナダへと飛び立った。そして始まった七か月間のカナダでの留学生活。はじめに直面することになった困難は、ホームシックであった。私は、日本にいる間は家族に頼ってばかりの生活を送っていたため、初めて家族から離れて生活をすることになり、とても戸惑った。それに加え、私は自分の語学力の足りなさ。はじめは自分が相手に伝えたいことを、まったく伝える事ができず、自分の語学力の足りなさを痛感させられる日々が続いた。楽観的に、留学に行きたいなどと言った自分に、とても後悔し、毎日日本に帰れる日までの残りの日数をカウントした。そんなとき、いつも周りの友達が私の心の支えになってくれた。そのおかげで、カナダの生活にも慣れてきた頃、徐々に「このまま気持ちが落ち込んだままでは、せっかくの貴重な七ヶ月が、なにも残らない無駄な七ヶ月になってしまう」と思い直せるようになった。
留学先での勉強
それから、心を入れなおし、語学力を身につけようと必死になった。しかし三か月が経っても、一向にスピーキング力が伸びる気配がなかった。周りのみんなは、順調にスピーキング力を身に付けられているように思った。それにもかかわらず、私の場合は、来た時となんら変わらないスピーキング力。あと四カ月で日本に帰らなければいけないのに、スピーキング力がまったく上がらないという焦りから、涙を流す日もあった。このままでは四カ月後日本に帰れないと思った私は、カナダ担当の先生にメールで相談してみる事にした。すると、先生は「三つの特訓(音読を五〇回・鏡を見ながら独りごと三〇分・授業で発言する内容の準備)を一カ月続けなさい。そうすれば、次第に効果が現れます。」と言って、アドバイスをくれた。留学に行く前のTOEICも、先生のアドバイス通り信じて勉強したら、みるみるうちに点数が伸びたから、今回の先生のアドバイスも信じて続ければ、絶対に効果が現れると思った。そこで、すぐにその特訓を毎日欠かさず始めた。毎日出されるたくさんの宿題に加えての三つの特訓は、とても大変だった。それと同時に、私の会話をする際の態度を見つめ直す事にした。それまで、語学力不足のせいもあって、自分から話しかけるというよりは、周りの人から話しかけてもらい、それに答えるといった受け身のコミュニケーションをしていた。だから、人よりもスピーキング力が伸びるのに時間がかかってしまうのかもしれないと思った。そこで、私も周りの積極的に会話をする友達を見習って、自分から周りの人に声をかけるように努力した。
そのような特訓の日々を過ごし、留学もあと残り一か月ほどになった頃。自分でも気づかないうちに、ホストファミリーと、三カ月前にはできなかったようなテンポのいい英語での会話ができるようになっていた。私が留学行く前に夢見ていたように、ペラペラと英語を話せるようになっている自分自身がはじめ信じられなかった。見事に、その特訓の成果が現れたのだ。周りの友達やホストファミリーからも、「最近、スピーキング力上がったんじゃない!?」と言ってもらえるようになった。とても嬉しかった。「先生のアドバイスはいつも正しい!先生出会えて、よかった。」とほんとうにそう思った。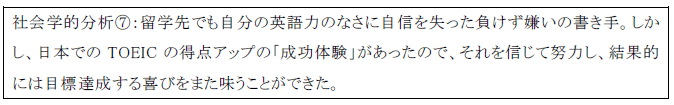
帰国してからの私
こうして、留学生活も終わり、日本に帰国した。次の課題は、TOEICで八百点を取る事だった。カナダに留学に行った先輩たちが、八百点を取っていたので、私にも絶対できるはずと思った。留学中はスピーキング力を磨くことを中心にしてきたが、帰国してからは、留学前にしていたTOEICの勉強法をもう一度思い出し、繰り返し繰り返し、同じ参考書を解いて、勉強した。そして、帰国後3カ月後に、見事八百点を超えることができた。自分でも、信じられなかった。高校時代には、やってもやっても、全然結果を残すことができなかったのに、大学に入ってからは、努力すればすべて良い結果となって返ってくることが。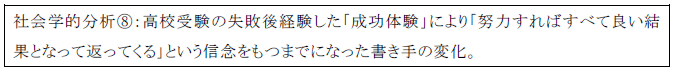
就活で初めて望んだ道へ
大学三年生の冬。ついに就職活動が始まった。私は、父の影響もあり、自動車関係の会社で働くことを夢見ていた。大学生活で私が力を入れてきた英語を活かして働きたいと思った。先生にアドバイスを貰いながら、履歴書を作成したり、面接の練習をしたりと、忙しい日々を送った。今回の就職では、もう失敗できないと思った。今まで、高校受験も、大学受験も、自分の望んだ第1志望には合格できなかった。でも、今回はできることは大学生活すべてこなしてきたし、あとは今まで蓄えてきたすべての力を発揮し、絶対に夢を叶えるんだと心に誓った。そうして、書類選考、何度かの筆記試験、面接試験を突破し、四月の終わり、第一志望の企業から内々定を頂く事ができた。本当に嬉しかった。はじめて自分の望んだ道に進めたように思った。家族も、いつも第一志望に進めない私が、今回初めて、望んだ道に進めることにより、とても喜んでくれた。
偏差値がすべてではない
今まで、思うように進めなかったり、いろいろな困難に出会ったけれど、それらはすべて今の自分に繋がるためのステップだったのかもしれないと思い、このとき初めて大学受験での失敗に、しっかりと向き合えたように思う。大学に入ったばかりの頃は、女子大にしか入れなかった自分を恥ずかしく思ったけれど、今は胸を張って、この大学に入ってよかったと言える。この大学にいなかったら、温かくサポートしてくれる先生や、同じ目標に向かって頑張りあえる友達とも出会うことができなかったから。高校まで偏差値ばかりに、捕らわれていた自分は、いったいなんだったのだろうか。偏差値が、人の人生をすべて左右するはずがないのに。あのころの私は、自分の中では頑張っているつもりだったが、それは単なる「つもり」であり、自分に甘かったのだと、今ふり返ってみて思う。あの頃は、偏差値だけで、進学先の価値を見出していただけだから、自分自身の目標に対する本気さが足りなかったのだろう。大学受験に失敗して、そのとき両親から、新たな価値観を教えてもらえて本当に良かったなと思う。あのとき、「人生偏差値がすべてではない」という新しい価値観を学べたからこそ、私自身の視野、世界観が広がり、人間としてまたひとつ成長できたように感じる。いつも、どんなときも、私を近くで支えてくれた家族には、本当に感謝の気持ちでいっぱいだ。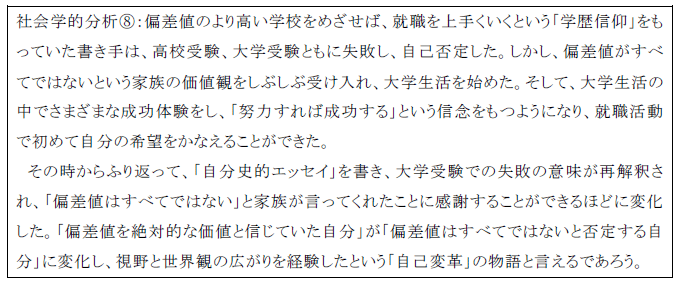 (3) 自分史的エッセイの社会学的分析のまとめ
(3) 自分史的エッセイの社会学的分析のまとめ
上記の「自分史的エッセイ」を書いた二人は、日本の受験体制下、「偏差値」をすべてを評価する基準として考えていた。そして、二人は共に「学歴信仰」を信じていた。その「学歴信仰」が内面化され、主観的リアリティとして位置づけられたのは、現代日本における塾あるいは予備校が「偏差値」を制度化し、受験指導において絶対的なパワーをもたせた結果であった。
そして、受験指導をする塾の教師、学校の教師が受験体制における偏差値をベースにした高校の階層構造を強化する役割を果たし、生徒たちにその階層構造を植え付ける役割をはたしている。
この二人の書き手は、偏差値体制の中で、高校受験あるいは大学受験でいったんは敗北を味わい、それが一種のスティグマになることはあったが、二人はそれぞれ別な方法で、偏差値体制を否定するまでの「自己変革」を経験することになる。
受験や勉強を重視しない「女子校文化」を経験した書き手Bは、「偏差値や勉強を重視していた自分」から、「個を重視し、学生生活を楽しむ自分」に変化し、大学に入学しても、今の生活を楽しむことに価値をおいていった。また、大学受験をめざす偏差値体制の進学校では、「成功体験」を経験できなかった書き手Aは、英語の勉強、留学体験を通して、「努力すれば成功する」という経験をし、自信をもつようになり、偏差値によって否定されていた自分を肯定するようになった。
この二人が、「自分史的エッセイ」を書いたのは、それぞれが夢だと思っていた就職先から内定を受け取ってからのことであった。人生の中で自分の願いがかなった時、今までのさまざまな苦しかった経験が今の自分に必要な、意味ある体験として再解釈された。また、人生における出来事を「何かの縁」で解釈する親に反発していた書き手Bは、希望がかなった経験をしたことで、その親に共感し、いままで起こったことを肯定的に解釈し、外的評価である「偏差値」を否定した。また、「偏差値がすべてでない」と言った母親に対して反発した書き手Aも、「努力すれば、全て良い結果になる」という経験をする中で、「偏差値はすべてではない」と母親に言われたことを感謝するようになった。
この二人の経験した日本の偏差値体制の価値観は、すべての人に影響力をもつように思われるが、この二人の「自分史的エッセイ」に見られたストーリーを時間軸を入れて分析することで、偏差値重視の価値観も、受験での「敗北」というネガティブと思われている経験を通して、影響力を失うものだということが明らかになった。受験体制の中で絶対的だと考えられている「偏差値体制」という神話は、必ずしも絶対的なものではないことが、主観的リアリティを表現している具体的なストーリーを通して明らかにすることができた。このように考えると、ストーリーの社会学的分析の役割は、一人ひとりの主観的リアリティを理解し、人びとの中にどのような共通した問題あるいはテーマが存在するかを明らかにし、一人ひとりの個別的な問題に対して、共感できる洞察を提供することではないだろうか。
参考文献
アトキンソン、ロバート 2006、『私たちの中にある物語』ミネルヴァ書房
アトキンソン、ロバート 2013年3月、“Best Practices of Life Story Interviewing” 岐阜県立
看護大学でのセミナーで発表
スタインホッフ、パトリシア 1986、インタビュー
塚田 守 1998、『受験体制と教師のライフコース』多賀出版
塚田 守 1991、『女性教師たちのライフヒストリー』青山社
塚田 守 2008、『教師の「ライフヒストリー」からみえる現代アメリカ』福村出版
塚田 守 2004、『私たちの告白―9人のライフヒストリー』(自費出版)
塚田 守 2012、『就職活動のさまざまなストーリー』(自費出版)
塚田 守 2013、『就活女子』ナカニシヤ出版(出版予定)
山口智子 2004、『人生の語りの発達臨床心理』ナカニシヤ出版
社会学を専攻し、特に、ライフストーリー研究をテーマとする3人が、ライフストーリーのアーカイヴ化とストーリーの社会学的研究の可能性について考察するために、本研究テーマである「ライフストーリーセンター構築によるストーリーの社会学的研究」を行った。3人はそれぞれライフストーリー研究を行ってきたという点では共通の関心ごとをもっているが、具体的な研究テーマ、方法論、あるいは、教育実践において、それぞれの特徴をもっている。その特徴を活かし共同研究を行い、役割分担をして第1章から第7章の執筆を担当した。本章は、この報告書のまとめにあたるので、それぞれの章で書かれたことを簡潔にまとめ、この研究を通して、何がわかったかについて整理し、今後の研究の発展の可能性について論じ結論としたい。
まず、第1章で、塚田は本研究のテーマを考えたきっかけについて述べている。ストーリーを語り、読むことの重要性について論じながら、そのストーリーを公開し広く読まれる価値について述べた。そして、ロバート・アトキンソンがアメリカで設立しているライフストーリーセンターについて研究した上で、ストーリーのアーカイヴ化である「ライフストーリー文庫~きのうの私~」の設立に至るまでのプロセスと現状について概観した。
第2章は、「ライフストーリー文庫~きのうの私~」のウェブ公開について横家がまとめている。本研究期間の3年間でライフストーリーの43編を公開したことを報告し、ウェブページとして公開する時に、人びとに読まれる魅力あるストーリーにするための工夫について述べた。そして、編集上の工夫や技術について整理し、ウェブ公開に伴う問題点に言及している。
第3章は、ライフストーリーストーリー研究の過去と今について、川又が整理し、まとめている。そのレビューの方法として、ライフストーリーが社会調査のテキストの中でどのように扱われているか、ライフストーリー研究を主眼とする3つの研究会の活動の中でどのような位置づけになっているか、そして、最後に、ライフストーリー研究の2人の代表的な研究者の最新の著書を読み解くことで、ライフストーリー研究のレビューを行い、現状について包括的なまとめを提供している。
第4章で塚田は、自分史をライフストーリーの一つの形態と考え、自分史の社会学的研究が明らかにしている、自分史のもつストーリー性に注目し、自分史作品をレビューし、その特徴について述べた。また、自分史作品が書かれる動機に関する議論を整理し上で、若者が書く自分史作品に注目した。その自分史作品は、自己の物語だと見なし、物語論から自分史を論じ、7章で描写している「自分史的エッセイ」を書く教育実践の理論的背景を整理している。
第5章で川又は、まず、ライフストーリー・インタビューに関する理論的な議論を包括的にレビューしている。次に、本研究がめざしているストーリーのアーカイヴ化している実践例を紹介し、それぞれの特徴をまとめている。そして、最後に、自らがライフストーリー研究のテーマとしている男性養護教諭に関するライフストーリー・インタビュー調査に基づいたライフヒストリーの社会学的研究の実例を示している。そして、インタビューは「人との出会い」であることにも触れ、ライフストーリー・インタビューに基づいた研究の意義について言及している。
第6章は、授業で受講生たちに対してインタビュー調査を課題としている横家が、授業の実践例を紹介する形で、ライフストーリーの作品制作が学生に対してもつ教育的効果について論じている。授業においてまず、制作の動機付けから始め、具体的な語り手探しに関わる学生たちの声に触れている。また、実際に学生がインタビューする時の実践的技術や編集から作品完成までのプロセスを描写し、学生にとって、インタビューは「人との出会い」としての教育的意義があると論じている。
第7章は、授業で「自分史的エッセイ」を書かせる課題を課している塚田が、「自分史的エッセイ」を書く授業実践を描写することで、自己語りとしての「自分史的エッセイを書く」作業は自己変革になるのではないかと論じている。また、「自分史的エッセイ」として書かれたストーリーは、それ自体が一つのテキストとして、読者に読まれるべきものであるという前提で、それをウェブで公開する意義について論じている。さらに、その独立したテキストである「自分史的エッセイ」を社会学的に分析する試論を展開し、ストーリーの社会学的研究の一つのあり方を示している。
以上のように、ライフストーリー研究に携わってきた3人による研究は、「ライフストーリー文庫~きのうの私~」を創設し、運営することで、ストーリーの社会学の可能性を追求している。一つの特徴的な点は、自分史も自己の物語だと位置づけ、ストーリー研究の枠で考えている点である。ライフストーリー・インタビューに基づくライフストーリー研究は、「語られた物語」の内容だけでなく、「どのように語られたか」の視点を重視し、インタビュー調査における相互作用から生まれた「共同作品」であるということが強調される。
それに対して、「自分史的エッセイ」「自分史作品」はその相互作用の要素が少なく、対話ではなく、書き手の「モノローグ」であり、共同作品とは言えないという議論があるかもしれない。しかし、研究代表者の塚田は、「自分史的エッセイ」を書く、読む行為の中にも、「他人の視点」「人間関係」「読み手」などを強く意識しているという点に注目し、インタビュー対象者の語りと同等な、「語られた物語」でもあると見なしている。
ライフストーリーを語ることを通して、インタビュー対象者が過去の経験を再解釈し、意味付与し、自己変革を起こすように、「自分史的エッセイ」も書く行為を通して、自らの過去の体験を再解釈し、意味付与し、自己変革を起こす可能性があるという点では質的に同じではないかと考えている。ただし、インタビュアからの働きかけがないので、相互作用から生まれる物語というよりはむしろ、「過去の自分との対話」、「語らなかった自分との対話」として見なされるべきで、本人の反省的な主体性がもっとも重要な要素になっている。
最後にこの報告書のまとめとして、本研究の意義について整理し、今後のライフストーリー研究の発展の可能性について述べたい。
第1の意義としては、まだ、質的なデータのアーカイヴ化があまり進んでない現在、3人という研究チームのレベルで小さい規模ではあるが、ライフストーリーのアーカイヴ化を行い、一般の読者に公開している点である。この公開されたライフストーリーが一般に人びとにどれだけ役に立っているかは未知数であるが、このように発信することで、ストーリーを読む機会を供給している点は重要であると思われる。今の段階では、まだ、43編のストーリーに過ぎないが、「ふつうの」人びとのストーリーを聞き、読む機会があまりないので、この後、数を増やすことで、その価値と意義が増すであろう。
第2としては、ライフストーリー研究の過去と現在を概観し、ライフストーリー研究に対する包括的な理解を提供しているのではないかと思われる。また、ライフストーリー研究の中に、若い年齢層が書く「自分史的エッセイ」に関わる議論を行い、物語論として展開する可能性に触れている点も本研究の意義であろう。いままで、自分史というと高齢層が自分の過去の経験を「歴史の記録として残す」ものという認識が一般的であったが、「自分史的エッセイを書く」行為は、インタビュアによってインタビューされた語り手が語る行為と類似するものがあるという指摘をし、ライフストーリー研究の枠を広げる可能性について述べている。
第3として、ライフストーリー研究の教育的機能について触れた点も重要であろう。まず、「語られたストーリー」や「自分史的エッセイ」を学生が読むことで、「物語的思考」が活性化され、いままで、理解しようと思わなかったことに共感し、今まで知らなかった世界を知る可能性がある。次に、ライフストーリー研究の一環として、学生自らインタビューを行い、ライフストーリー作品を完成していくなかで、「人びととの出会い」を経験し、編集作業等を経験することで、他人理解、自己理解を深める可能性がある。インタビューをして他人のストーリーを理解し新しい発見をするように、「自分史的エッセイ」を書くプロセスで過去の体験を再解釈し、自己理解を深める可能性がある。大学教育におけるライフストーリー研究は、単なる知識の獲得ではない、体験型の知を創造する可能性をもっていると言えるであろう。
祖母の涙
私は、A県のほぼ真ん中に位置する田舎の町に、二一年前に生まれた。家族構成は父、母、二つ上の姉で、親は共働きで二人とも公務員である。そのため、裕福でもなければ貧乏でもない、普通だが、かなり安定した暮らしをさせてもらっていた。
ただ、小さいころから父親が厳しく、遊びに行くのを規制されるなど、自分が思っているように事が運ばないことが多々あった。保育園、幼稚園、小学校は近所の学校に通っていたが、両親ともに割と教育熱心な方で、本ならすぐに買ってくれたのだが、おもちゃはほとんど買ってもらった記憶がない。そして、中学受験を嫌々させられ、中学校と高校は隣の市にある私立の学校に通っていた。
家族構成は現在4人だが、生まれてから一一年間くらいは、父方の祖母と祖父とも暮らしていた。しかし、小学校六年生のときに、事件があった。
その日の夜、母が仕事の終わる定時刻よりも、いつものごとく遅く帰ってきた。私は祖母が荷物をまとめている姿を目撃した。そして、「何かあったの?」と聞いた。すると、「もうおばあちゃん、この家に居れへんわ。お母さんの態度に耐えられへん」と言い、泣きながら私に抱きついてきた。
いつもニコニコしていて優しく、時に厳しい私の知っている祖母の姿と全く違い過ぎて、本当に衝撃的だった。そして、その後、祖父と共に今まで住んでいた、もう一つの家に帰ってしまった。そのときすぐには、何が起きたのか状況がよく読めなかった。
その原因は母だった。私の母は仕事が忙しいためか、土日以外はご飯をつくることがなく、弁当も祖母につくってもらわなければいけないくらいだった。そして、何かしてもらっても感謝や申し訳ない気持ちを言葉に表現することはほとんどなく、挨拶もほとんどない。母の祖父祖母との会話はほとんどなく、会話しなければならないときは、私の幼いころの目でも、面倒で煩わしそうに見えたほどだった。そんな母の態度は私が大きくなると、より一層ひどくなっていき、祖母はその態度に耐えられなくなり、家を出ることに決めたようだった。
そこから数年は父、姉、私とは一年に数回くらいは顔を合わせる機会があったが、母と祖母は数年ほど顔を合わせることがなかった。この一件から母の前で祖母の話をするのはタブーという空気になり、父も心なしか母に気を遣って不満を感じているような感じがした。
そして、私は家に帰ってきても誰もいない、今まで感じたことのないような寂しさを感じるようになった。今思えば、母がもっとちゃんと祖母に気を遣うべきであったと思うし、祖母も母に対して低姿勢で気を遣い過ぎだったとも思う。
しかし、こういった事件があったが、母は自分のせいで祖母が辛い思いをしたことは少しもわかっていないようであった。鈍感であるのか、悪いことであるという認識がないだけなのか、このときはまだ小学生であったが、家族であってもお互いが気を遣って生きていかなければいけないことを学んだし、自分の態度一つで相手を嫌にさせることがあるということも学んだ。
気を遣い過ぎても、自分が辛くなるだけなので、バランスは難しいが…。これは現在も、継続して心に留めていることである。そして、どんなときでも愛想よくし、相手に不快感を与えないようにつとめている。
別れのメール
前述のとおり、私は地元の公立中学校へは進まず、私立の中高一貫校に通っていた。中高一貫校のため、中三のときでも高校受験は、一般入試のような難しいものはなく、形式的に三年間のまとめテストのようなものが行われ、それを受けるだけで高校に楽に進むことができた。
転機は、中一から高二までほぼ同じメンバーであった中高一貫コースから、文理Ⅰコースという、他の公立中学校から一般試験で入学してきた、国公立私立大学を目指す生徒がいるコースへコース変更したことだった。
その高校二年生の一年間は、私が生きてきた二一年間で最も長く感じられた変化のあった一年であった。六年間中高一貫コースにいたのではなく、なぜわざわざ他コースを選択することになったのか、そのコース変更した経緯についてこれから話そうと思う。
私には、中二から高一まである同じ学校の同級生と二年半ほど付き合っていた彼氏で、Bという人がいた。しかし、高一の冬に倦怠期を迎え、相手からまさかの別れをメールで切り出された。嫌いになったわけではないが、友だちに戻ろうという理由であった。内心、自分は彼のことをまだ好きであったため納得はいかなかったが、意地を張って、「私もそう思ってた」とウソをつき、結局別れてしまった。
しかし、彼は別れたにもかかわらず、そのあとすぐに、半年ほど恋人のときのような関係を求めてきた。みんなの前では普通にして、と…。それでも相手がまだ自分を必要してくれているんだという気持ちで受け入れていたが、自分は次の彼女までの、ツナギとして利用されているのではと感じて、自己嫌悪に陥ったりもして、正直辛かった。そんな関係が高二の一学期まで続き、「誰にも言うな」と口止めされていたため、彼と私以外でその関係を知る人はいなかった。彼とは別れてしまったが、彼には私しかいないのだという感覚で、そのとき彼は自分のものであるんだという意識でいた。
そんな中、私が中一のころからケンカや仲間外れなどいろんなことがあったが、仲良くしてきていた親友とも呼べる友人のCという人がいるのだが、高二になってからBと急接近しているところを見てしまった。私に隠して付き合っているのかと思い、Cに「付き合ってないん」と聞いたことがあるのだが、「そんなわけないやん」と言って、否定されたため少しの間は安心していた。BとCは、私がBと付き合っていたときから、友人として仲が良く、CはBと私の二人の相談を受ける役として、なんでも相談していた仲だった。しかし、そんなCがBと学校の誰もいない教室で会っているのを、数回ほど目撃してしまったのだった。
そこから、二人の動向が気になった。今になって思うが、私はCに対して嫉妬心を抱いていたと思う。二人と私は同じクラスであったため、二人をできるだけ近づけたくないように行動していた。Cのことは前から信頼していたし、最も仲の良かった友人であったのだが、今回の一件で疑い深い気持ちをもって接するようになってしまった。
孤立
学校の友人とのおしゃべりは、それまで楽しいものだったが、全く楽しくなくなり、無口になっていった。その時期に修学旅行があったのだが、どの写真を見ても私があまり笑っている姿はなく、不機嫌な顔か不安そうな顔のどちらかであり、怖い顔をしていた。そんなせいか、周りの仲の良い友人たちに怒っているように見えたのか、こちらから話しかけなければ皆あまり話をしてくれなくなってしまった。
皆が私に対してコソコソ話をしているような感じがあり、そのときはちょうど、一学期の期末テスト最中とかぶっていため非常に辛かった。中一のときにクラスのほとんどの女子から無視され、コソコソと悪口を言われていたことがあったことを思い出し、その当ときの辛さをまた味わうことになると考えると、逃げたい気持ちになった。私は一つのことでも引っかかることがあると、それ以外の他のことに集中できないところがあった。テスト期間という大事な時期であるのに本当に苦しまされた。こんなことで悩まされている自分が本当に嫌いで仕方なかった。
そして遂に、そのテスト期間の最終日に体調を崩し通学中の電車の中で倒れてしまった。その日の朝、精神的に自分を追い詰めすぎて、どうとでもなってしまえばいいという思いでバファリンを通常の五倍服用するという、今考えるとぞっとするようなことをしていたためである。
一緒に登校していた友人に、学校の最寄駅で電車から担いで降ろしてもらい、学校に連絡し、救急車が来て、病院に搬送されることになった。昼を過ぎたくらいに、病室の中で目を覚まし、母親が隣にいることに気づいた。体に異常はないとのことで、病院を後にした。倒れてから意識を失ってしまっていたそうだった。その日のテストを受けることはできず、特例のため公欠扱いとなった。
次の日は日曜だったため、気楽に過ごすことができたのだが、月曜日に学校に行かなければならないことを本当に酷に感じた。あのまま意識を失ったまま、目が覚めなければ良かったと思ったほどだった。夏休みが近づいていたため、学校に行くのが少しだけであったが、それさえも苦痛で、どうやったら学校に行かずに済むかしか考えられなかった。夏休みが始まるまでは苦痛さを感じながらもなんとか学校に通った。
夏休みが終わって、二学期が始まってからも学校に行くことが苦痛にしか感じられず、学校にいるだけで蕁麻疹(じんましんん)が出ることが何回もあった。そして、授業中にも心の中の不安要素のことばかりを考えてしまい、落ちついていることができなかった。そのせいからか過呼吸や腕の痙攣(けいれん)などの症状を学校で引き起こし、倒れてしまうようになった。学校に行っても早退することが多く、学校のことを考えると家でもこの症状を起こすことが多くなり、学校を休みがちになっていった。そのせいで、私の学校は進学校で、ただでさえ授業進度が早いのに、どの授業もほとんどついていけなくなった。
不登校
「休む→授業ついていけない→宿題がおわらない→学校に行けない→休む」という悪循環の繰り返しであった。数学は数ⅡBの分野に入ってからほとんど赤点ぎりぎりであったのに、休むことで余計授業についていけなくなり、進級できるかが本当に際どいところでもあった。
BとCのことだが、私が休みがちになることで、教室の中でも、心おきなく仲良くできたようで、更に距離が縮まっているように見えた。自分は長期間休んでいたのに、Bが心配して連絡をくれなかったことは本当に悔しかったし、自分がこんなに辛い思いをしているのに、楽しそうにしている二人を見かけると、いらだちと自分の惨めさを感じ、やり場のない怒りがあった。
一一月くらいになり、Cに本当のことを聞き、自分の気持ちをすっきりさせてしまおうと思い、Cを保健室に呼び出し、「本当はBと付き合っているんでしょ」と聞いた。するとCは、「黙っていてごめん。傷つけたくないと思って黙ってたんやん」と言った。話を聞いていたら、Bが私に別れを告げたその後、二人は付き合うことになったようだった。つらい現実だったが、はっきりわかったことで少しすっきりした。そして、Bにも、「本当のことを聞いたよ」といった。すると、Bは、「Cが言ってきたから付き合っただけやし」という呆れた返答をしてきた。
Cは私にはっきり伝えることができたことを安心したようで、特定の人以外にも付き合っていることを知らせるようになり、私が今まで学校を休みがちであったのは、その事実にショックを受けているからだというような噂が女子内で流れるようになり(あながちウソではないのであるが…)、すっきりしたはずであったのに、また学校に行きづらくなってしまった。BとCと私の三人ともが同じクラスであるというのが本当に私にとっての不幸にしか思えなかった。なんでも相談できる友人がいたら良かったのだが、思えばこのとき私にはそんな相談相手がいなかったのも、考え込んでしまう原因であったと思う。
恋人関係の次に友人関係、それだけでなく家族内の関係も私の不登校が原因で悪くなっていった。
「また学校行かへんかったんか」「このままいったら進級できれへんようになるのわかってるんやろ」「このままずっとダメな人間であるんか」「学校に行かへん学生なんやったら、この家から出てけ、働け」など、父親から散々耳が痛くなるような言葉を浴びせられた。
母親からは、「お願いだから、学校行ってもらわなお母さんらも困る」と痛切に何回も言われた。しかし、体調不良や不登校の理由を親に相談できず、「行きたくないから」の一点張りで突き通した。
普通の高校生であれば、親に悩みを打ち明けると思うのだが、言いにくい理由もあるし、忙しい母親に悩みを相談したところで、ちゃんと相談に乗ってくれるのか疑問で頼りにできなかったからだった。父親は股関節が元から少し悪かったのだが、心身の疲れが原因で痛みが悪化し、より私を叱るようになり、母もどうしたら私が学校に行くようになるのか全く分からず、困惑していたようであった。
後になってから父から聞いた話であるが、母は私が不登校になりだしてから、寝る前に毎晩のように泣いていたらしい。この話を聞き、母に一番迷惑をかけていたことを知って、申し訳なさでいっぱいになった。当時、母は仕事人間で、家に帰ってきても自分の時間が欲しいだろうから、私の話なんかしたら、面倒くさがれてちゃんと話を聞いてくれないだろうと、諦めの思いがあった。しかし、泣かせてしまうくらいなら、ちゃんと話すくらいでもしていたら良かったと後悔した。本当に高二のときは今までの人生で一番迷惑をかけた一年であったと思う。
コース変更
一二月になり、担任の先生からこのまま休み続けると出席日数が進級や卒業に関わってくるし、最もネックである数学を中高一貫コースでやっていくのは今の学力だと厳しいのではないかと言われ、三教科型の国公立と関関同立(関西、関西学院、同志社、立命館)を目指すコースへの変更を勧められた。全く違うメンバーの中で、人間関係も勉強も心機一転し、新しいクラスでやってみないかとの提案である。
三教科型のクラスに変更すれば、今まで悩まされてきた数学の授業を文系の私は受けなくてもよく、高一のころの数学の成績しか反映されないため、卒業のことを気にせずにやっていけるということだった。同時に、今までやってきたセンター対策のための七教科型国公立ではなく、三教科型国公立や関関同立を目指す勉強をした方が、身体への負担は少なくなるとも言われた。決断は早い方がよく、年内のコース変更を勧められた。
高二になってからは中高一貫コースにいることで、身体の調子が悪くなるほどまで、悩まされたことが多々あり、憎しみの気持ちもなかったわけではないが、いざ他のコースに行くことを考えるとなると、中一からの楽しかった思い出が頭に浮かび、全てが悪いわけではなかったとも思い、自分が約五年間も在籍した中高一貫コースに思い入れがあったのだと感じ、他のコースへの変更に、すぐに踏ん切りがつかなかった。
躊躇していると担任の先生からまた呼び出しがあり、行ってみると、「迷っている時間はないし、本当にこのまま今のコースに居続けるのだと進級できなくなってしまうのは目に見えてる。あと、自分の身体の調子にしても、七教科をこれから続けていくことは体力的にもどうか。身も心も元気な状態で勉強できることが最良。生徒たちは、中高一貫コースから他のコースに移動することは、レベルが下がったという誤った認識を持っているけど、コース変更したって友だちでいてくれるやつは本当の友人で、どのコースに行ったって、結局勉強をして志望校に行くというのは同じことやで、本当に早く決断しろ」と言われた。
三者面談があり、その場で担任の先生が親にもコース変更の説明をし、親とも相談して、年明けの三学期が始まってからコース変更をすることが正式に決定した。決定してからも、はっきりとコース変更するというふん切りがつかなかったが、仕方ないことだと割り切って、これから勉強に身を入れようという決心が最後にはついた。
そして、年末最後の授業のときに、担任の先生がホームルームの時間にみんなの前で、私がコース変更するという連絡をし、クラスの皆にもコースを変更して、別のクラスに行くということが伝えられた。
裏切りの謝罪
その事実を事前にわたしから伝えていた人は数人いたため、女子には結構知られていたようだったが、男子は全く知っている人がいなかったため、その発表が終わってから、結構仲の良かった男子の友人たちが声をかけてきて、「まじか、知らんかったし。でも、あっちに行ってもがんばってな」という声をかけてくれた。女子にはそんなあっさりとした言葉をかけてくれた子は一人もおらず、その後女子は気まずそうにするか、あえてその話題に触れないという子がほとんどだった。男子がかけてくれた言葉は軽い言葉であったが、私にとっては不思議とすごく背中を押された言葉であった。このときに、男子って友人関係とかもフランクで、自分が男子だったらこんないろいろ悩まなかっただろうにと、男子がうらやましかった。
その日の夜、寝ようとすると急にCから電話がかかってきた。そして泣きながら、「コース変更、あたしのせいやんな。本当にごめん。Bと別れようと考えたこともあったんだけど、無理だった。本当にごめん」という、弁解の電話があった。
今さら謝るのかという怒りの気持ちをおさえながら、「そういうのは理由じゃない、進路を変えるだけだから」と答え、半年ぶりくらいに普通の会話をして、電話を切った。自分でもびっくりするくらい、Cと普通に会話することができた。正直、一番大好きだった人を一番仲の良かった友人にとられるというのは裏切りであるし、一生許したくないと思っていた。しかし、一生恨むことで自分に利益はないと考え、すっきりとした関係になればいいんや、と割り切ることができた。
そして年が明けて二〇〇九年になり、ドキドキの新しいクラスを迎える一年が始まったのだった。渡してもらった、冬休み課題を済ませ、学校が始まる一月六日は本当に緊張で、何日も前からドキドキだった。ついにその朝、新しいクラスの担任(現代文の授業でお世話になっていたため、実は何回も喋ったことがあった)、に挨拶をしに行き、新しいクラスの子が二人(その二人は当時、学級委員をしていたためだったと思う)、自己紹介をしてくれ、「お迎え」に来てくれたのだった。前いたクラスから自分の机とイスを持っていくことになり、その二人にも運ぶのを手伝ってもらった。教室に入ると、ほとんど見たことのないメンバーばかりで、一斉に視線を浴び、かなり緊張した。
以前中高一貫コースに在籍していた男子の友人二人を見つけ、少し話すことができ、うれしかった。ホームルームの時間になり、新しいクラスの担任がやってきて、私の名前を黒板に書き出し、「前で自己紹介してや」と言われ(まじか、なんか転校生みたいな扱いやん、と思いながら)、前に出て「中高一貫コースから来ました、○○です。ずっと中高一貫にいたので、こっちのクラスのことが全然分からないんでいろいろ教えてください」と言った(緊張しすぎて口がまわらず、噛み噛みになってしまったので、とても恥ずかしかったのを覚えている)。
そして先生が、「ずっと中高一貫におった子やから、まるで転校してきたみたいな気分やと思う。不安なことがいっぱいやと思うから、みんな仲良くしたってな」と言ってくれ、ありがたいお言葉だったのだが、挨拶を噛んでしまったことが気がかりで恥ずかしさでいっぱいだった。
カルチャー・ショック
一日目はお昼までの授業でどんなことをしたのかあまり覚えていないのだが、一番後ろの席であったため、どんな人がいるのかなと人間観察していた。私は中学生のとき、剣道部に所属していたのだが、近隣のいろいろな中学校の剣道部が集まる大会で何回か見たことのある元剣道部の子たちが何人かいた。少しでもつながりのある子を発見することができて、ホッとしたことを覚えている。その中の一人の子に勇気を出して声をかけ、「剣道部だったよね」と言い、一日目であったが初めてそのクラス内に新しい友人ができた。
一日目は緊張でクラスの雰囲気を知ることくらいしかできなかったが、クラス内の仲は男女共に全体的に良く(いじめではないが男子が女子をどついたり、からかうという光景を見たりした)、お弁当を食べるときも、ある一定の人とだけ集まって食べている子もいるが、ほとんどの人が自分の席から離れず、男女問わず、近くの席の人と話しながら食べていたのに、良い意味でカルチャーショックを受けた。席を移動するのが面倒だということもあるが、もとある友人関係に固執せずに自分の席に座って食べる姿勢を見て、なんて気が楽そうなクラスなんだろう…と思ったのを覚えている。
また、女子間でもはっきりと物事を伝え、女子特有のねちっこい関係というものが全く見られなかった。自分が今までいたクラスと対照的な部分が多く、数日で新しいクラスのことが好きになり、もっとクラスの子たちと仲良くなりたいと思うようになった。
そこからは人見知りをしないように心掛け、授業は現代文と世界史は文系メンバーで受けるのだが、その文系メンバーと仲良くなり、友だちの輪も広がっていき、最初の一週間は不安でいっぱいだったが、学校が徐々に楽しくなっていった。勉強の方も、落ち着いて打ち込むことができ、最初のテストもまずまずの出来であった。三年の一学期が終わるころにはクラスの全員と話せるようになり、女子だけでなく、男子の仲の良い友人も何人かできた。男子の友人が何人かできたことで、いじられキャラが定着し、何回もしょうもないことで皆にいじられていた。
友だちとの付き合い方も以前とは変わり、特定の人と仲良くなるのではなく、いろんな人とかかわり、話すことで自分に合った子とさらに仲良くなっていこうと思い、新しいクラスに入ってからは友人関係で悩むことはほとんどなかった。男子のようにさっぱりした性格の女子が多かったことも理由であると思う。楽しい思い出が多くありすぎて、どれか一つを選んで書くことができないくらいだ。
「ありがとう」
長々と書いてしまったが、コース変更し新しい環境に行くことで私は、自分も新しい自分にすることができた。友だちの付き合い方や授業への取り組み方も変わったし、今までの細かいことに固執する自分の視野の狭さを実感し、視野を広く持てるようになった。そして、両親からは、学校に行くのが楽しそうになったし(実際にコース変更してから、欠席したのは二、三回ほどしかない)、のびのびしているし、本来の私の姿になったのではないのかと言われた。
コース変更することになった理由は、端的に言えばBやCのせいであったが、このコース変更がなければ私は、世界が狭いまま今に至ったのではないだろうかと思う。そう思うと、辛い思いをしたが、逆に二人には新しい環境に行くことにさせてくれて、ありがとうという気持ちになれた。
クラスが替わって、毎日、本当に楽しく過ごせたのは、自分の力ではなくて、先生やクラスのみんなの人のよさのおかげであったと思う。消費者金融か何かのCMで、「ピンチをチャンスに」という言葉を聞いたことがあるのだが、この件に関しては、まさにこの言葉が当てはまっていると思う。どんな状況も自分にとってマイナスになりえるし、プラスにもなりえるのだということを学べた。
コース変更してから仲良くなった男子女子含めた友人たちとは、今でもツイッターなどでよく話したりするし、飲みに行ったり、大阪方面に行ったときに遊んだり(ほとんどの友人が京阪神方面の大学に進学したため)、大きな休みがあるときには必ず誰かに会うほど、今でも仲良くさせてもらっている。そして、毎回と言っていいほど、私の何かに対してツッコミが入り、いじられる…(笑)。
一方、中高一貫コース時代の友人で頻繁に連絡をとるのは一人だけである。しかし、無理して合わない人と付き合うことの方が苦痛であるので、一人の友人と連絡がとれて気楽に二人だけで会うので、私にとっては充分であるし、この一人の友人を通して、男子二、三人が主催してくれる飲み会に誘われるので、友だちは少なくても案外大丈夫だし、楽しいです(笑)。
編入試験の合格
私は高校を卒業後、Y県にある公立短期大学へ入学した。高三のセンター試験を大失敗し、志望していた三教科型の国公立の二次試験を受験することはできなかった。また、「関関同立」の一般入試もいくつか受けたのだが、全て失敗した。私の通っていた学校は大学附属であったため、内部生の特権としてその大学の試験を校内で受けることができ、そこで一つ合格を得た。しかし、私立大学の入学金や授業料を知り、唖然とし、親には私立に行かせることはできないと言われた。
そこで公立の短期大学や大学校があることを知り、センター試験が終わってからの時期でも出願でき、自分の興味あることに少しでも近い、学校を必死に探した。そこでヒットしたのはX短期大学部というところと、私が後に入学することとなったY短期大学だった。どちらにも出願をし、Xの方はセンター試験の結果利用方式で、Yの方は独自一般試験があるとのことで、Y県までZから新幹線に乗って出向き、試験を受けた。
結局どちらも合格し、より自分がしたいことに近いことが学べるY短大の方に入学することに仮決定した。しかし、Y県は遠すぎるし未知の場所であるし、周りが皆四大に行っている中、短大にいくのは…という思いがあり、浪人することも考えたのだが、浪人も賭けであるし、お金が私立に行く並みにかかると言われ、私の性格的にも追い込まれるのはやっていけないだろうということで、浪人は反対された。
そして、Y短大の入学金振込二日前まで悩み、パンフレットを眺めていた。すると、短大から四大へ編入する制度がありことを知り、短大を出たら就職して終わりとしか思っていなかった私にとって希望の光が見えた。親にもそのことを話し、絶対に合格できるか分からないけど、短大に入ってから編入試験に向けてがんばってみようと思うから、やはり九州の短大に入学するという意思を話した。親もこのご時世で就職するなら四大を出ていた方が良いと考えていて、絶対に最後まであきらめないという約束で短大に入学した。
入学してから、何も知らない地での生活は本当に慣れず、ましてや住んだこともない九州で実家から片道で半日もかかる場所にYはあるため、普通の土日休みに帰ることは無理であるし、新幹線を使うとなるとお金がかなりかかるので、大きな休みのときくらいしか実家には帰ることができず、寂しい思いを一年の前期はよくしていた。しかも、私の通っていた短大は地元、Y県の高校からの入学者が多く、同じ高校同士で友人も固まってしまうため、本当に前期のころは友人ができず、大きな休みに地元に帰り、高校の友人たちと遊ぶことが楽しみの一つであった。
しかし、夏休み明けにアルバイトを始めたこともあり、徐々に土地にも慣れていき、後期からは気のあう友人やサークルの友人ができ、だんだんと学校が楽しくなっていった。
そうこうするうちに、進路決定の年の二年生になり、私は短大入学のきっかけとなった四大への編入である進学を迷わず選択することにした。二年になり、授業は一年のときよりは少なかったが、厳しい研究室であったため卒論の準備が大変で、しかもバイトも結構入っていたので忙しい毎日を送っていた。九月くらいから編入試験が始まるため、夏休み前くらいには大体の編入試験で課される、英語と小論文の勉強を開始し、夏休みはお盆くらいしか、実家に帰らず、夏休み中は毎日図書館に通うようにした。
そして、面接の練習もいろんな研究室の先生に練習に付き合ってもらい、小論文の添削も何回もお願いし、数をこなして慣れていった。D大が第一志望であったため、夏休み中に開催されたオープンキャンパスにも行き、アポをとっていた教授の研究室にお邪魔し、D大のいろいろなお話を聞くこともできた。
祝福
その甲斐あってか、滑り止めで受けていた大学も合格し、第一志望であるD大に合格することができた。高三のころの私では、センターの点数が足らず絶対に行けなかった大学に合格することができて、自分でも本当にびっくりした。合格発表の日の夜に父に電話すると、今までにないくらい喜んでくれた。そして、卒業後も進路のことを何かと気にかけてくれていた、高二、高三からの担任にも電話をし、合格報告をするとても喜んでくれ、これから頑張るんやでという言葉をかけていただいた。
また、研究室の先生にも「本当によかった! すごい! おめでとう!」と言っていただいた。高校のときの友人や短大の友人も合格を自分のことのように喜んでくれ、自分の合格だけでこんなに多くの人を喜ばすことができるということが何よりもうれしかった。
この編入試験への合格を機に、一つのことに対して目標を持ってそれに向かってがんばるという姿勢がいかに大事かということを学んだ。そして、正直高校生の自分は不完全燃焼であったな、と思ったし、努力しなければ何もつかめないことを実感することができた。
また、編入試験によりD大へ入学できたことで、留学生支援サークルに入り、私の長年の夢だった外国人留学生と友だちになるという夢がかなった。後期になってからはしていないが、留学生チューターをすることで、日本語を教え、相手の国の言葉も勉強できるという貴重な体験をすることができた。
そして、学部はバラバラであるが、自分と同じ編入生という立場で親しくなることができた編入サークルの人たちとの出会いが、私の学校生活を充実させてくれている。そのサークルの中で知り合った友人はこれから卒業してもずっと仲良くしていきたいと思える人たちばかりであるし、その中で出会えた今の彼氏との出会いは本当に編入したからこその出会いだった。
自分史を書いて自分の二一年を振り返ってみると、あのときはこう思っていたが、今は違うといったことが多かったし、自分が少しずつでも成長しているなと感じた。また、今いる周りの人を大切にしていきたいと思った。そしてこれからも「ピンチをチャンスに」変えることができるような人生をおくっていけたらと思っています。
