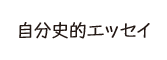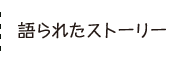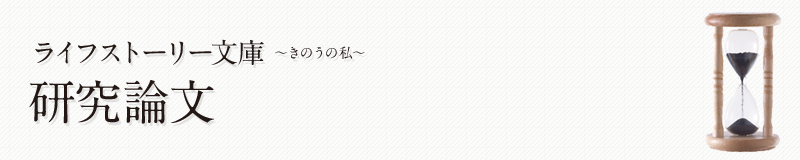
運営:椙山女学園大学国際コミュニケーション学部「ライフストーリー文庫~きのうの私~」編集室

| 2013.04.30 |
ライフストーリーセンター構築によるストーリーの社会学的研究 第2章 ライフストーリーのウェブ公開 |
(横家 純一) |

1.はじめに
これまでわれわれは、紙媒体による編集・製本という作業により、ライフストーリーの作品を発表してきたため、こんかいの電子媒体によるウェブ公開という、まったく新しい企画の遂行においては、多くの困難に直面した。ここでは、これまでの作業をふりかえりつつ、その問題点のいくつかを紹介したい。
関係者の尽力のおかげで、表1、表2のように、3年間で、合計43点のライフストーリー作品を収集し、ウェブ公開することができた。その内訳は、「語られたストーリー」13点と、「自分史的エッセイ」30点である。
前者の「語られたストーリー」は、聞き手の要請をうけて語られたものを、主に編集者が編集したもので、そのうち8点は、男性の語り手によるものである。インタビュー調査の記録であることから、自分史的エッセイよりも、あきらかに、実現しにくい。それは、語り手との共同作業が前提となり、相手の都合(ここには、意欲や話好きかどうかということも含まれる)が絡むからである。しかし、いったんそのハードルをのりこえると、他者との相互作用の醍醐味がえられる、ということでもある。
後者の「自分史的エッセイ」は、まず筆者によって書かれ、筆者または編集者によって編集されたもので、全員、女性によるものである。これだけの作品が集まったのは、ひとえに、授業での課題としたからにほかならない。ウェブページでの公開だからといって、ひろく一般からの投稿をつのることは、容易ではない。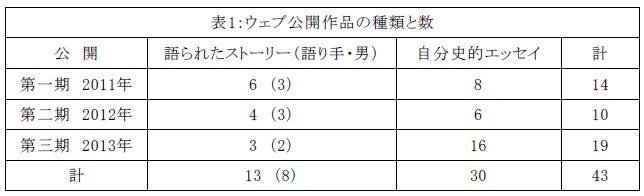
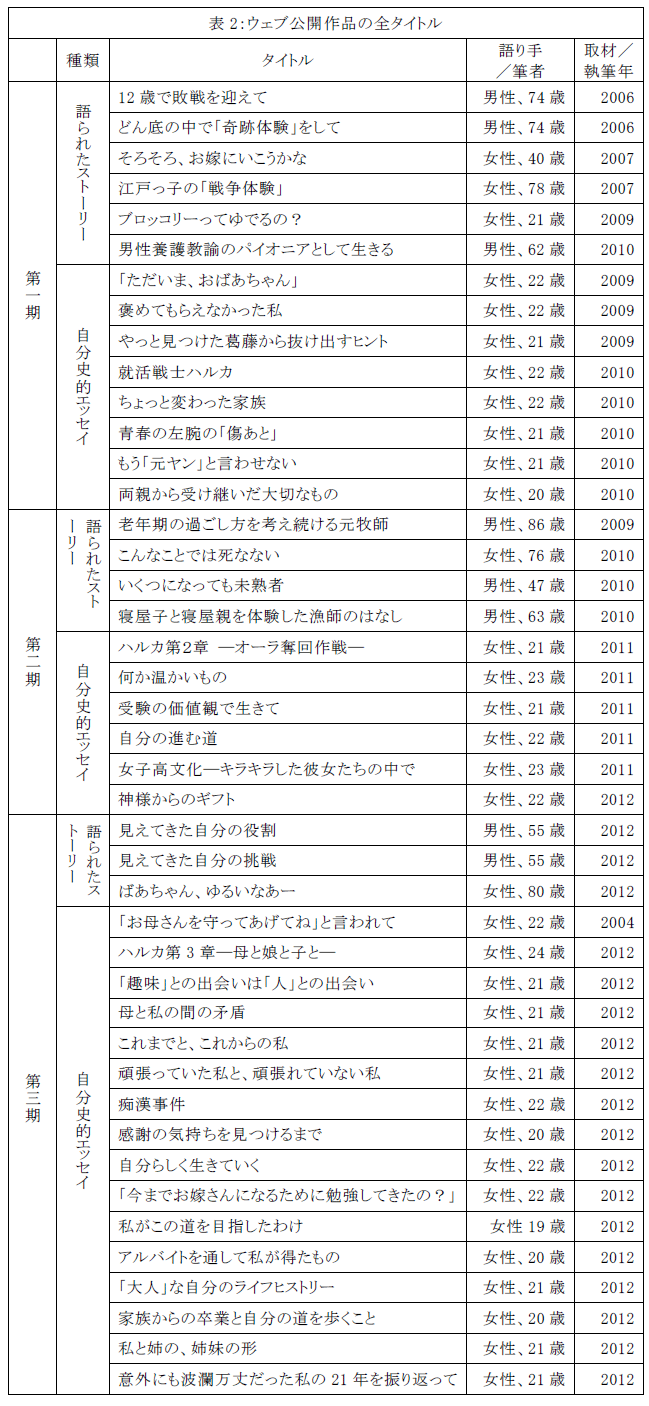
1. ウェブページの構成
電子ファイルとして提出された原稿は、数回以上の校正――なかには、幸運にも筆者や語り手自身による校正が可能だったものもある――を経て、作品となる。こんかいは、読みやすいタテ書きのPDFファイルと、ケータイなどの端末ユーザーのためのHTMLファイルの二種類を用意した。ただ、この“サービス”が奏功したのかについての確認はしていない。
構成で工夫したことといえば、第一画面で、各ストーリーのテーマを象徴する「タイトル」、および、読者をひきつけるための「リード」(表3)を配し、読者がすばやく目的の作品にたどり着けるようにしたことである。また、それぞれの作品の冒頭には、「あらまし」(表4)をおき、作品内容の、いわば〈予告編〉を提供することで、読みこみの動機づけを行った。
さらに、長い作品を2回のシリーズ物にし、読みやすさとウェブの動きを追求するといった工夫もしてみた。たとえば、第一期の「12歳で敗戦を迎えて」と「どん底の中で「奇跡体験」をして」は、一つの「語られたストーリー」を二つに分けたものであり、「就活戦士ハルカ」(第一期)と「ハルカ第2章―オーラ奪回作戦―」(第二期)は、一つの「自分史的エッセイ」を二つに分けたものである。いずれも、結果的にどうだったかという検証はできていない。
いまふり返ってみると、「リード」はともかく、「あらまし」の作成は、本文の校正作業と重なり、時間的にどちらを優先するかという問題をかかえることになった。その結果、第三期では、「あらまし」をつけないものが多くなったが、これも、やむをえない選択だった。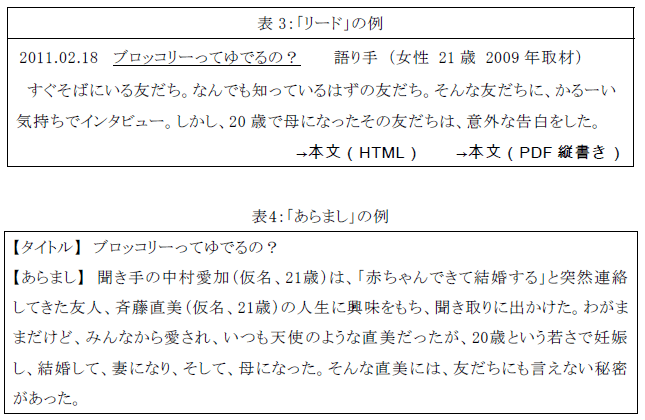
こまかいことだが、英数字の処理は、容易ではない。たとえば本稿のように、ファイルすべてがヨコ書きであれば半角のままでもいいが、タテ書きの場合は読みにくい。タテ書きのみの場合を考えたとしても、漢数字にするのか全角のアラビア数字にするのかといった判断は、いまだに、決着がついていない。
ここで技術的な問題として一つ報告しておきたいことは、こんかいのように、一つの原稿をPDFとHTMLの二種類のファイルとして共有したとき、変換のさい、バグが発生する危険があるということである。たとえば、ルビつきのワード文書をHTMLファイルに変換すると、いうまでもなく、ウェブ上の文章は、ぐちゃぐちゃになる。これを避けるためにわれわれは、やや見ばえは落ちるが、○○(△△)といった形で、○○の漢字のあとに、△△のルビをカッコつきで表現した。
漢字変換については、たとえば、「出来る」は「できる」に、「事」は「こと」にすることで、読みやすさを追求したが、「時」「頃」「今」「行く」「来る」「言う」「見る」などの場合は、一貫性の追求はあきらめざるをえなかった。あるときは漢字で、またあるときは、ひらがなとなった。かといって、それがデタラメかというとそうでもなく、漢字が続くときは、ひらがなに変えるといった、作品の読みやすさを追究した結果といいたい。
2.プロの編集
ホームページの運営一般にいえることだが、より多くの読者を獲得するためには、ウェブ・ページが「動いている」ことを印象づける必要がある。そのためにわれわれには、精力的な編集が求められたにもかかわらず、年一回のウェブ公開、つまり「アップ」が限界であったことである。とはいえ、第一期は、プロの編集者の力を借り、文章表現を洗練させ、作品の完成度を高める工夫をしてみた。たとえば、第一期作品の校正例を一つ紹介しよう。
プロの編集者が手を入れたところを、ゴシック体にしてみた。ここでは、3点のみ指摘しよう。まず、タイトルを「『元ヤン』の私」から、「もう『元ヤン』と言わせない」と変えたこと。「元ヤン」という強烈な言葉を生かしつつ、名詞で終わっている弱点を克服する仕掛けを用意している。静態的な前者にたいして、後者は、読者に向かって叫び、訴えている動態的な感じがする。あきらかに、その効果は、絶大である。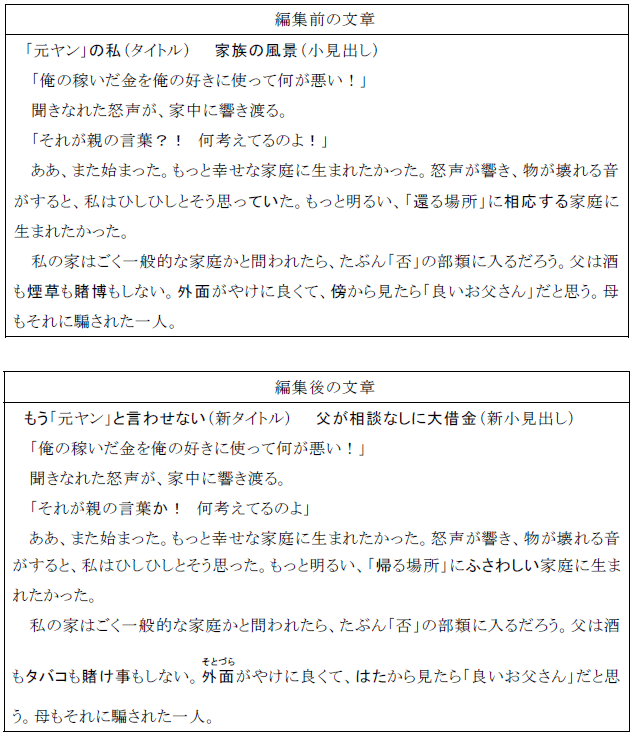
つぎに、「家族の風景」を「父が相談なしに大借金」という小見出しに変えたのはなぜか。あきらかに、前者が、どこにでもある一般的な事象の説明となっているのにたいして、後者は、これから始まるストーリーの前説(まえせつ)――読者を話の内容に惹きこむ仕掛け――として、きわめてインパクトのあるものになっている。さすが、プロの目のつけどころ、と言ってしまえばそれまでだが、おそらく、そのような選択ができたのは、「『元ヤン』の私」という文章を何回も、何回も読みこんで、その筆者の叫び声をきき、それに共振することができているからにほかならない。
もう一つは、煙草を「タバコ」とし、外面に「そとづら」とルビをふっている点である。いきなり、タバコとくれば、漢字の読みにわずらわされることはないし、ともすると「ガイメン」という、意味をなさない音が出てきそうな漢字にたいして、ソトヅラと援護することで、文意をよりはやく正確に伝えることに成功している。そればかりか、そのような表音のカタカナ語は、読者に、筆者が自分のストーリーを創作するために、頭の中で発話したときの〈息遣い〉までを運んでいる。
3.編集の理念
自分史的エッセイにせよ、語られたストーリーにせよ、ストーリーである以上、曖昧な部分は残る。その多義性をそのまま残せば、読者に敬遠されたり誤解されたりするおそれがある。それを避けるために、あえて、編集者の判断で、できるだけ一義的に洗練させることにした。
そんなことはできるはずはないとか、そんなことはしてはいけない――というヴァレリー・ヤウ⑴のような反論も聞こえてきそうだが、ここには、せめてなんとか、こんな生き方をしている人がいる、ということを知ってもらいたいという〈祈り〉がある。それが、「越権行為」であるかという議論は、別の機会にゆずりたい。
ただし、自分史的エッセイは、書かれたものであり、編集者といえども、安易に修正することは許されない。どうしても、書き手にさし返すことができないものは、たとえ、文章表現が乱れていても、慎重に取り扱った⑵。このことは、自分史的エッセイを、いったん、語られたストーリーと同じ水準で、つまり、文章の一義性を重んじた――これをかりに、「第一水準」とする――校正をしていくうちに、「なにか違う」という感じたことからヒントをえた。そのため、さいど原文にさし戻し、こんどはややゆるい、いわば「第二水準」で校正することで、結果的に、エッセイ表現のもつ、〈ゆれ〉を包摂する独自の世界に光をあてることになった。つまりそれは、相手がいる前で語られたものは、もはや、取り消しや訂正はできないが、書くために自分の頭の中で反すうしているうちは、何度でも修正がきくという、自由な世界なのだ。
その過程で一つのおもしろい発見があった。ある6600字ほどの作品に、「わたし」という表現が頻繁に出てくるので、数えてみたところ、なんと72回もの「わたし」が使われていたのである。このこと自体は、別の視点から考察することができるはずだ。ここでは、「私」という漢字で統一することで、語り手にとって特別に大切な自分というものを強調してみた。もちろん、「わたし」というひらがな書きの方が、自分の強調になる、と考えることもできようが。
注
(1)ライフストーリー・インタビューの記録を、歴史的な情報とみなすヴァレリー・ヤウは、トランスクリプトの作成について、「意味があると思われるものはすべてそのままにする」(『オーラルヒストリーの理論と実践』、インターブックス、2011:385)と主張している。
(2)とりわけ、第三期の編集では、それまでと比べて、たとえ平凡なタイトルであっても、筆者のあつい思いがこもっているものには、あまり手を加えない方針をとった。その結果、書かれている内容の核となる部分を象徴しない、ややもの足りないタイトルになっているケースもある。学期途中であれば、この点について、筆者との対話や相談も可能なのだが。