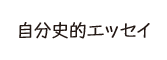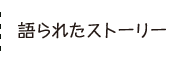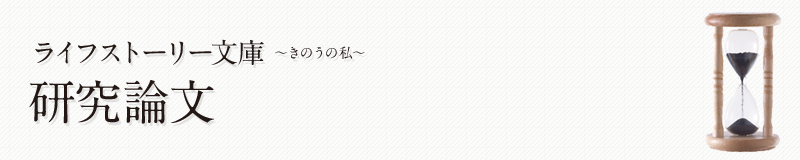
運営:椙山女学園大学国際コミュニケーション学部「ライフストーリー文庫~きのうの私~」編集室

| 2013.04.30 |
ライフストーリーセンター構築によるストーリーの社会学的研究 第7章 物語としての「自分史的エッセイ」の教育実践とストーリーの社会学的分析の可能性 |
(塚田 守) |

はじめに
この章では、「自分史的エッセイ」の教育実践のまとめと、物語としての「自分史的エッセイ」の社会学的分析の可能性について書いている。
第1節では「自分史的エッセイ」を授業の課題としている「ライフヒストリー研究A」(半期科目)は何を目的として授業がなされているのか。また、実際にどのように授業が運営され、学生がどのように参加しているのか。物語としての「自分史的エッセイ」を書くプロセスはどのようなものであったか。授業という場でそのようなエッセイを書くことの効用と満足とは何か。さらに、「ライフストーリー文庫~きのうの私~」との関わりに触れ、ライフストーリー(自分史的エッセイ)を用いた授業の可能性について考えている。
第2節では、「ライフストーリー文庫」に掲載されている、学校教育の過程で「偏差値」にこだわって生きた二人の学生の「自分史的エッセイ」を事例として取り上げ、物語としての「自分史的エッセイ」を独立したテキストとして提示した上で、社会学的分析を試みている。また、物語として、テキストとして「自分史的エッセイ」を読み解くことで、共通のテーマとは何かを考察し、テーマを一つに限定し、さまざまなデータを使う横断的な社会学的分析とは異なった分析を試みる。具体的には、二人の学校体験を自分史という時間軸を考慮し、その時間軸が学校文化とダイナミックに交差する中で起こる、「自己変革」のストーリーの社会学的分析の可能性を考えてみたい。
1. エッセイを書く授業の実践
(1) 「ライフヒストリー研究A」という授業の内容と目的
「ライフヒストリー研究A」は、『私たちの中にある物語』にある、個人史の書き方を学び、今までの自分の人生でもっとも意味あると思われる体験について「自分史的エッセイ」を書くことを通して、「いままで語ることのなかった事」を語ることで、「今までの自分」とは異なる「新しい自分」へ変わる一つのきっかけを作ることを目的としている。
自分の体験を書き、語ることには変革的機能があるということを前提にし、この授業を通して、受講者の「自己変革」が起こることを期待し、「ライフヒストリー研究A」のシラバスには以下のように書いた。
この授業では、ライフヒストリーの社会学の視点から、人の人生における転機に焦点を当て、
人の生き方とはどのようなものかを考察する。授業の前半では、ロバート・アトキンソンの
『私たちの中にある物語』について講義し、人びとがストーリーを語る意味を理論的に整理し、
その理論を理解した上で、自分的エッセイをどのように書くかについての実践的方法を学ぶ。
後半では、同世代の自分史的エッセイを読み、解説し、身近な自分史的エッセイをどのように
書くかについて講義する。最後には、受講生たちの書いたエッセイを授業で読み、相互にコメントを
しながら、それぞれの人生を考え、自己理解を深める。
授業の方法としては、相互に議論をする参加型をめざすものである。受講生たちは、事前学習として、前半では、『私たちの中にある物語』の該当する章と配布された自分史的エッセイを読んで授業に臨むことが期待されている。また、授業を履修している学生は、学生自身が書いたエッセイを授業時間中に全員で読み、コメントあるいは感想を言うことも期待されている。
この授業では、前半では、該当の章と配布された自分史的エッセイに関するリアクションペーパーを提出し、後半では、自分が書いたエッセイの草案を随時、担当教員に提出することになっている。よって、すべての受講生は、「自分に関わるテーマでエッセイを書くことが必修課題となるので、書きたいテーマをもって履修すること」という条件で、履修することになっているので、履修する学生は、すでに「語りたい、書きたい物語」が曖昧な形であれ、自分の中にある学生だと言える。授業で「自分的エッセイ」を書くことが必須だとわかった段階で、授業の履修を取り消す学生は2~3人いる。しかし、履修した学生は、自分が書いたエッセイが読まれることを前提にし、書き、担当教員に提出して初めてこの授業の単位が与えられるので、全員が「自分史的エッセイ」を書くことになる。
(2) 学生の中にも「語る物語」はある
一般的に自分の個人的な経験をあえて話したいとは思わないと理解されているが、どんな人、どのような年齢であっても「語りたい物語」を心の中にもっているということを前提にこの授業を始めている。
アトキンソンが言っているように、「ほとんどの人はたいていの場合、自分の話を聞いてくれる人、自分の話に興味を示してくれる人を必要としているので、そのような機会があれば、自らの自伝を喜んで語るであろう」(2006:172)。たとえ、それが1970年代の極左翼連合赤軍のメンバーやテリアビブで集団銃殺テロ事件の犯罪者であろうと、「判断されず自分の話を聞いてくれる人がいれば、かかわった事件に関する物語を話すものである」と言ったのは、戦前の転向問題を研究し、1970年以降は、連合赤軍メンバーのインタビュー調査を、それぞれの囚人の拘置所で何度もインタビューをしたスタインホフ教授である(1986年)。また、筆者が15年以上続けている教師のライフストーリー研究で、「あまり話すことはない。私よりもっと適任な人に話を聞いた方がよい」と言っていた先生たちが、自分の若い頃の教師体験、今の自分の教育哲学、価値観などを、インタビュアである筆者に長時間語ってくれた(1998、1991)。それは、アメリカ人の教師も同じであった。インタビューの最初は、日本から来た身知らぬ研究者にアメリカの教育について教えてやろうという話ぶりで話していたが、その内、自分が生きてきた社会、個人史などを語り始め、その人の人生の中のもっとも「意味ある体験」を筆者は聞くことができた。その中には、長い間自分の中で封印していた学生時代の「公民権運動への関わり」に関する語りもあった。それらは、聞かれなければ語られない物語であった(2008:82-84)。
そして、自らの人生の「意味ある体験」を語り終わった後、多くのインタビュー対象者は、自らの「人生の語り」をインタビュアである筆者に語ったことに満足した、という発言をした。曰く、ヒスパニック系のある教師は3時間ほどのインタビューを終えた後、「こんなインタビューだったら何回でも受けるから、いつでも声をかけてください」と言ってくれた(2008:324)。あるいは、自分の経験を話し、自分の人生をふり返ることができ、インタビューをもとに書かれた「自分史」を娘や息子に読んでもらうことができて良かったと、自らの「ライフヒストリーを語る」意味を積極的に評価してくれた教師がいた(1998:483-384)。聞かれて初めて話し、そのように話したことで、自らが言葉にしてこなかったことを語るプロセスを通して、一つのまとまった「人生の物語」を語ることができたことに満足することができたと言ってくれた、インタビュー調査の中で出会った教師たち。彼らも「語る物語」をもっていたのである。
しかし、ある程度長い間生き、さまざまな経験をもった教師たちとは異なる、20年前後しか生きていない学生たちには、「語る物語」はないのでは、と思う人も多くいるであろう。実際は、年齢に関係なく、今生きている私たちは、それぞれの成長段階で、「語る物語」をもっていることは、「ライフヒストリー研究」「人間論」を履修した学生によって書かれた「自分史的エッセイ」あるいは、創作的「卒業研究」として書かれた自分史を読んだ経験から言える。いじめ体験、いじめられ体験、学校教育での葛藤、家族のこと、友達のこと、非行体験、性同一性経験、親の死などについて書かれたものを筆者は読んできている。20年間生きてきたにすぎない学生たちの中にも、多様な「人生の物語」があった。もちろん、年齢層が上の世代で経験されるほどの多様なものではないが、筆者が社会学研究の知見から理解していた家族問題、学校問題などとは異なったレベルの、生き生きとした物語が「自分史的エッセイ」として書かれていた。
「学生たちにも語る物語ある」という前提で、その物語を聞く、読む機会としてこの授業を展開している。一般的には、自分史は本人が書きたいと思い、何らかの動機があって書き、何らかの手段(自費出版、自分史サークル、自分史の文化講座で作られる冊子、ブログ、ホームページなど)で、自主的に書くことはありうるが、授業の中で課題として出された「自分史的エッセイ」を、学生がどれだけ本気に書くのかという疑問があるかもしれない。しかし、実際に授業をやってみると、自らの人生上の意味ある体験について考え、熱心に書いたレポートを読むことができている。そして、筆者には、それらの書かれた「自分史的エッセイ」は単なる課題以上のものだと思えた。そのような授業の経験から、学生たちにも「語る物語」をもっていると確信するに至った。そして、そのことは既に、この報告書の第1章でくわしく描写したように、実際、アトキンソンも大学院の授業でやっていたことを、後で知ることになった。アトキンソンが著書の中で議論を展開しているように、だれの心の中にも「語る物語」をもっているという前提で、この授業も展開してきている。
(3) 授業の実践の内容―授業の段階的展開
半期の授業で、実際にどのような流れで行われているかについて具体的に描写する。
第1段階: 物語を書く、語る意味についての講義と話し合い
まず第1段階である最初の数回の授業は、「物語を書く、語ること」の意味と機能について、教科書として用いているアトキンソンの議論を読むことを課題として与え、その章の内容に解説を加えながら、「物語を書く、語ること」は、自己理解、人生への意味付与、人生の体験の再解釈などの機能をもち、最終的には、書くことで「自己変革」が生まれる可能性があるということを、理論レベルで説明する。また、書くことが「自己変革」につながったと思われる例を、担当者である筆者が解説も行う。受講生は、自分自身の語る物語をもって授業を履修していることが前提であるが、「物語として書く意味」の重要性を授業の中で強調することで、書く意欲の動機付けしている。その授業形式は講義ではなく、課題として読んできたものについて話し合うという、参加型の授業で行われている。
第2段階: どんなものを書くかのイメージづくり
授業を受講した学生が書いた「自分史的エッセイ」をサンプルとして配布し、その内容について議論することで、どのようなものを書くべきかのイメージ形成を促す作業を行う。「物語を書く意味」を理論的に解説するだけでは、受講生たちを十分に動機づけることは難しいので、具体的に先輩たちが書いた「自分史的エッセイ」を呈示する。「ライフストーリー文庫~きのうの私~」のウェブに掲載されている「自分史的エッセイ」あるいは、担当教員が以前に編集した『私たちの告白~9人のライフヒストリー』などから、2~3のエッセイを「書かれた物語」のサンプルとして配布し、その内容についてディスカッションする形式で授業を行っている。学生たちにとっては、書きたいと思っている自分の中にある「物語」を、どのように文章として書くことができるのかが解決されるべき課題としてあり、何を書きたいか、どこまで書くべきかについても曖昧なまま授業に参加している学生が多ので、いくつかのサンプルを読むことにより、先輩たちはどこまで書き、どのような物語を書いているのかを具体的に理解し、「自分史的エッセイを書く」ということのイメージを形成していく。
第3段階: 自分史的エッセイの書き方について
具体的な自分史的エッセイの書き方についての解説的講義を行う。『私たちの中にある物語―人生のストーリーを書く意義と方法』の第4章「自分にストーリーを与えよ―自伝的に書く」の章の具体的なサンプルと「書くためのガイドライン」を中心に読み、解説的な講義を行う。そこで述べられているキーワード「自分のために書くこと」「内なる声に耳を傾ける」「記憶を呼び起こし、掘り起こすこと」などを強調し、「話すように書くこと」について解説し、この「自分史的エッセイ」は基本的に他人のため、他人に自分を顕示するために、あるいは、他人に評価されるために書くのではなく、自分のために書き、自分理解や自己変革を目的として書くということを強調して説明する。そして、学生がそれまでに書いてきた「作文」や「小論文」のとの違いを明確にする。小学校から高校までの文章は、それぞれの段階での教師の評価を意識して書かれるので、自分の気持ちや考えを表現するのではなく、むしろ、自分の気持ちを抑え、期待されていることを書き、良い評価を得ることを目的としていたと講義した上で、それとは対照的に、「自分史的エッセイ」は他人の評価を気にすることなく、文章としての上手さや日本語としての表現の良さなど気にせずに、「話すように書くこと」で、自由に自分の経験、気持ちを表現してよい、ということを強調している。そしてあくまでも、「今も自分がこだわっている」「自分にとって意味あった」と思える体験、出来事について書けばよい、とも説明する。その意味では、どんな些細なことでも本人が重要であると思えることこそ、書くに値するのだということも強調している。
第4段階: エッセイを書く段階
書く枚数を規定して、最初の草案の締切りを6月中旬までとして、授業が終わる1か月以上前までに「自分史的エッセイ」の締切りを設け、草稿としてA4判で3頁程度を書くようにと指示する。この段階で、「宿題」となった課題の提出が近づく段階では、「書けない」という声が聞こえることが多くなる。「書きたいことがある」受講生であるにもかかわらず、書きだそうとした時に、書けないという現実にぶつかることが多いのである。そこで、担当教員としては、何枚でも良いので、書けるだけ書くことを基本として、「締切り厳守」を再確認する。そして、締切りに間に合ったものから受け取り、それを授業で読むという現実的な対応をしている。受講生のなかで、他でもエッセイ・ライティングなどの授業を履修した学生がまず書いて、提出する場合が多い。そして、エッセイを書いた受講生に書いた時の感想を言ってもらい、書くことの難しさと楽しさを、その学生自身の言葉で語ってもらう。受講生は五月雨式にエッセイを提出することになるが、その都度、書いた時の心境を他の学生に伝えてもらうことにしている。そして、共通して言えることは、「いったん書き始めると、止まらない」ということが受講生に共有されることになり、書き始めさえすれば、どんどん書けると確信し書き始め、ほとんどの受講生が第1草稿を1~2週間のうちに提出することになる。
これは、いったん書きだしたら、どんどん書いてしまうという「人生の物語」を書く行為のもつ特徴だと言える。いったん書き始めたら、一つの心の扉を開けることになる。あるいは、いままでとは違う理解に達することができた結果、と言えるかもしれない。
大学教育でのレポートの提出は、成績を付ける最後に設定している場合がほとんどであるが、この授業の場合、最終レポートに対して成績を付ける点においては通常と変わりはないが、第1草案を6月中旬に提出させて、それを授業の中で、全員で読み、そのエッセイに対して、出席者全員からコメントや質問を受けるという方式をとり、受講生間での意見交換や質疑応答を通して、エッセイを書いた学生が、第1草稿を推敲し、書き直せるようにしている。
第5段階: 読まれたエッセイを相互にコメントする段階
個人的なこと、今までだれにも言ったことのない「人生の体験」について書いて、それが読まれるということの心理的プレッシャーは、たとえ授業という限られた空間でも20歳前後の女性にとっては、大きなものである。いままで語り得なかったことを初めて書いて、他人に書いたことを授業で発表し、それを共有する形でコメントをお互いに交換することは困難なことである。そこで、提出された第1草稿で、担当教員が読ませたい、プライバシー保護の点から読んでも良いと判断し、本人がクラスで読まれてもよいと同意したものを、名前などを消して匿名にして(本人が同意すれば、実名で)、全員がコメントをするという方式をとる。そして、本人がコメントする時に、何らかの「不自然な行動」をとる場合、そのエッセイを書いた執筆者だとわかることになるが、基本的には、だれが筆者であるかを追求しない前提で授業を進めている。
コメントする時も、いくつかのルールを設けている。まず、評価的なコメント、書かれた内容が良いか悪か価値判断するコメントを禁止している。次に、書かれたエッセイの理解しがたいこと、不明な点、もっと説明がほしい点などを中心に質問するという形式のコメントをする。第3に、反発を感じる点ではなく、共感する点だけに限定してコメントをする。クラスの中に書いた本人がいることが前提なので、エッセイの執筆者にとって、ポジティブで意味あるコメントだけをいうことを基本的なルールとしている。最後に、この授業で話されたことは、基本として、他の人に「うわさ」として話さないこととしている。授業の最終課題として、授業に参加していた受講生からいろいろなコメントを加味した上で、担当の教員が最終的なコメントを文書で書き、執筆者はそれを参考にして、そのエッセイを深めて、修正された最終草稿を提出することになっている。
授業を以上のような5段階で行いながら、受講生たちは、「自分史的エッセイ」を書き、自らの人生の意味ある体験、今のこだわっている出来事などをエッセイとして「語る」ことで、自己理解、それぞれの体験や出来事の再解釈を行うことが期待されている。時には、書くことを通して、「自己変革」が起こる場合もある。
(4) 2012年度の授業実践から考える物語としての「自分史的エッセイ」のもつパワー
この9年間、匿名にして読むという方式で行ってきたが、2012年の授業で初めて、一人以外は、実名でエッセイを発表し、読み合うという参加型の授業が行われた。そのようになった主な要因は、受講生9名という少人数であったと推測される。また、4年生が4名、3年生3名、2年生2名と、上級生が多かったことも要因になっていたかもしれない。授業の第3段階が終わり、第4段階に移行する時、「人数が少ないので、それぞれの提出されたエッセイをオープンにして、実名で発表するのはどうですか」と提案をしてみたところ、一人以外は賛成した。その一人の学生が書いている内容を考えると、確かに、プライバシー保護の点から本人が拒否する理由が推測できたので、その学生を例外として、他の8名に関しては、書かれた草稿を全員で読むということを決定した。
人数が少数だということもあり、ゼミでよく行われているように、エッセイを読む第5段目からは、お互いの顔が見えるように円座で座ることも、みんなの同意のもと行われた。その頃から、1回の授業で平均、二人分のエッセイを授業で読むことができた。誰が書いたか明らかにされていたので、通常の授業よりも、コメントや質問が活発に行われたような印象が残っている。ゼミ形式の参加型で行われたので、お互いの信頼関係ができたことがその要因であったのかもしれない。
文章を読み、コメントをお互いに言う中で、それぞれの「自分史的エッセイ」に書かれたテーマの共通性に対して、共感が表現されるコメントが2012年度の授業では特に多かった。次の節で社会学的分析の対象としている「今までお嫁さんになるために勉強してきたの?」の執筆者Aさんは、授業中にサンプルとして全員で読んだBさんの「女子高文化―キラキラした彼女たちの中で」のコメントをしている最中に、「自分も受験で苦しんだ経験があるので、つい、共感してしまった」と声を詰まらし、突然、涙を流し、自らの受験の体験を話し始めた。AさんはBさんと同じように、「偏差値」を気にして生きた高校時代を経験したことを思い出し、その当時の「受験勉強の苦しさ」を思い出し、泣いてしまったようだ。Aさんの泣きながらのコメントについて、同じように受験で苦しんだという他の受講生からのコメントが続き、日本の高校受験、大学受験をテーマにディスカッションが展開される授業になった。次の節で、この2つの受験に関わるエッセイを物語として読み、その社会学的分析の可能性について論じるが、身近な先輩Bさんの物語をAさんが読むことで、共感し、過去の受験時代の私をふり返り、Aさんもまた、その苦しかった高校時代をテーマとして「自分史的エッセイ」を書くことになった。
これは、たまたま起こった一つの例に過ぎないこと、ではなかった。他にも同じようなことが起こった。匿名の書き手が書いた「もう『元ヤン』と呼ばないで」に対して、授業中一人ずつコメントした時のことであった。この「自分史的エッセイ」の内容は、父親と母親の仲が悪く、経済的な問題も関係し、家族が崩壊状態の中、書き手自身は、「ヤンキー」と呼ばれ、喧嘩を繰り返し、非行に走っていたが、おじいちゃんの支えのもと、頼りにしてくる弟を守るために、「ヤンキー」を止め、生まれて初めて勉強して、その後、今の大学に入学したというものであった。家族崩壊に面と向かうようになってから変わったという「自己変革」の物語であった。「ヤンキー」と呼ばれた中学時代と、その当時の家族崩壊の実態が具体的で鮮明なタッチで書かれた物語。その経験について「自分史的エッセイ」が書けるほどの精神状態になっている点で、執筆者Cさんの「今の自分」にとって意味ある体験としてあり、その時の苦しさや大変さは、過去の出来事になっている。
しかし、Cさんが描いた家族崩壊についてのエッセイについて受講生Dさんがコメントしようとした時、Dさんは家族崩壊のまさに渦中にいた。葛藤していた日々の中で、まさに今の自分の家族の状況を描き出しているエッセイを読み、共感し、「自分の事」「自分の問題」として考えてしまったのである。「今の自分の家族崩壊」を見るようで、その苦しい思いで精神が高ぶり、一言も言えず、泣いてしまった。Cさんの意味ある過去の物語がDさんに直接語りかけ、Dさんがいままさに自らに起こっている「家族崩壊」と直面することになった。その段階まで、エッセイの課題を提出していなかったDさんは、翌週には、今進行しつつある家族崩壊の現状を報告するエッセイを書いて提出してきた。そのエッセイは、物語としてまとまったストーリーになっていない、現状報告のようなものであったが、Dさんが、Cさんの物語を読み、みずから見ようとせず、逃げていた現実について書く作業を通して、直面しようとしたものであったと思われる。その半年後、Dさんは、授業で書き始めた「自分史的エッセイ」をさらに展開させ、それを名古屋市が募集するエッセイコンテストに応募し、そのエッセイは一つの賞を与えられた。見たくなくて、避けていた家族崩壊の現実をエッセイとして物語化することによって、ある程度の「解決」をした例と言えるかもしれない。
以上、AさんがBさんのエッセイを読み、涙を流し、自分がこだわっていた苦しい高校時代について書いたこと、また、DさんがCさんの家族崩壊の物語を読み、当時起こっていた自らの家族崩壊に直面し、そのことをエッセイとして書いたことは、一つの物語が、同じような体験をもった読者に直接的に働きかけ、影響した例と言えるであろう。影響を受けたAさん、Dさんは、自分の中にある「今まで話せなかった体験」を物語化することで、その共感する思いを表現し、その渦中にいた自分とその後の自分の理解をしながら、「自己変革」を経験していったのではないだろうか。この二人のケースを考えると、他人の「人生の物語」「意味ある体験」は単なる他人事として読まれるのではなく、自分自身の物語のように自分に語り掛けてきたと言えるのではないであろうか。因果関係的説明をする社会科学的説明様式を超えた、物語形式のもつパワーをここにみることができたように思える。
「ライフストーリー文庫」に掲載されている「私の物語」は、教室のまさに隣にいる学生の声を「物語」として表現している。そこには計算され、作られた作品のような完成度はないが、学生自身の「生の声」のもつパワーがあると言える。そこには技巧が施された美しい表現はないかもしれない。流れるように書かれた文章ではないかもしれない。しかし、まさに未完成であるが故に、隣にいる学生たちの「ふつう」の感覚に直接的に響くのではないか。「自分と似ている人」「自分と同じ体験をもった人」として共感が得られた時、人は自分の経験していることは、自分だけではないと思い、癒され救われることがある。問題を抱えた家族、問題の渦中にいる人びとの「ふつう」の話を読むことで、元気づけられる。その意味では、すべての人が自分の中に「語る物語がある」とアトキンソンが言っていることが、今筆者が描写した授業実践の一コマからも言えることである。
(5) テーマシリーズ「就職活動」の物語―分析よりも物語が共感を生む
本研究を進めていくプロセスで、大学生の就職活動に関する聞き取りや「自分史的エッセイ」を読み、いまの女子大生が直面する問題を「物語」として理解する試みを行った。その一部は、「ライフストーリー文庫~きのうの私~」に掲載しているが、まだ、未完のままで終わっている。未完ではあるが、それまでに至るプロセスを描写し、伝統的な社会学的説明にはない、「物語」がもつ「共感パワー」について論じたい。
2011年度のゼミ生の就職活動を支援しながら、学生たちが抱える就職活動の特徴を描写し、後輩の学生たちに役立てたいと考え、ゼミ生20名全員の就職活動の物語を『就職活動のさまざまなストーリー―20人の女子大学のキャンパスライフと就職活動―』(未刊行)としてまとめた。学生一人ひとりに「就職活動メモ」や「私の就職活動エッセイ」として書いてもらったもの、ゼミ担当者の筆者が、就職活動を支援し、就職のための履歴書やエントリーシートの書き方を指導するなかで、聞いた学生たちの語り、さらに、学生たちの就職活動に関する筆者によるフィールドノート、この3点を組み合わせて、それぞれの就職活動のストーリーを書いた。
その書き方は、社会学研究をしている筆者の分析的解釈を加え、就職活動に関するアドバイスなどを含むものであった。『就職活動のさまざまなストーリー』を就職活動を始めたばかりの学生に読んでもらったところ、学生の体験を分析した「社会学的解釈」などは、学生にはまったく興味がもてないものであった。学生たちは先輩たちがどう活動したか、その経験に関する「生の声」にもっとも興味を示し、その他の部分は飛ばし読みをしたようであった。
そして、読んだ学生の多くにとっては、20人の中で最も能力があり、自分の強い意志をもって就職先を決め、第1志望の企業に内定を受けた「成功物語」がもっとも不評であった。曰く、「あの物語を読んで、嫌になった」「私とは別の世界に住む人間だ」「私はあの先輩ほど能力はあるわけではないので、関係ないです」ということであった。つまり、自分とはあまりにも異なる世界にいる人の声など、あまりにもかけ離れていて、興味をもつことはなかったのである。学生たちが好んで読んだストーリーは、就職活動の中で葛藤し、苦しんだというストーリーであり、その苦しみや葛藤を共有することで、その物語に共感し、「自分もがんばろうと思えた」というコメントをした学生が何人かいた。これは、アトキンソンの「最良のストーリーは誰かが他の人の苦しみについて私たちに語っているものである。そのような他人の苦しみのストーリーは私たち自身の苦しみを耐え抜くための強力な治療方法になりうるのである」(2006:206)でも言われている通りである。
今就職活動をしている学生たちの就職活動に関する本の読み方を理解した上で、就職活動している学生の「生の声」、あるいは一人称で書かれた物語の方が、社会学的解釈を含んだストーリーより、物語としてインパクトが大きいと思い、『就職活動のさまざまなストーリー』の中の筆者が行った社会学的解釈を全て取り除き、9人の「私の就職物語」を入れたものを『就活女子』(未刊行)として、編集し直し、まとめた。そこには、9人の学生が就職活動のさまざまな局面で、苦労しながら葛藤した一人称によるストーリーが書かれている。社会学的分析を含まない「私の就職物語」である『就活女子』を読んだ学生は、物語として書かれている、詳細で具体的な内容に共感し、読書後は、「就職活動で悩んでいたけれど、この本を読んで、がんばってみたいと思った」という感想を述べ、その時まで就職活動を避け、考えないようにしていたが、具体的に就職活動をし始めた、という。一人称で書かれた物語が読者に共感を生み、元気にさせるパワーをもっているのではないかと言える。
とするならば、読者の共感をえるためには、一人称で書かれた物語を呈示することがもっとも効果的であると言える。そのことを理解した上で、本研究は、一人称で書かれたストーリーである、さまざまな「語られたストーリー」や「自分史的エッセイ」をホームページにアーカイヴ化し、広く人びとに公開し、社会に発信し、多くの人に利用してもらい、利用した人が自らの体験と似た体験についてのストーリーを読み、自らの人生をふり返り、その人生をより深く理解し、意味付与することで人生上の体験や出来事を再解釈する機会をもつことを期待しているものである。本研究はまた、ストーリーをアーカイヴ化し人びとに発信するだけでなく、ストーリーの社会学的研究を促進することも目的としている。では、物語のもつパワーを失わせない、社会学的分析は可能なのだろうか。次の節で、ストーリーの社会学的研究の試論を行う。
2. ストーリーの社会学的研究の可能性―ストーリーと社会学的分析の関係性―
山口(2004:11-13)は、ブレナーの2つの思考様式についての議論を簡潔にまとめている。ブレナーによれば、思考には2つの様式、つまり論理科学的思考モードと物語的思考モードがあり、両者は経験を秩序立て、現実を構築する異なる思考様式であり、お互いに補完的であるが、片方を片方に還元することはできない。論理科学的モードは科学的パラダイムであり、「真か偽か」という問いかけによって答えが導かれるが、物語的思考モードは2つ以上の出来事がどのように関係づけ陳述されるかが問われるとしている。普通の人が普通にやっていることを知りたいならば、物語的思考モードによる心理学が必要であると言っている。
本研究の中心的テーマは、ストーリーのもつパワーを理解した上で、ストーリーの社会学の可能性を考えることである。ストーリーとしての「自分史的エッセイ」を中心に論じ、ストーリー、あるいは物語を呈示することで生まれるパワーが、同じような状況にいる人が自分のおかれている状況を理解する助けになると述べてきた。その意味で、「ライフストーリー文庫~きのうの私~」の創設は、ストーリーをウェブ上にアーカイヴ化し、普通の人のストーリーを普通の人に多く提供することで、似た状況にいる人に対して、共感と理解を深める機会を提供することをめざしている。より多様なストーリーをより多くアーカイヴ化することで、より多くの人びとの自己理解、他者との共感を得る可能性がある。
アトキンソンが言うように、ストーリーを書く、語ることによって、私たちは、主観的リアリティを追求している。「自分史的エッセイ」「語られたストーリー」は、書き手、語り手自身の真実である。彼らは私たちに、書きたいストーリー、語りたいストーリーのみを提供している。私たちは、彼らが真実としていることしか読むことはできない。それは、書き手あるいは語り手の主観的リアリティの世界である。自分史的エッセイを書くことは、自分の経験を反省的にとらえ、それに意味付与し、それをストーリー化することである。ストーリーを分析的に考えるなら、そのストーリーを、語り手あるいは書き手が、「生きられた生」について私たちに語りたい何かをもつテキスト(text)として受け入れなければならない。ストーリーの多くは、彼ら自身にとってもっとも重要なことを話す(書く)ので、共有される「神聖なる瞬間」であることが多い。それを解釈するために3つの重要なポイントがある。
第1に、そのストーリーを評価するのではなく、そのストーリーそのもののもつ意味を追求すること。第2に、ライフストーリーはほかの分野でのドキュメントと同じように、テキスト(text)である。それ自体で存在していて、小説や詩と同じようなもので、読者の考え方に基づいて、ある一定の反応を生み出すものである。第3に、私たちは、お互いにとって教師である。小説や詩のように、ライフストーリーも私たちに人生について言う何かをもっている。私たちは私たちが聞いた、あるいは読んだストーリーから何かを学ぶことがある(アトキンソン2013:19-21)。
だから、ストーリーに解釈を入れて分析するのではなく、ストーリーそのものを示すことがこのセンターの目的であるし、この研究の目的であった。しかし、それとは独立した社会学的分析の展開も可能であると考え、ライフストーリーの社会学的分析の可能性について考えてみたい。
まず、テキストそのものを読みながら、論理科学的思考モードとしての社会学的解釈を付け加え、書き手の主観的リアリティついての論理的整理としての社会学的分析を試みる。具体的な方法としては、「ライフストーリー文庫~きのうの私~」に掲載している、2つの事例を取り上げ、それぞれの文章の中の「書き手の主観的な語り」に下線を引き、その下線部に対する社会学的分析のコメントを時間軸にそって付けくわえることで、「書き手」の「自己変革」のプロセスを説明的に描写し、「書き手」の主観的リアリティに焦点をあてるライフストーリーの社会学的分析の試論を行う。また、この2つのエッセイを分析した後、その2つを比較し、同世代を生きている女性に共有された「主観的リアリティ」とは何かを考え、現代の日本社会の学校教育の問題を、それを経験した本人の視点と時間軸という2つの要素で分析することで、数量的社会学の枠組みで展開されている制度的、統計的分析とは異なった、ストーリーの社会学的分析が可能ではないかと考えている。
(1) 事例1:「女子高文化―キラキラした彼女たちの中で」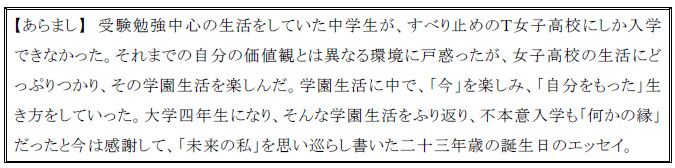 中学は勉強だけだった
中学は勉強だけだった
私は中学一年生から本当に優等生。とーっても真面目な生徒だった。定期テストの点数はいつも学年十位以内。学年一番をとったこともある。通知表は、一年生の時から全ての科目オール5。4をとったのは三年生に体育で2回だけ。部活も部長とペアでテニス部。すごーく真面目に練習していた。部活の後は週に2回の塾。塾は中学一年生の頃から三年間、卒業まで通い続けた。帰ってきたら宿題して、テレビ見て、寝る。特別な趣味もなければ特技もなかった。
でも、この生活が普通だった。その時はこれで充実していると思っていた。みんなから「頭が良くて羨ましい」と言われたけど、それだけの勉強をしていたから点数とれるのは当たり前だ。人より勉強したら人より点数はとれるものだ。定期テストってそういうもの、そう思っていた。だから、テスト前は毎日塾に通っていたし、土日も塾で朝から夜まで勉強していた。朝九時から夜九時までとか。そんなテスト勉強が普通だった。
こんなにしなくても点数がとれる人もいるのかもしれないが、私にはそれだけの時間が必要だった。それだけの量をこなしていた。テストの結果が出て自分より点数が高い人がいたら、「私の今回のテスト勉強は足りなかったんだ」って、「もっと勉強しとけば良かった」っていつも思っていた。「次はもっと準備しないと」って。別に無理をしていたわけじゃなかった。この私が私だった。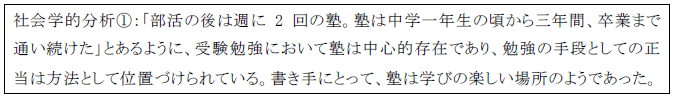 テストの点数がよかったから、成績がオール5だったからって親からお小遣いがもらえたわけでもないし、ご褒美に何か買ってもらったことだって一度もない。結果を見せると決まって他人事のように言われた。
テストの点数がよかったから、成績がオール5だったからって親からお小遣いがもらえたわけでもないし、ご褒美に何か買ってもらったことだって一度もない。結果を見せると決まって他人事のように言われた。
「毎回、毎回よくやるねえ、お母さんにはできないわ〜」。とりあえず、これが母のいつもの感想だった。「次はもっと頑張りなさいよ」なんて言われたことがない。父からは特に褒められたこともないし、「勉強しなさい」なんて言われたことも、もちろんない。両親にとっても、この私がいつもの私だった。私は私のために勉強していた。学期末、学年末、良い成績を残すために、定期テストで高い点数をとる。美術や音楽なんかも普通に頑張ってたいら、いつも良い成績がもらえた。
「良い成績があれば、偏差値の高い高校に行ける。偏差値の高い高校に行けたら、良い大学に行ける。良い大学に行けば、就職は大丈夫」
今思うと、とてーも甘ーい考え方をしていた。周りから見るととっても優等生な中学生。これが私だった。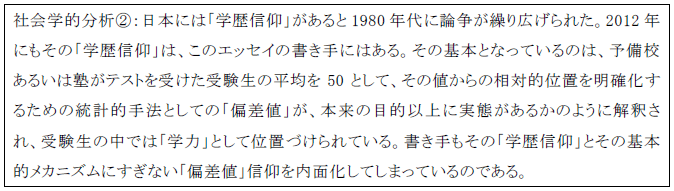
高校入試に向けて
中学三年生にもなると、学校でも塾でも受験についての話題が自然と増えた。
「あの高校の制服可愛い」
「あっちの高校の校則は緩いらしい」
「学園祭が楽しそう」
「早く決めたいから推薦が欲しいなー」
それまで偏差値の高い高校に入るためにあれだけ勉強してきていたのだから、私にとっては待ちに待っていましたという話題のはずだった。でも、何故か私は全く高校に進学するということに関して興味がもてなかった。 「高校生の私」なんて、その時は全くイメージができなかった。皆盛り上がっているけど、私はなぜか冷めている時。
中学三年生の春、担任に聞かれた。
「どこの高校に行きたいんだ?」
「わからない。行けるところに行くよ」
「そうか、おまえならどこでも大丈夫だ」
私は思った。
「この人は私のどこを見てこんな簡単に、こんな無責任なことが言えるんだ?」
担任の先生は決してきらいではなかったし、どちらかと言うと、とても生徒に真剣で、面白くて私はとても信頼していた。でも、この時に、「あー、この人に受験の話はできないなー」なんて感じた。当たり前の話だが、担任は私の定期テストの「結果」しか知らなかった。
高校受験を考えた時、学校の成績に意味がないことは私自身、よくわかっていた。私はあくまで、定期テストのために勉強していた。教科書を暗記したり、授業中に先生がくばったプリントばかり復習したり。実力ではない。塾では、「一年生の時から実力をつけろ」と言われ続けていた。塾で言われたことは全てこなしていたし、全校テストの成績もまあまあ良かった。
でも、自分の実力には全く自信がなかった。良い成績を残していたのはあくまで偏差値の高い高校に入るため。成績はある。あとは実力をつけるだけ。特に深く考えずにこの辺の一番偏差値の高い高校を受験しようと思った。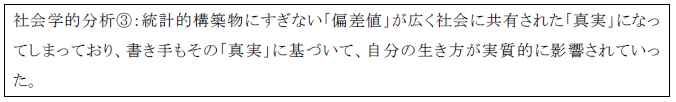 「A高校に行こう」
「A高校に行こう」
私の答えは案外簡単に出た。でも、ひとつ問題点があった。A高校はほぼ私服登校だったことだ。私服に関して若干、面倒に思っていた私は、とりあえず、高校までは制服が着たかった。これが私の志望校選びの悩みだった。ばかばかしくて笑えるかもしれないが、本当にどうしようかと悩んでいた。
学校のやりとりから数日後、塾の先生と全く同じやり取りをする。
「どこの高校に行きたいんだ?」
「分からない。行けるところに行く。でも、『良い』高校に行きたい。A高校とか興味あるよ。先生、どう思う? でも、私服なんだよね」
私は、その時思っていたことをそのまま伝えた。
「おまえに、『良い』学校があるんだ」
先生はそう言った。
「B高校知ってるか?」
「知らない。どこそれ?」
そこは、A高校の次くらいに偏差値が高いと言われていた高校だった。先生に言われるまでB高校に関して全く知らなかった。というか、他の高校に関しても全く知らなかった。先生は付け加えた。
「制服があるぞ、しかも、スカートには黒いリボンが入っていてとっても品がある。あの制服着てれば、すぐにどこの高校かわかる。一種のステータスみたいなもんだな」
「なんで私にその高校がいいの?」
「勉強できる生徒ばかりだし、部活動も活発だ。おまえみたいに、こつこつ頑張るタイプの生徒が多い雰囲気だな。A高校はおまえには自由すぎて戸惑うんじゃないか?」
「ふーん、じゃあ、その高校に行く」
この会話で私の志望校は変更された。塾の先生は、一人でも多くの生徒に偏差値の高い学校に合格してほしいと思っていることは、その時の私でもわかっていた。でも、学校の先生より塾の先生の方が私自身を見て学校を考えてくれているように思えた。学校の先生は私の結果しか見ていないけれど、この先生は私の結果に至るまでの時間を知って、この高校を薦めてくれているのだと思った。今までの私を認めてくれている。そんな気持ちになった。
「先生、私、さすがに一校だけだと不安なんだけど、後、どこ受ければいいかな?」
「なら、公立はもうひとつ、○○高校。私立は、△△高校、T女子高校、□□学園の順でいいんじゃないか?」
こうして、私の志望校の五校は塾の先生によって全て決められた。私は、何か具体的にやらなければいけないことができると頑張れるらしい。第一志望を決めてから、それまで以上に勉強に打ち込んだ。学校の成績はもちろん、落とさない。部活も中学最後の夏、大きな大会が控えていた。部活も本当に忙しかった。土曜日は練習試合で潰れたし、部活の時間がどんどん増えていった。
でも、今の私の実力ではトップの公立校なんて無理だとわかっていた。だから、しっかり実力をつけようと基礎から勉強した。定期テストのための勉強の他に、公立高校一般入試のための勉強、加えて、受験予定の三つの私立の入試のための勉強をどれもしっかりとこなしていた。私立の入試はそれぞれの学校のテストに特色があり、厄介だったが、やらなければいけない。「不合格なんてありえない」と受験する全ての高校に合格しようと、ただひたすら勉強していたように思う。
夏休みには近所の通っていた塾にプラスして、地下鉄で十五分ほどの同じ塾の違う校舎に特別講座のために通う日々だった。そこには他の校舎の生徒が、「同じ思い、良い高校へ」という強い気持ちで集まってきていた。私の通っていた校舎からは、私しかその講座をとっておらず、友達はいなかった。でも、みんなそれぞれの目標は明確だった。友達とおしゃべりにわざわざ来ている訳ではない。自分の実力をつけるためだ。今までの塾の教室の雰囲気とは全く違うものを感じた夏休みの経験だった。
その教室での私の順位は平均だった。もっと勉強している同級生を見て、私もまだまだなんだと考え直された。今思い出しても、よく頑張っていたなと、あの時の自分を褒めてあげたい。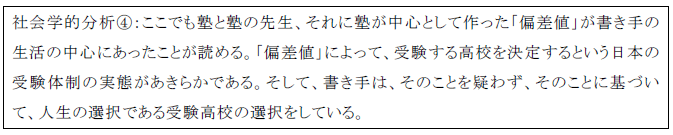 不本意入学
不本意入学
これだけ勉強していても落ちる時は落ちる。私立の第一志望は不合格。その次のT女子高校と、その次の滑り止めはなんとか合格。私立の一般入試は二月。その後に公立。私立が一つダメだったことは全然気にもしていなかった。「私はB高校に行くから大丈夫だよー」。何の根拠もない話だった。それでも、笑いながらそんなこと言っていたのを覚えている。それだけ勉強していると思っていたし、自信があったのだと思う。三月の公立入試の本番まで、私のB高校に対する思いはだんだんに強くなっていった。
公立は2校とも不合格。あれだけ憧れをもっていた、B高校の制服を着るという目標は果たせなかった。中学の集大成、このテストに全てを懸けていた。その時は、高校受験が私の人生を左右する全てのように思えていた。公立高校合格発表から帰宅。2校とも不合格。この事実は、T女子高校に入学することを示していた。泣いて、泣いて、泣いた。 「あなたが頑張ったなら、それでいいじゃない」
「あなたが頑張ったなら、それでいいじゃない」
母はとても冷静だった。でも私は後悔の塊だった。
「あの時、もっと…」と考え始めたら切りがなかった。
「T女子高校に行くくらいなら、高校には行きたくない」
この一言に母は言った。
「あなたのおばあちゃんたち姉妹は、みんなT女子高校の卒業生なのよ」
私の母方の祖母は、母が六歳のころに亡くなっている。今のおばあちゃんは、後妻さんだ。亡くなった祖母は五人姉妹だった。みんな女。祖母は長女。よくできた人だったと話だけは聞いていた。
祖母はもう一人いるという事実を母から聞いたのは、私が小学三年生のころ。曖昧に親戚だと言われてきた人たちが沢山いたことは、小さいながらとても不思議に思っていた。亡くなった祖母方の家族だったのだ。今のおばあちゃんは祖母の話を嫌がった。もちろんその気持ちも周囲は分かっているから、自然と亡くなった祖母の話はしてはいけない暗黙のルール。祖母の妹たちを含めた親戚の話ももちろんしてはいけなかった。
でも、私には関係なかった。亡くなった祖母に会ったことはなく、今、目の前にいるおばあちゃんが私のおばあちゃんだ。だから、私もその件に関しては何も聞かずにいた。
その祖母の姉妹たちみんなが、T女子高校卒業だというのだ。しかも中学から。全く知らなかった。公立2校に不合格になり、私がT女子高校に入学することが決まって、その時初めて言われたのだ。母は付け加えた。
「お母さんは、あなたが私立の第一志望に落ちて、T女子に合格したことは何かの縁だと思っていたの。B高校よりも、もっとあなたにとって良い学校かもしれないと思っていた」
そんなことを言ったのだ。私は腹が立って仕方がなかった。私があれだけ勉強してきたことを全否定されたような気持ちだった。この言葉をきいて更にT女子高校に行きたくなくなった。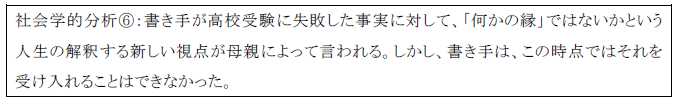 どうして、これほどまでに行きたくないと拒否をしたのだろう。あれだけ勉強してきていたのに認められず、結果が出ず、目標を達成できなかった。なんだか大きな勝負に負けたような気持ちだったのだ。その負けを素直に認めることができなかった。それまでにこんなにも大きな負けを感じたこともなかった。ずっと勝ちたい勝負は勝ってきたように過ごしてきていたのも、ひとつの理由かもしれない。
どうして、これほどまでに行きたくないと拒否をしたのだろう。あれだけ勉強してきていたのに認められず、結果が出ず、目標を達成できなかった。なんだか大きな勝負に負けたような気持ちだったのだ。その負けを素直に認めることができなかった。それまでにこんなにも大きな負けを感じたこともなかった。ずっと勝ちたい勝負は勝ってきたように過ごしてきていたのも、ひとつの理由かもしれない。
入学式の日
私も現実を見て、T女子高校への入学に同意したが、入学まで、その敗北感から立ち直ることができなかった。入学式の日になってもまだ、顔は不機嫌でいやいや感がたっぷりだった。入学式当日、体育館にクラスごとに並べられたイスは各クラス2列ずつ。1列はT中学からの生徒、片方は外からの入学生。きれいに分けられた。一目見て、違いは歴然としていた。T中学からの子たちは慣れ親しんだ友達とおしゃべりに盛り上がり、全く入学式の緊張感はなく、リラックスした様子。私たち、外からの入学生はもちろん、知っている友達もおらず、緊張感たっぷり。女子だらけの四〇人のクラスだった。その時の私はもちろん不機嫌で加えて、不安でいっぱいだった。
入学前のT女子高校のイメージはいいとこ育ちのお嬢様がたくさんいて、いじめとかもたくさんあるのかな、とか。女子の特有なグループ意識も特に強かったりするのかな、なんて思っていたりした。そんなところ絶対馴染めない。入学前からそんなことを決めつけたりもしていた。
入学式後、教室に移動。その時の私の正直な感想。
「うわー、女子しかいないー。すごい変な感じ」
クラスに女子だらけ。一年生のころは先生も女性の先生だった。はじめ教室内は、自然と中学からのあがりの子たちと、それ以外の子たちで分かれていた。でも不思議なことに、帰る頃になるとそんな境界線なんかなく、みんながわいわいしていた。私も中学あがりの子二人、YちゃんとTちゃんとと仲良くなり、三人で駅まで帰ったりした。どうしてあの二人だったのかはよく覚えていない。でも、二人が話かけてくれたことは覚えている。とっても気さくで面白くて、とっても個性的。その後クラスが分かれたりもしたが、高校三年間とても仲良かった。
大学も学部は別々だったが今も連絡をとっている。その二人がいたから私がもっていたT女子高校のイメージは、初日にどこかにいってしまった。二人からT女子高校のはじめの一から十まで教えてもらったような気がする。校舎内のことから先生のこと、T女子高校の暗黙のルールみたいなこと、T中学出身の子たちの情報まで、ありとあらゆることを教えてくれた。
入学式から帰宅。私の一言は、「結構、楽しかった」。その言葉に母はびっくり。私自身はそんなこと言ったことを覚えていなかったが、後から母が言うには、それは、それはびっくりするくらいの態度の変わりようだったらしい。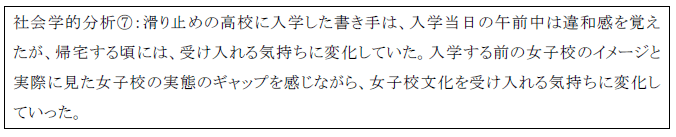 学園生活
学園生活
T女子高校の生活がスタートして私の考え方は大きく変わった。T中学出身のクラスの友達たち、T高校という環境の影響がとても大きかった。上手く言葉に表すことができないが、彼女たちはみんなとてもキラキラしていた。みんな、それぞれ違う「自分」をもっていた。自分の好きなこと、興味あること、自分が思うがままに、「今」をとても楽しんでいるように見えた。ただ、「今」だけではなくて、「未来の自分」についてもしっかり考えをもっていたし、物事に関しても自分の意見もしっかりもって、発言する力もあった。
中学時代、私があれだけ頑張っていたテストに関しては、「テスト勉強はそこそこに!」が、みんなそろっての合い言葉だった。私にとっては全く違う世界に来たようだった。
私も一年生の時点では、大学進学は内部推薦でT大ではなく、他大受験を考えていたため、中学同様、今まで通りテスト勉強に励んだ。またT女子高校は、公立高校の授業のカリュキュラムと大きく違いがあったため、その差を埋めるため、また新たに塾にも通い出した。
T女子高生活の中で私の気持ちが全く変わった。高校三年間に出会った友達、先生、起こった出来事全てが私の考え方を変え、世界を新しくした。いつの間にかT女子高校の先生についても詳しくなって、テストの傾向もつかみ、授業で力を抜くようになった。後輩もでき、球技大会のドッヂボールに全力を注ぎ、朝練することにも全く違和感がなくなり、体育の授業ではちまきをつけることも、ラジオ体操の第二しかしないことも、冬には体育館でフォークダンスを踊ることも、文化祭の出し物に数か月の全てをかけることも、全く不思議に思わなくなった。T高校生活をおおいに楽しんでいた。
特にT女子高での文化祭の比重はとても大きかった。出し物の案について話し合いを始めるところから、みんな「超」真剣。T中出身の子たちがとりあえず、目の色を変えて、体を乗り出し、話し合いに挑む姿勢は一年生の私に大きな衝撃を与えた。準備が進む中で仲間割れもしばしば。真剣になりすぎて、泣き出してしまう子も。いつもおちゃらけて、部活バカな友達も、文化祭と聞くと顔が変わった。文化祭の出し物の順位の結果発表でも、泣き出す子は当たり前。嬉し涙、悔し涙、みんな本当に素敵だった。三年生の頃には、こんな生活も当たり前すぎて自然なことになっていた。
こんな話を同じ中学出身の公立高校に通う友達にすると驚かれ、少し引かれる。テストの点数、成績、部活だけの生活に充実感を感じていた頃とは変わり、T女子高校独特の生活、友達との旅行、おしいいランチ、映画を楽しんだり、コンサートに行ったり、読書する時間も増えた。一年生の頃から水泳部に入っていたが、体調が思わしくなく、二年始めには退部。それからは時間もできたので、「アルバイト!」と思ったが、T女子高校では高校生のアルバイトは禁止。でも私は、親戚の伝手で家のお手伝いという名目で歯医助手として働き始めた。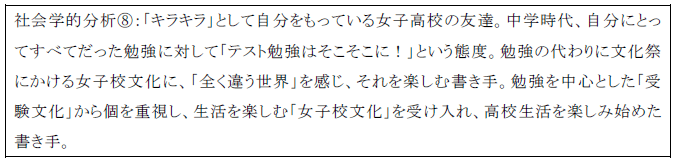 七年たった今でもそこでのアルバイトは続いている。その歯医者で高校生を雇うのは私が初めてで、多分最後。何も知らない、分からない、高校生の私に教えることはとても大変だったと思うが、先生やパートのおばちゃんたち、その時の大学生のバイトの先輩には本当に感謝している。「働く」ということに関して考えるようにもなったし、電話対応から、患者さんへの対応、器具の準備、片付け、厳しく注意されることも多かったが、ここでの経験はとても貴重なものだ。私の高校生活は、中学の頃とは違う意味でとても充実していた。
七年たった今でもそこでのアルバイトは続いている。その歯医者で高校生を雇うのは私が初めてで、多分最後。何も知らない、分からない、高校生の私に教えることはとても大変だったと思うが、先生やパートのおばちゃんたち、その時の大学生のバイトの先輩には本当に感謝している。「働く」ということに関して考えるようにもなったし、電話対応から、患者さんへの対応、器具の準備、片付け、厳しく注意されることも多かったが、ここでの経験はとても貴重なものだ。私の高校生活は、中学の頃とは違う意味でとても充実していた。
大学受験に向けて
高校二年生と三年生の担任は同じ数学の男性の先生だった。私の考え方が変化していくのを一番知っている人かもしれない。二年生の時点でもまだ、他大の受験を考えていた私は、担任の先生に素直に相談した。先生は、「T大への進学に少しでも興味があるのなら、一つの選択肢として残しておいた方が良い」と言ってくれた。私は何故か中学の頃から理系で、数学も理科も得意科目だった。高校でも何故か、頑張って勉強しなくても数学や理科のテストはなかなか点数が良く、数学の先生だった担任も「将来、真剣に理系の職を考え、大学進学するなら決断は早めに」とアドバイスをくれた。
逆に、文系のテストはイマイチ。中学ほどテスト勉強に打ち込まなくなった私は、苦手な科目の成績は良くもなく悪くもなく、くらいだった。英語、国語、社会、どの科目も好きだったが、成績は普通だった。長文読解は元々、読書が好きだったので得意だったが、古文の暗記に近い勉強はとても苦手。英語を聞くのは好きだったが、教科書の暗記は苦手。歴史が好きで日本史も世界史も好きではあったが、カタカナの人名、地名はまるっきりダメだった。
今思うと、これが私なんだと思う。すごーく普通だ。数学も理科も好きだったが、理系に進みたいという思いには至らなかった。数学は一つの解答にたどりつけた時の達成感が好きだったし、理科は、世の中の不思議なこと、化学だったり、物理、生物であったり、それぞれの分野を理解していくことが面白かった。基本、学ぶことが好きなことは中学の頃と変わらなかった。
でも、三年生にもなると理系のクラスには本当に数学、理科が好きな子、理系の学部を他大で受験する子たちが集まった。私はそこまでの気持ちはなかったし、自然に英語や国語の授業を選択。でも、成績はイマイチ。特別に勉強したい分野もない。軽く、壁にぶつかった。「他大で特に行きたいところもない。なら、残りのT女子高校での生活を多いに楽しみ、T大に進学しよう」。それが、三年生の春、決意したことだった。この決意も両親ととても驚かせた。
高校の成績はトップではなかったが、とりあえず、T大の学部を選べるようなくらいにはいたので、これ以上落とさないように、少し上げるくらいの気持ちでいた。夏休みはもちろん、クラスの出し物の準備に全身全霊を込めていた。公立高校の友達は受験勉強のために予備校に毎日通っていたが、私は毎日学校にいた。劇の準備のために。私の夏休みはこんな感じだとは到底、その友達たちには話せなかったのを覚えている。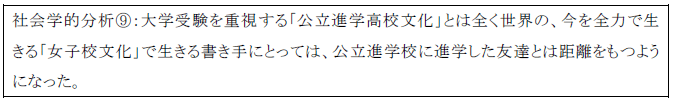 学部選択も、高校受験した時の志望校選択となんら変わらなかった。T大の内部推薦は高校の成績順で選択権が与えられるようなものだった。管理栄養学科は成績トップクラスの子たちで定員いっぱい、こんな状況だった。私たちの大学入学から新しく教育学部ができた。担任には、「数学が好きなら数学の先生の道もある」と、勧められたが、先生になることにイメージがもてず、教育学部は断念。特にデザインなどにも興味がなく、なぜか自然に、国際コミュニケーション学部を選択していた。管理栄養学科の次くらいに言語コミュニケーション学科の目安成績が高く、私の成績ではギリギリだったが、とりあえず、第一志望は、「国際言語コミュニケーション学科」だった。
学部選択も、高校受験した時の志望校選択となんら変わらなかった。T大の内部推薦は高校の成績順で選択権が与えられるようなものだった。管理栄養学科は成績トップクラスの子たちで定員いっぱい、こんな状況だった。私たちの大学入学から新しく教育学部ができた。担任には、「数学が好きなら数学の先生の道もある」と、勧められたが、先生になることにイメージがもてず、教育学部は断念。特にデザインなどにも興味がなく、なぜか自然に、国際コミュニケーション学部を選択していた。管理栄養学科の次くらいに言語コミュニケーション学科の目安成績が高く、私の成績ではギリギリだったが、とりあえず、第一志望は、「国際言語コミュニケーション学科」だった。
三年の秋、文化祭も終わってそんなに時間もなく、すぐ内部推薦の選考だった。なんか普通に考えてありえない感じではあったが、それは軽くやってきた。
「いついつまでに最終志望を決めて」
「おおーこんな簡単にやってくるのか」
と、その時は思ったが、何故かすんなり受け入れられた。
「これがT女子高校の流れなんだなー」
と思い、流れに沿っていた。しかし、結果は残念。
一部の成績上位の子が最後にして志望を変更、私は「言語」の定員に入ることができず、第二志望の表現文化学科に。その時はもちろん号泣。高校受験の結果を思い出した。
でも、表現への入学は案外早く受け入れることができた。どちらの学科も同じような授業が選択できると知っていたし、テスト勉強も手を抜いていた。成績が十分でなかったのは自分の責任であるし、「表現」へ行けば行ったなり、自分の道を見つけ、楽しめると思った。おそらく中学生の頃の私だったら、こんな考え方はできなかっただろう。こんな風に考えるようになったのもT高校での生活の影響だと思っている。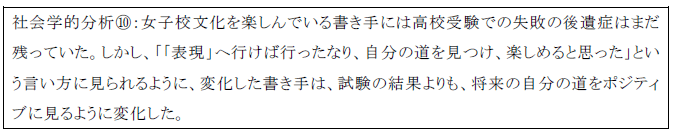 大学生として
大学生として
今は、表現文化学科に来て本当に良かったと思っている。今まで興味をもっていなかった内容の授業も取ることになったりして、新しい発見が多い学科だったように思う。休学までして留学もした。英語は苦手科目だったのに不思議な話だ。自分で休学したい。なんて行動に移すことも以前の私では考えられなかった。でも、留学でまた、新しい人たちとの出会いもあったし、考え方も変わった。
今、中学の頃の友達に会うと、私は高校に入って本当に変わったと言う。「自分があるね」って言われることがとっても嬉しい。T女子高校に通って、人と比べないようになった。もちろん、今でも勝負事は負けるととても悔しいが、「自分のままで勝負している」感じがする。人と比べない。私には私の考えがあって、人に押し付けることはしたくないが、伝えたいとは思う。相手の思いを聞く時間もとても好きなんだと。これまで自分と向き合ってきての発見だ。
T女子高校では、こうして自分と向き合うこともできるようになった。普通に公立高校に進学していても、自分について考える時は誰にでもくると思う。でも、私にとっては、そういった時間をT女子高校という環境の中で過ごすことができたことは本当に嬉しく、感謝している。
私にとってT女子高校で出会った友達、後輩は本当に個性的で頼もしい。彼女たちの存在なしでは「今の私」はいない。それぞれが、それぞれの方法で輝いているし、かっこいい女性ばかりだ。私は彼女たちをとても尊敬している。これからも今まで通り切磋琢磨して支え合っていきたい。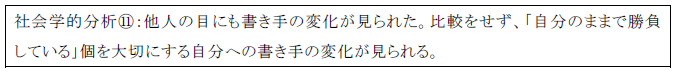
今の私―祖母との縁に感謝して
母と私の今までについて話したことがある。「あなたは高校生活をT女子高校で過ごして本当に良かったね」と言われたことがある。母も私の変化に気づいていたのだ。母も私も、T女子高校でおきた私の変化は良い変化だったと思っている。あの時、高校受験で第一志望の公立高校に合格していたら、T女子高での充実した生活はなかった。こんな風に自分について考えることはなかったかもしれない。T大に来ることもなかったかもしれない、休学して、留学してなんてことを考えることもなかったかもしれない。
でも、今はこうしていまT学園の一員として学べていることがとても嬉しい。これから社会人になって大変なこともたくさんあると思うが、私は私らしく乗り越えられると信じている。
「第一志望に落ちて、T女子高校に入学するのも何かの縁かもしれない」
これは、私が高校受験で第一志望に落ちた時に母が言った言葉だ。あの時、私はこの言葉に本当に腹が立ったが、本当に良い縁だった。亡くなった祖母は、T女子高校が私に良い場所だとわかっていて、あの時の私に「T女子高校で学べ」と天国から言っていたのかもしれない。
二〇一一年年七月三日二十三時、二十二歳最後の日がもうすぐ終わる。二十三歳の一年はどんな年になるのかな。小学生の頃に描いていた二十三歳の女性ってもっと大人な感じだったような。二十二年間の私の時間を振り返ってみても、何ひとつ後悔はない。
「本当に…?」
やっぱり少し違うのかもしれない。後悔はたくさんある。でも、後悔しないように気持ちを変えることができるようになったのだと思う、この二十二年間で。私の人生に起こった出来事には全てに意味があって、「今の私」をつくるために、「未来の私」のために必要な時間だった。
そう思えるようになったのは、明らかな私の中の変化だ。T女子学園の一員として学び始めてから、私の世界は新しくなった。あれからもう七年がたった。八年目の真っ只中、この学園の学生であることを誇りに思い、最後の一年を大いに楽しみたい。T女子学園が私に与えてくれた経験全てに、感謝して…。
最後に、神様は、これまでT女子学園で成長してきたであろう私にちゃんと大きなご褒美をくれた。第一志望の企業に内定。二十三歳を思い、考えることは沢山あるが、後悔はひとつもない。大きすぎるご褒美にとても感謝している。これからもっと世界が広がって、沢山の人たちに出会って、新しい発見をして、苦しいこと、大変な時を乗り越えながら楽しく生きていくことが楽しみで仕方ない。
これからもT女子高校、T大学で出会った友達と自分らしく生きていきたい。来年の誕生日はきっとお仕事が大変だろう、その時、私はどんなことを考えているのだろう。楽しみだ。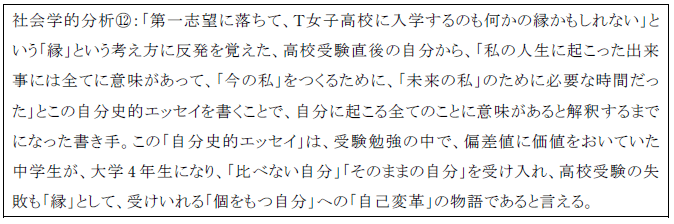 (2) 事例2:「今までお嫁さんになるために勉強してきたの?」
(2) 事例2:「今までお嫁さんになるために勉強してきたの?」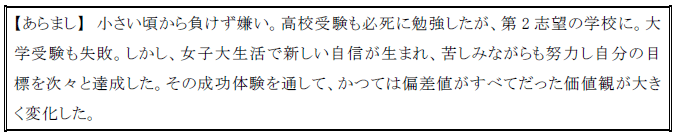 高い偏差値の高校をめざして
高い偏差値の高校をめざして
私は、小さい頃から負けず嫌いだった。だから、小学校の頃から授業をしっかり聞き、テスト前には自分自身で勉強するといったように過ごしてきた。中学にあがってからも、より一層勉強を頑張った。できるだけ高い偏差値の高校に入学するために。毎日の授業はしっかり聞き、きちんと宿題もこなし、週に何度かは塾にも通っていた。テスト、二~三週間前からは、夜遅くまで勉強し、土日は塾の自習室に行き、夜遅くまで残り、納得がいくまで分からないところを、先生に質問したりもした。塾で宿題として出されたプリントは、もちろんすべてこなし、新しい他のプリントをもらって勉強することもよくあった。そのかいもあって、いつも定期テストは、ほとんど見た事のある問題ばかりを解いていく感じであった。負けず嫌いな私にとって、テストでの順位や、模試での偏差値は、とても重要であった。そうして、次第にできるだけ偏差値の高い高校に入学することを目標とするようになった。三年間、勉強をおろそかにすることなく頑張ってきたのに、第一志望の高校には合格する事ができず、第二志望の高校に進学することになった。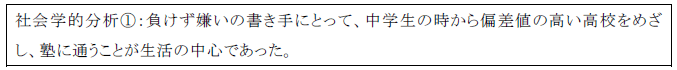 進学高校での受験勉強生活
進学高校での受験勉強生活
私は、いわゆる進学校と呼ばれる高校に入学した。私の高校の学生は、一見派手で自由に学生生活を送っているようにみえるが、実際は違った。校則も緩かったため、化粧もしている子もいれば、髪の毛を染めている子もいた。しかし、みんな勉強に対しての熱意は鋭かった。どんなに派手に見えて、勉強になんて興味なさそうに見えても、「やるべきときはやる子」ばかりだったのだ。みんな国公立を目指し、できるだけ偏差値の高い大学に入学しようと一年生の頃から頑張っていた。高校の先生も、私たち学生にいつも、こう教えた。「できるだけ偏差値の高い有名大学へ行け。浪人して当たり前。有名大学に通えば、それが就職を成功へと導くんだ!」と。そのような高校で3年間を過ごす中で、私も自然に、全国的に有名な大学に進学することを夢見るようになった。そして、私はいつからか、人生の最終ゴールは大学名にあると思うようになっていた。
高校三年生の秋、私は大学受験を控え、とても悩んでいた。それは、価値観の違いが生んだ大学選びの違いだった。偏差値を重視する大学選び、そこに重点を置かない大学選び。私は、大学受験に向けて、最終的に受験校を決定しようとしていた。私は、全国的に名の通った大学に行くために、県外の大学へ進学したいと思っていた。家族にそのことを相談すると、「女の子が1人暮らしをするのは危ないし、心配だから。家から通える大学にしなさい。」と言われてしまった。その頃の私は、高校の先生や、周りの友達の影響もあって、家族の心配など、まったく受け入れがたいもので、大学受験において妥協など許されないと思い込んでいた。そこで、私は家族との相談の結果、新幹線で家から通える大学と、両親が勧める女子大を受けることに決め、志望校調査票を担任の先生に提出した。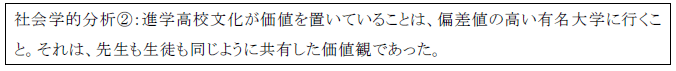 どうして女子大を受験するの?
どうして女子大を受験するの?
それからすぐに一人ずつ、その調査票をもとに、担任の先生と話し合う機会があった。私は、今の自分のレベルからは挑戦にあたる県外の大学と、両親の勧める女子大の二校を受験するつもりだと言うと、先生の表情が曇った。そして、先生は「どうして女子大を受ける必要があるの?あなたは、なんのために、この高校に入学して、今まで勉強してきたの?結婚をするために、今あなたはこの高校にいるわけじゃないでしょ?」と私に問いかけた。私は衝撃を受けて固まった。自分でも、女子大を受験することに対して、少なからず抵抗はあったものの、あれほどまで先生に言われるとは思いもしなかった。今でも、この情景を思い出せるほどだ。それ以来、先生や学校の友達の前では、「努力もできず、すぐ諦める子なんだ。」というレッテルを張られるのが怖くて、それと同時に恥ずかしく感じられ、いくら滑り止めであったとしても、女子大を受験することなど、口が裂けえても言えなかった。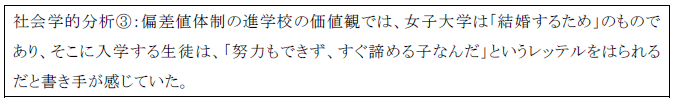
女子大に入学することを決めて
そうして、受験も終わり結果発表。残念ながら、第一志望の県外の大学に落ち、もう一つの女子大に合格するという、私にとって信じがたい結果となった。三年間進学校で過ごし、「偏差値がすべて。有名大学が人生のすべて。」と思い込んでしまっていた私にとって、この結果はとても簡単には受け止められるものではなかった。私は、すぐに家族に、「一年間浪人させてください。」と話をしてみた。しかし、家族は「浪人はやめなさい。女子大に通えばいいじゃない。大学に入るのに、偏差値がすべてではないよ。もっと視野を広げなさい。」と言った。家族は春休みの間中、ずっと私に女子大に通うよう説得し続けた。家族の中だけにいれば、日に日に「女子大に行くのも悪くないんじゃないか。」と思えたりもしたが、高校の友達に会えば、そんな感情は一気に吹き飛んでしまった。「自分は本当にこれでいいの?みんなは、行きたい大学に入れるまで浪人する意気込みなのに。」と自分自身によく問いかけた。私の高校三年生のクラスの子は、半分ほどが浪人を決めていた。彼らにとって、一年間行きたい大学に入るために他の子たちに遅れることなど、全然恥ずかしくないことで、逆に誇りさえ感じられた。そういう姿を見ると、余計に自分自身が恥ずかしく、自分のこれからの人生は終わったようなものだと思った。
春休みが終わる頃、私は大学で留学をさせてもらうことを約束に、しぶしぶながらも女子大へ入学することを決めた。家族はみんな「日本の中なら、どこの大学に行っても、自分次第で同じことを学べる。でも、海外に留学すれば、今までは見た事、感じた事のない事がたくさんあって、そこでしか学べないことがある。だから、同じ一年を過ごすなら、浪人に費やすのではなく、留学した方が、もっと有意義な時間になるんじゃない?」と私に言った。中学生の頃から、いつかは留学に行きたいと思っていた私は、この言葉を信じてみることにした。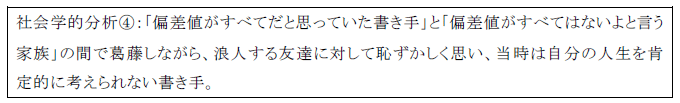
女子大で自信が生まれた
入学式当日。気が進まなかったが、一応入学式へ行った。会場に入ってみると、今までとは違った周囲の雰囲気をすぐに感じ取り、それと同時に戸惑った。「やっぱり私の行きたい大学はここじゃない。」と強く思った私は、家に帰り、母に泣きながらお願いした。「来年もう一度受験して県外の大学に行きたい」と。春休みの間、ずっと私を説得し続けてきた母も、さすがに、私を女子大に通わせ続けるのは無理だと感じたと、あとから聞いた。私は女子大に通いながら、受験勉強を並行してやり、来年もう一度、受験することを心に決めた。
記憶が曖昧だが、たしか入学式の次の日はオリエンテーションがあり、その中で英語のクラス分けのテストがあった。これまで偏差値ばかり追い求めてきた私にとって、テストは重要なもの。そんな私は、このまま女子大に通い続けるのは嫌なのにも関わらず、どうしてもこのクラス分けテストを受けずにはいられなかった。そして、そのテストの結果、私は一番上のクラスに入る事ができた。高校の時には、なかなか結果を残すことができなかった私にとって、このとき中学生以来の快感を久しぶりに味わう事ができた。
こうして始まった大学生活。嫌々とは言いながらも、中途半端は嫌だった私は、心を入れ直して、勉学に励もうと心に誓った。大学での授業を受けるうちに、高校時代は、努力しても、なかなか自分が思うような結果が出せなかったが、ここの大学では自分が頑張れば、頑張るほど、自分の力になり、それが成果としてでるような気がした。その感覚が、私にとって快感になった。高校では、自主自立が基本で、先生は勉強に対して口出しはしても、温かくサポートはしてくれなかった。でも、ここの大学の先生は違った。私が望めば、望むほど、より一層それが叶うように、相談にのってくれたり、温かくサポートしてくれる。そのうえ、だんだん友達も増え、徐々に私は、この女子大に通うのも楽しいかも!?と思えるようにまでなり、自然に来年受験をし直そうという気持ちはなくなっていった。だからといって、周りの人に胸を張って、女子大に通っていることを言えなかったが。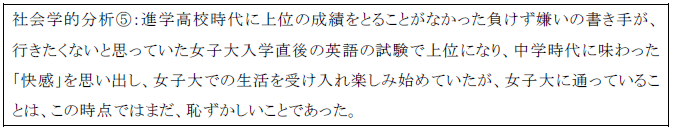 カナダへの留学
カナダへの留学
私は、大学生の間に、英語をペラペラと話せるようになることを夢みていた。二年生の後期に中期留学として、私は大人気であるカナダに留学したい一心で、その選抜に使われる一年生の冬のTOEICでの勉強を頑張った。その結果、TOEICの点数自体は決していいとは言えないが、なんとかカナダへ留学できることになった。そこで、私はその担当であった一人の先生と、一緒にカナダに行く四人の友達に出会った。留学に向け、何度かミーティングをするうちに、カナダに行った先輩方とお会いする機会があり、先輩方の英語の流暢さに感動すると同時に、私たちもこうなりたいとグループ全員で思った。カナダに行くグループの伝統として、留学から帰ってきてからのTOEICの点数の伸びが他に比べ、すごく良いということも知った私たちは、留学前にTOEICグループ全員六百点達成という目標を掲げた。それから二カ月間、範囲となった部分の問題集をやり、随時先生による確認テストが行われた。私は、もう大学生活失敗したくないと思い、確認テストで高得点を取れるように勉強した。しかし、一回目の確認テストは、最悪のものだった。自分ではやったつもりだったが、それは単なる「やったつもり」であって、全然自分の力になっていなかったのだ。その時、先生に言われた言葉は「これで、本当に勉強したの?」だった。私は、本当に悔しかった。でも、この悔しさが私を変わらせてくれた。やったつもりではなく、自分の力になる勉強をしなきゃいけないと。それからは、勉強方法も変え、今まで以上に努力した。ただでさえ、大学の英語の授業は宿題が多いというのに、そのうえにTOEICの勉強もしないといけなかったため、ほぼ毎日三時間ぐらいしか寝られない日々が続いた。学校でも、お昼や空き時間、少しでも時間があれば、TOEICの勉強をした。そんな生活が時々、嫌になることもあり、たまに泣きながらTOEICの公式問題集を解いていたような気もする。しかし、その結果、私は留学前に、六百点を超えるという目標を達成する事が出来た。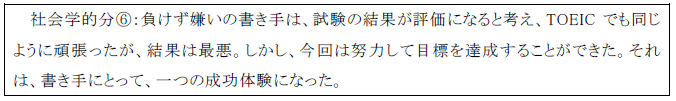 ある程度TOEICの点数もあることだし、会話も困らないのではないかと、甘い考えでカナダへと飛び立った。そして始まった七か月間のカナダでの留学生活。はじめに直面することになった困難は、ホームシックであった。私は、日本にいる間は家族に頼ってばかりの生活を送っていたため、初めて家族から離れて生活をすることになり、とても戸惑った。それに加え、私は自分の語学力の足りなさ。はじめは自分が相手に伝えたいことを、まったく伝える事ができず、自分の語学力の足りなさを痛感させられる日々が続いた。楽観的に、留学に行きたいなどと言った自分に、とても後悔し、毎日日本に帰れる日までの残りの日数をカウントした。そんなとき、いつも周りの友達が私の心の支えになってくれた。そのおかげで、カナダの生活にも慣れてきた頃、徐々に「このまま気持ちが落ち込んだままでは、せっかくの貴重な七ヶ月が、なにも残らない無駄な七ヶ月になってしまう」と思い直せるようになった。
ある程度TOEICの点数もあることだし、会話も困らないのではないかと、甘い考えでカナダへと飛び立った。そして始まった七か月間のカナダでの留学生活。はじめに直面することになった困難は、ホームシックであった。私は、日本にいる間は家族に頼ってばかりの生活を送っていたため、初めて家族から離れて生活をすることになり、とても戸惑った。それに加え、私は自分の語学力の足りなさ。はじめは自分が相手に伝えたいことを、まったく伝える事ができず、自分の語学力の足りなさを痛感させられる日々が続いた。楽観的に、留学に行きたいなどと言った自分に、とても後悔し、毎日日本に帰れる日までの残りの日数をカウントした。そんなとき、いつも周りの友達が私の心の支えになってくれた。そのおかげで、カナダの生活にも慣れてきた頃、徐々に「このまま気持ちが落ち込んだままでは、せっかくの貴重な七ヶ月が、なにも残らない無駄な七ヶ月になってしまう」と思い直せるようになった。
留学先での勉強
それから、心を入れなおし、語学力を身につけようと必死になった。しかし三か月が経っても、一向にスピーキング力が伸びる気配がなかった。周りのみんなは、順調にスピーキング力を身に付けられているように思った。それにもかかわらず、私の場合は、来た時となんら変わらないスピーキング力。あと四カ月で日本に帰らなければいけないのに、スピーキング力がまったく上がらないという焦りから、涙を流す日もあった。このままでは四カ月後日本に帰れないと思った私は、カナダ担当の先生にメールで相談してみる事にした。すると、先生は「三つの特訓(音読を五〇回・鏡を見ながら独りごと三〇分・授業で発言する内容の準備)を一カ月続けなさい。そうすれば、次第に効果が現れます。」と言って、アドバイスをくれた。留学に行く前のTOEICも、先生のアドバイス通り信じて勉強したら、みるみるうちに点数が伸びたから、今回の先生のアドバイスも信じて続ければ、絶対に効果が現れると思った。そこで、すぐにその特訓を毎日欠かさず始めた。毎日出されるたくさんの宿題に加えての三つの特訓は、とても大変だった。それと同時に、私の会話をする際の態度を見つめ直す事にした。それまで、語学力不足のせいもあって、自分から話しかけるというよりは、周りの人から話しかけてもらい、それに答えるといった受け身のコミュニケーションをしていた。だから、人よりもスピーキング力が伸びるのに時間がかかってしまうのかもしれないと思った。そこで、私も周りの積極的に会話をする友達を見習って、自分から周りの人に声をかけるように努力した。
そのような特訓の日々を過ごし、留学もあと残り一か月ほどになった頃。自分でも気づかないうちに、ホストファミリーと、三カ月前にはできなかったようなテンポのいい英語での会話ができるようになっていた。私が留学行く前に夢見ていたように、ペラペラと英語を話せるようになっている自分自身がはじめ信じられなかった。見事に、その特訓の成果が現れたのだ。周りの友達やホストファミリーからも、「最近、スピーキング力上がったんじゃない!?」と言ってもらえるようになった。とても嬉しかった。「先生のアドバイスはいつも正しい!先生出会えて、よかった。」とほんとうにそう思った。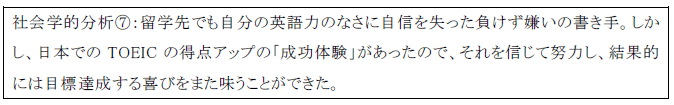
帰国してからの私
こうして、留学生活も終わり、日本に帰国した。次の課題は、TOEICで八百点を取る事だった。カナダに留学に行った先輩たちが、八百点を取っていたので、私にも絶対できるはずと思った。留学中はスピーキング力を磨くことを中心にしてきたが、帰国してからは、留学前にしていたTOEICの勉強法をもう一度思い出し、繰り返し繰り返し、同じ参考書を解いて、勉強した。そして、帰国後3カ月後に、見事八百点を超えることができた。自分でも、信じられなかった。高校時代には、やってもやっても、全然結果を残すことができなかったのに、大学に入ってからは、努力すればすべて良い結果となって返ってくることが。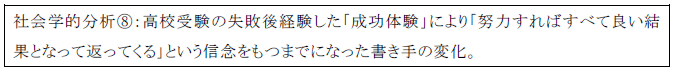
就活で初めて望んだ道へ
大学三年生の冬。ついに就職活動が始まった。私は、父の影響もあり、自動車関係の会社で働くことを夢見ていた。大学生活で私が力を入れてきた英語を活かして働きたいと思った。先生にアドバイスを貰いながら、履歴書を作成したり、面接の練習をしたりと、忙しい日々を送った。今回の就職では、もう失敗できないと思った。今まで、高校受験も、大学受験も、自分の望んだ第1志望には合格できなかった。でも、今回はできることは大学生活すべてこなしてきたし、あとは今まで蓄えてきたすべての力を発揮し、絶対に夢を叶えるんだと心に誓った。そうして、書類選考、何度かの筆記試験、面接試験を突破し、四月の終わり、第一志望の企業から内々定を頂く事ができた。本当に嬉しかった。はじめて自分の望んだ道に進めたように思った。家族も、いつも第一志望に進めない私が、今回初めて、望んだ道に進めることにより、とても喜んでくれた。
偏差値がすべてではない
今まで、思うように進めなかったり、いろいろな困難に出会ったけれど、それらはすべて今の自分に繋がるためのステップだったのかもしれないと思い、このとき初めて大学受験での失敗に、しっかりと向き合えたように思う。大学に入ったばかりの頃は、女子大にしか入れなかった自分を恥ずかしく思ったけれど、今は胸を張って、この大学に入ってよかったと言える。この大学にいなかったら、温かくサポートしてくれる先生や、同じ目標に向かって頑張りあえる友達とも出会うことができなかったから。高校まで偏差値ばかりに、捕らわれていた自分は、いったいなんだったのだろうか。偏差値が、人の人生をすべて左右するはずがないのに。あのころの私は、自分の中では頑張っているつもりだったが、それは単なる「つもり」であり、自分に甘かったのだと、今ふり返ってみて思う。あの頃は、偏差値だけで、進学先の価値を見出していただけだから、自分自身の目標に対する本気さが足りなかったのだろう。大学受験に失敗して、そのとき両親から、新たな価値観を教えてもらえて本当に良かったなと思う。あのとき、「人生偏差値がすべてではない」という新しい価値観を学べたからこそ、私自身の視野、世界観が広がり、人間としてまたひとつ成長できたように感じる。いつも、どんなときも、私を近くで支えてくれた家族には、本当に感謝の気持ちでいっぱいだ。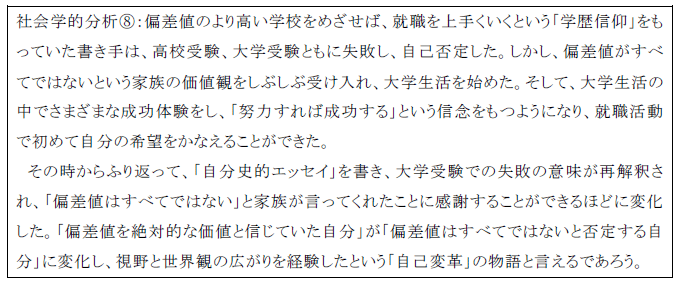 (3) 自分史的エッセイの社会学的分析のまとめ
(3) 自分史的エッセイの社会学的分析のまとめ
上記の「自分史的エッセイ」を書いた二人は、日本の受験体制下、「偏差値」をすべてを評価する基準として考えていた。そして、二人は共に「学歴信仰」を信じていた。その「学歴信仰」が内面化され、主観的リアリティとして位置づけられたのは、現代日本における塾あるいは予備校が「偏差値」を制度化し、受験指導において絶対的なパワーをもたせた結果であった。
そして、受験指導をする塾の教師、学校の教師が受験体制における偏差値をベースにした高校の階層構造を強化する役割を果たし、生徒たちにその階層構造を植え付ける役割をはたしている。
この二人の書き手は、偏差値体制の中で、高校受験あるいは大学受験でいったんは敗北を味わい、それが一種のスティグマになることはあったが、二人はそれぞれ別な方法で、偏差値体制を否定するまでの「自己変革」を経験することになる。
受験や勉強を重視しない「女子校文化」を経験した書き手Bは、「偏差値や勉強を重視していた自分」から、「個を重視し、学生生活を楽しむ自分」に変化し、大学に入学しても、今の生活を楽しむことに価値をおいていった。また、大学受験をめざす偏差値体制の進学校では、「成功体験」を経験できなかった書き手Aは、英語の勉強、留学体験を通して、「努力すれば成功する」という経験をし、自信をもつようになり、偏差値によって否定されていた自分を肯定するようになった。
この二人が、「自分史的エッセイ」を書いたのは、それぞれが夢だと思っていた就職先から内定を受け取ってからのことであった。人生の中で自分の願いがかなった時、今までのさまざまな苦しかった経験が今の自分に必要な、意味ある体験として再解釈された。また、人生における出来事を「何かの縁」で解釈する親に反発していた書き手Bは、希望がかなった経験をしたことで、その親に共感し、いままで起こったことを肯定的に解釈し、外的評価である「偏差値」を否定した。また、「偏差値がすべてでない」と言った母親に対して反発した書き手Aも、「努力すれば、全て良い結果になる」という経験をする中で、「偏差値はすべてではない」と母親に言われたことを感謝するようになった。
この二人の経験した日本の偏差値体制の価値観は、すべての人に影響力をもつように思われるが、この二人の「自分史的エッセイ」に見られたストーリーを時間軸を入れて分析することで、偏差値重視の価値観も、受験での「敗北」というネガティブと思われている経験を通して、影響力を失うものだということが明らかになった。受験体制の中で絶対的だと考えられている「偏差値体制」という神話は、必ずしも絶対的なものではないことが、主観的リアリティを表現している具体的なストーリーを通して明らかにすることができた。このように考えると、ストーリーの社会学的分析の役割は、一人ひとりの主観的リアリティを理解し、人びとの中にどのような共通した問題あるいはテーマが存在するかを明らかにし、一人ひとりの個別的な問題に対して、共感できる洞察を提供することではないだろうか。
参考文献
アトキンソン、ロバート 2006、『私たちの中にある物語』ミネルヴァ書房
アトキンソン、ロバート 2013年3月、“Best Practices of Life Story Interviewing” 岐阜県立
看護大学でのセミナーで発表
スタインホッフ、パトリシア 1986、インタビュー
塚田 守 1998、『受験体制と教師のライフコース』多賀出版
塚田 守 1991、『女性教師たちのライフヒストリー』青山社
塚田 守 2008、『教師の「ライフヒストリー」からみえる現代アメリカ』福村出版
塚田 守 2004、『私たちの告白―9人のライフヒストリー』(自費出版)
塚田 守 2012、『就職活動のさまざまなストーリー』(自費出版)
塚田 守 2013、『就活女子』ナカニシヤ出版(出版予定)
山口智子 2004、『人生の語りの発達臨床心理』ナカニシヤ出版